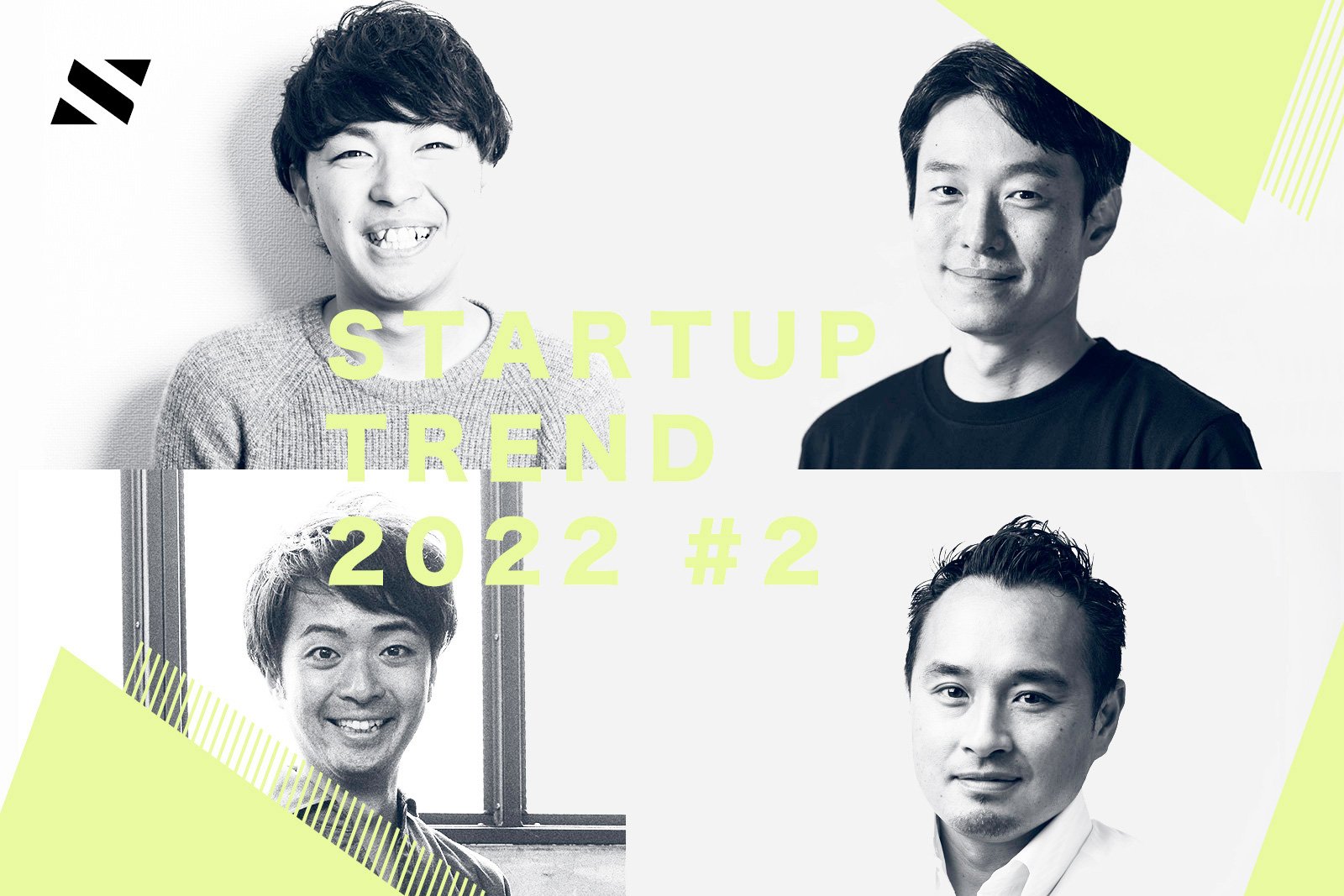
2020年に引き続き、新型コロナの影響を大きく受けた2021年。人々の生活様式はさらに変化し、その影響は大企業からスタートアップまでを巻き込んでいる。果たして2022年はどんな年になるのか。
DIAMOND SIGNAL編集部では昨年と同様に、ベンチャーキャピタリストやエンジェル投資家向けにアンケートを実施。彼らの視点で2021年のふり返り、そして2022年の展望と注目の投資先について語ってもらった。第2回はTHE SEED General Partner 廣澤太紀氏、KUSABI 代表パートナー 渡邉佑規氏、ANRI ジェネラルパートナー 鮫島昌弘氏、グロービス・キャピタル・パートナーズ代表パートナー 今野 穣氏の回答を紹介する。
THE SEED General Partner 廣澤太紀
2021年のスタートアップシーン・投資環境について
若手起業家の資金調達が困難に
プレシード/シードステージで若手起業家に投資活動をする中で、個別企業によって違いはあるものの、全体としては過去の事業実績がない起業家が資金調達することは難しくなっていると感じます。
過去の実績がない中で資金を集めるには事業の進捗が重要になるものの、資金を集めることが難しいため、進捗も出しづらい状況になっています。
スタートアップへの資金供給量は増えましたが、「若手×創業期」の資金調達は以前よりも難しくなった1年のように感じました。




