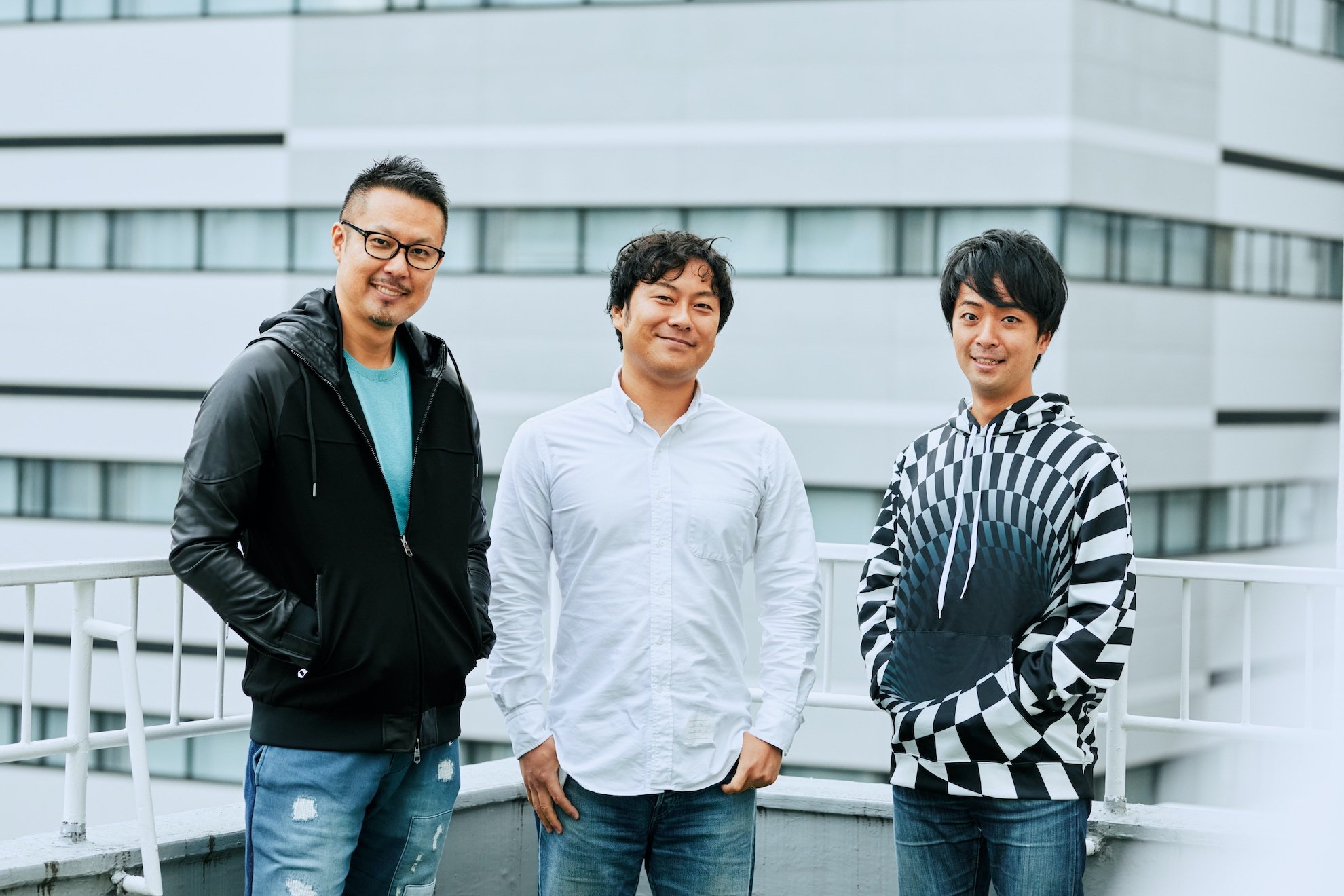
2050年には日本を代表し世界を牽引するグリーン・ジャイアントと呼ばれるような企業を創出したい──。そう話すのは独立系VCのANRIでジェネラル・パートナーを務める鮫島昌弘だ。
現在4つのファンドを通じて累計約350億円を運用するANRIでは、2012年の1号ファンド設立時よりシード期のスタートアップへの投資に注力してきた。2017年に立ち上げた3号ファンドからは投資対象を拡張し、鮫島氏らを中心に研究開発型のディープテック企業の支援にも積極的に取り組んでいる。
そんなANRIが、1月26日に気候変動や環境問題に特化した新ファンド「ANRI GREEN 1号(以下 グリーンファンド)」の運用を始めた。
同ファンドを通じて太陽光や風力、蓄電池、核融合など“脱炭素”や“クリーンテック”に関連するスタートアップへの投資を加速させる計画。ファーストクローズの段階で産業革新投資機構や関西電力グループであるK4 Venturesなどから43億円を集めており、最終的には総額で100億円規模を目指すという。
なぜ従来運用してきたファンドとは別で、新たに領域特化型のファンドを立ち上げたのか。その背景や狙いを鮫島氏とANRI代表パートナーの佐俣アンリ氏に聞いた。




