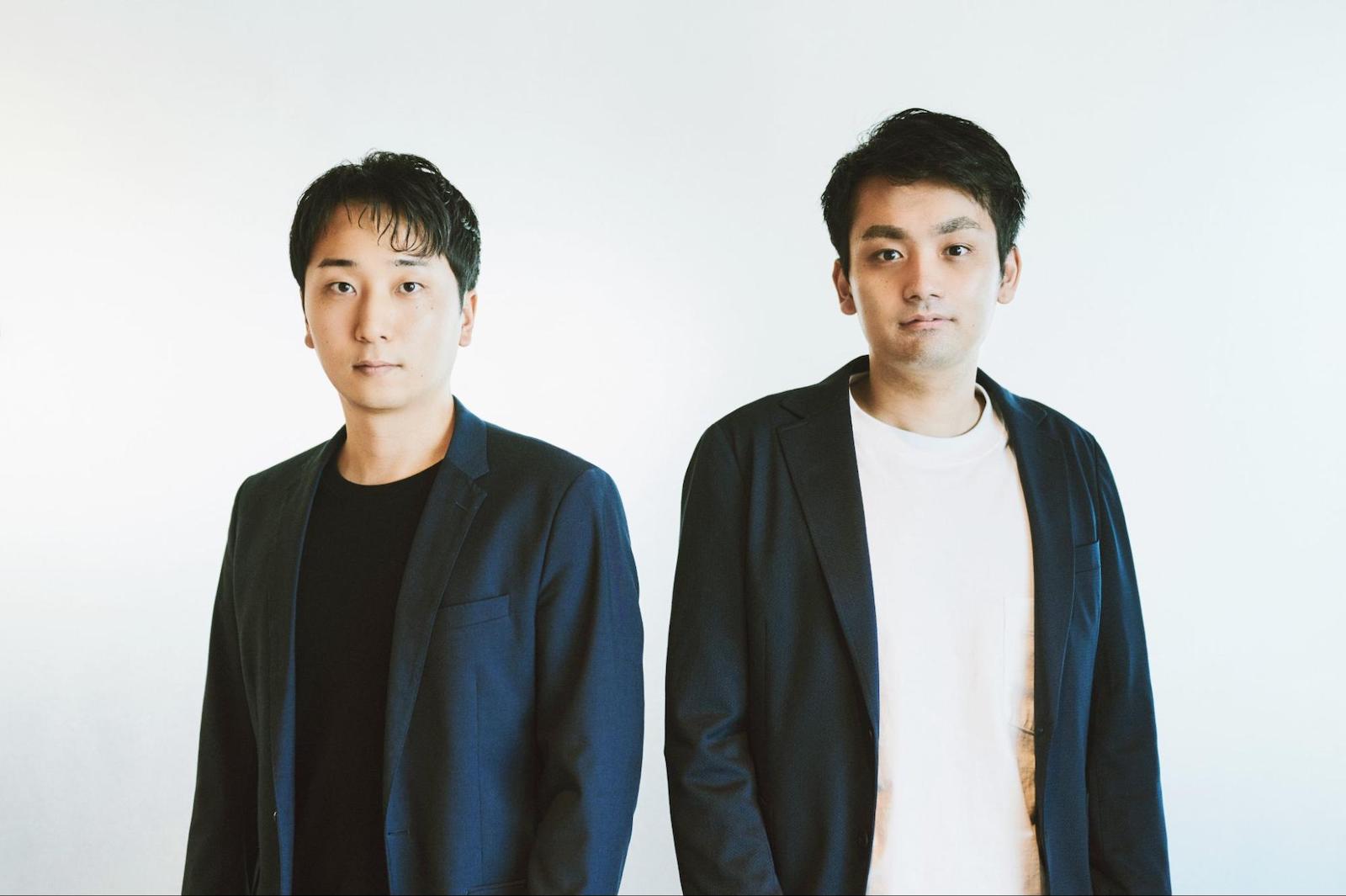
生鮮食品や日用品などをオンデマンドで配送するグロサリーデリバリーサービス。海外では2012年創業でユニコーン企業のInstacart(インスタカート)が市場の代表格として知られており、その後AmazonがWhole Foods、WalmartがJet.comを買収する形で大手企業が市場に参入した。
最近は米国発のJOKR(ジョーカー)やロシア発のBuyk(バイク)、ドイツ発のGorillas(ゴリラズ)、トルコ発のGetir(ゲティール)など、VCマネーで急成長を目指す新興サービスが多く立ち上がり、グロサリーデリバリー市場の競争が激化している。
一方、日本では生活圏の中にコンビニやスーパーがあることが多いことから、海外と比べてデリバリーサービスの需要はそこまで高くなかった。しかし、コロナ禍で状況が変わりつつある。
生活様式が大きく変わり、外出を控える人が増えた結果、デリバリーサービスを利用する人が増加。それに伴い、市場規模も大きくなっている。ICT総研が実施した「フードデリバリーサービス利用動向調査」によれば、2018年に3631億円だった市場規模は2021年に5678億円、2023年に6821億円へと拡大することが予測されている。
コロナ禍で高まる「自宅にいながら、必要なものが手に入る」という需要に目を付けたのが、料理レシピ動画サービス「クラシル」を展開するdelyだ。




