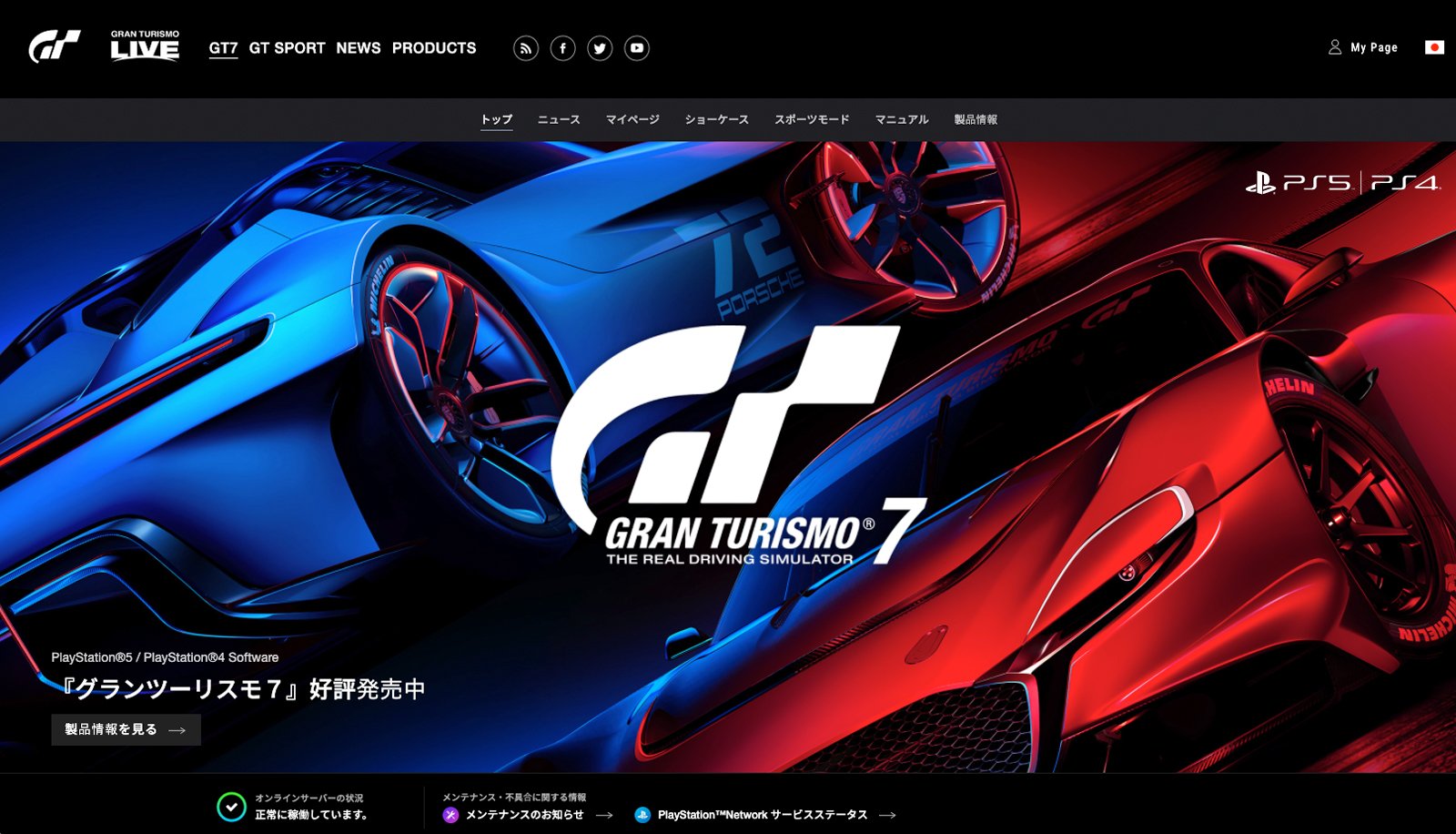
ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)自社販売タイトルの中でも25年の歴史を持ち、世界中にファンを持つ『グランツーリスモ』シリーズ。その最新作で3月4日に発売された『グランツーリスモ7』の評価が揺れている。
世界のゲームメディアが下した評価をまとめているウェブサイト「Metacritic」のメタスコアは100点満点で87点と、なかなかの高評価。一方で、ユーザー投票によるスコアは10点満点の1.8点。これは、筆者の知る限り、全PlayStation用ソフトの中で最低の点数だ。
なぜメタスコアとユーザースコアとの間で、ここまで大きな乖離(かいり)が生まれたのか。順を追って説明していこう。
「クルマのシミュレーター」としての評価は世界最高クラス『グランツーリスモ』
『グランツーリスモ』シリーズは1997年末にPlayStationで発売された初代から、現在まで25年の歴史を持つ大人気シリーズ。ジャンルは「レース」ではなく「ドライビングシミュレーター」を名乗るほど、物理法則の再現を重視した「シミュレーター」に徹しているのが特徴だ。
2016年に開催されたFIA(国際自動車連盟)主催の『グランツーリスモSPORT』の大会で世界チャンピオンとなった冨林勇佑選手。彼が2018年には実車のレーサーとしてもデビューし、「スーパー耐久シリーズ」でシリーズチャンピオンになったと聞けば、このゲームのリアルさも伝わるのではないだろうか。




