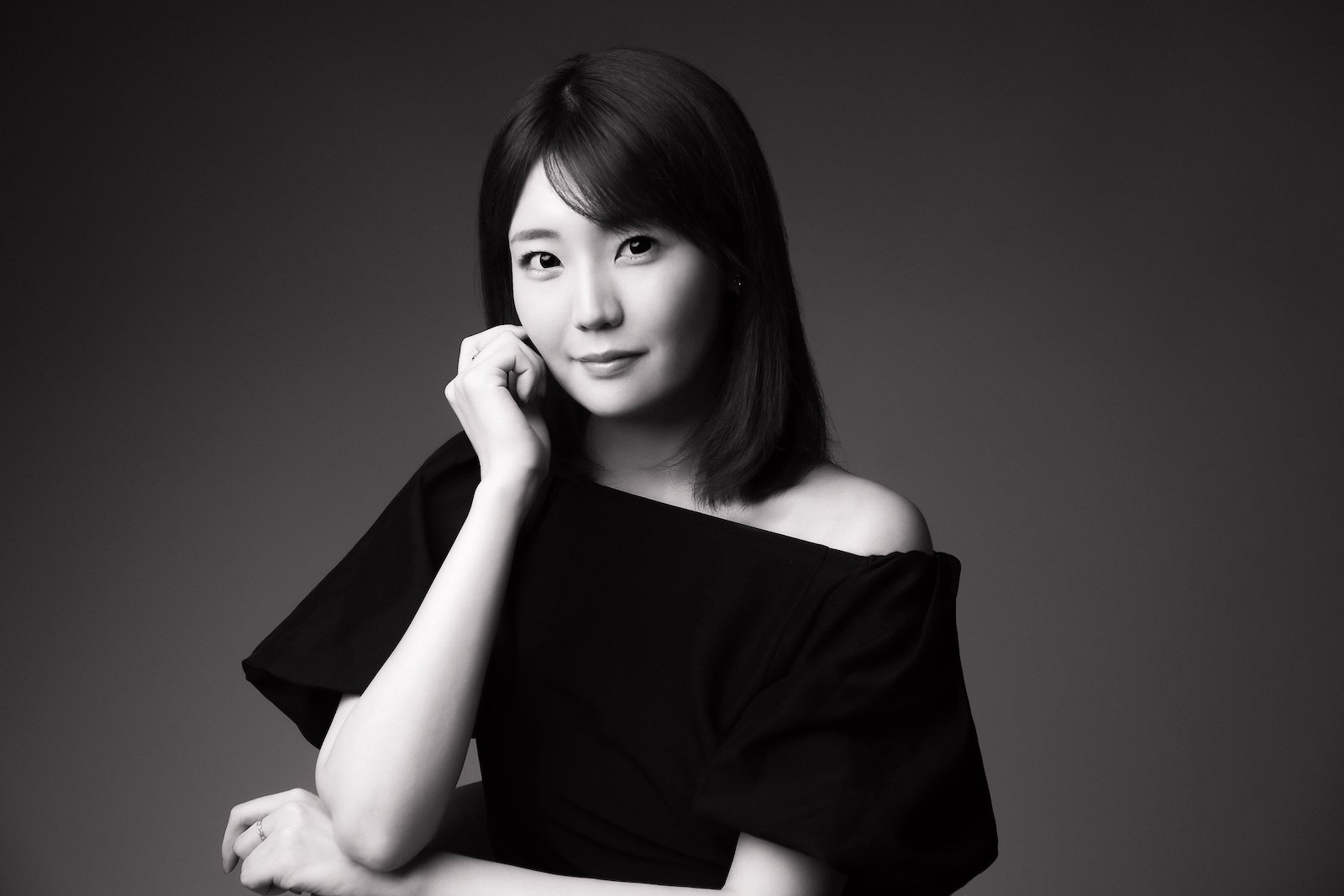
連載「アニマル・スピリット最前線」では、ノンフィクションライターの石戸諭氏がアニマル・スピリット──つまり溢れんばかりの好奇心に突き動かされる人たち、時には常識外とも思えるような行動を起こす人たちの思考の源泉に迫っていきます。第1回に話を聞いたのは、ROSE LABOの田中綾華氏です。
新型コロナ禍でも原則出社、社員全員でラジオ体操、朝礼、行動指針の唱和、業務の最後に日報を書いて提出する──字面を見れば、いかにも昭和の日本企業である。これは、新世代の「六次産業」の旗手として注目を集めるベンチャー企業「ROSE LABO」のブレない方針だ。社長、田中綾華氏がたどり着いた危機を乗り越える新世代のネオ昭和経営術とは。
コロナ禍の経営危機を救った、起死回生の一手
東京・六本木、といっても煌びやかなオフィスビルではなく、駅から少しばかり歩いた古いマンションの一室にROSE LABOの東京事業所がある。
1993年、東京に生まれた大学生が「食べられるバラ」に魅せられ、食用バラ業者に飛び込み、まったくの素人から栽培方法を学ぶ。埼玉県深谷市に生産拠点を確保し、2015年に起業してから、わずか3期で年商1億円の売り上げを達成する。食用バラに加え、バラをつかった加工食品と化粧品を展開、販売まで手がける戦略も当たり、南青山の一等地にオフィス兼路面店を構える田中のサクセスストーリーは多くのメディアの注目を集めた。
「私の中で調子に乗っていた時期でもあった、と今になったら思います。私たちの努力には見向きもせず、『若い女性だから注目もされるよね』という陰口にもまともに反応しすぎていました。わかりやすいかたちで自分たちも成功したのだ、と示したいと思っていましたが、新型コロナ禍でそんなことを考えている時期は終わりました」




