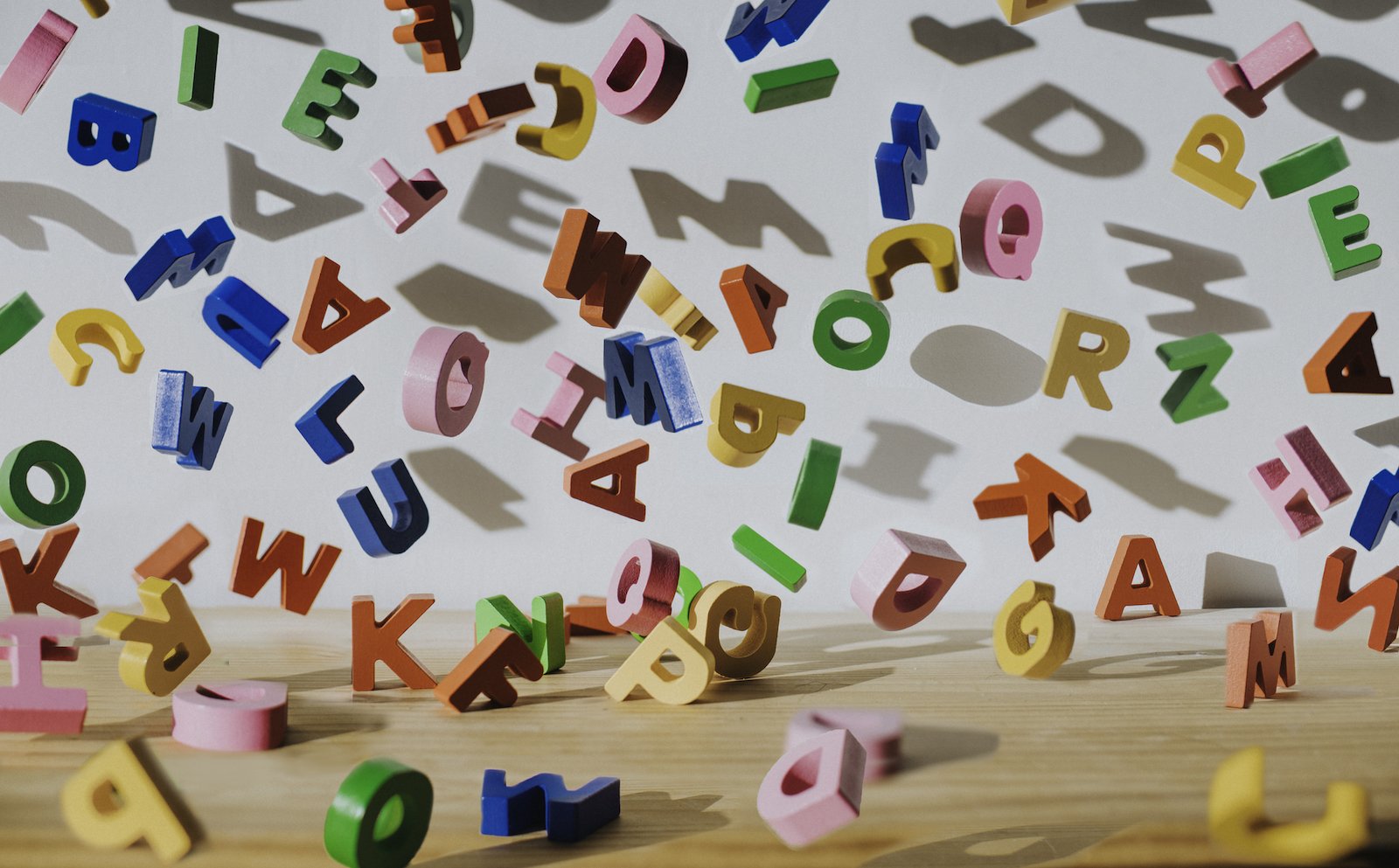
「英単語は正しいプロセスでインプットすれば誰でも覚えることができる」と語るのは、スギーズ英語発音教育研究所代表の杉本正宣氏だ。同所は言語学者の古川慧氏監修のもと、英単語を効率よく覚えられるアプリ「意味と音」を開発した。
先日、応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」でプロジェクトを開始したところ、約1カ月で1100人超のサポーターから、約900万円の支援が集まっている(7月末から一般にもリリースを予定している)。なぜ、スギーズ英語発音教育研究所は英単語を効率よく覚えられるアプリを開発することにしたのか。以下は、杉本氏によるコラムである。
Appleの意味は「りんご」じゃない
英語を学ぶ際、まず最初に目にするであろう単語「Apple」。このAppleの“意味”とは何だろうか。多くの人はりんごと答えるかもしれないが、実はこれは意味ではない。
りんごはappleの意味ではなく「Appleの日本語訳」に過ぎない。では意味とは何なのか。それは、りんごの見た目・匂い・味・食感など言葉になる前のイメージのこと。赤くて丸いあの果物のイメージそのもの、これこそがAppleの意味なのである。
これは理論言語学をヒントに導き出した考え方で、日本人にとっては梅干しを例に挙げるとわかりやすい。梅干しという日本語を見たとき、ほとんどの日本人は酸っぱい味を想像し、唾が出てくる。りんごも同じで、日本語で「りんごの意味って何ですか?」と質問されたとき、頭に浮かぶのは「丸くて赤い果物」なはずだ。




