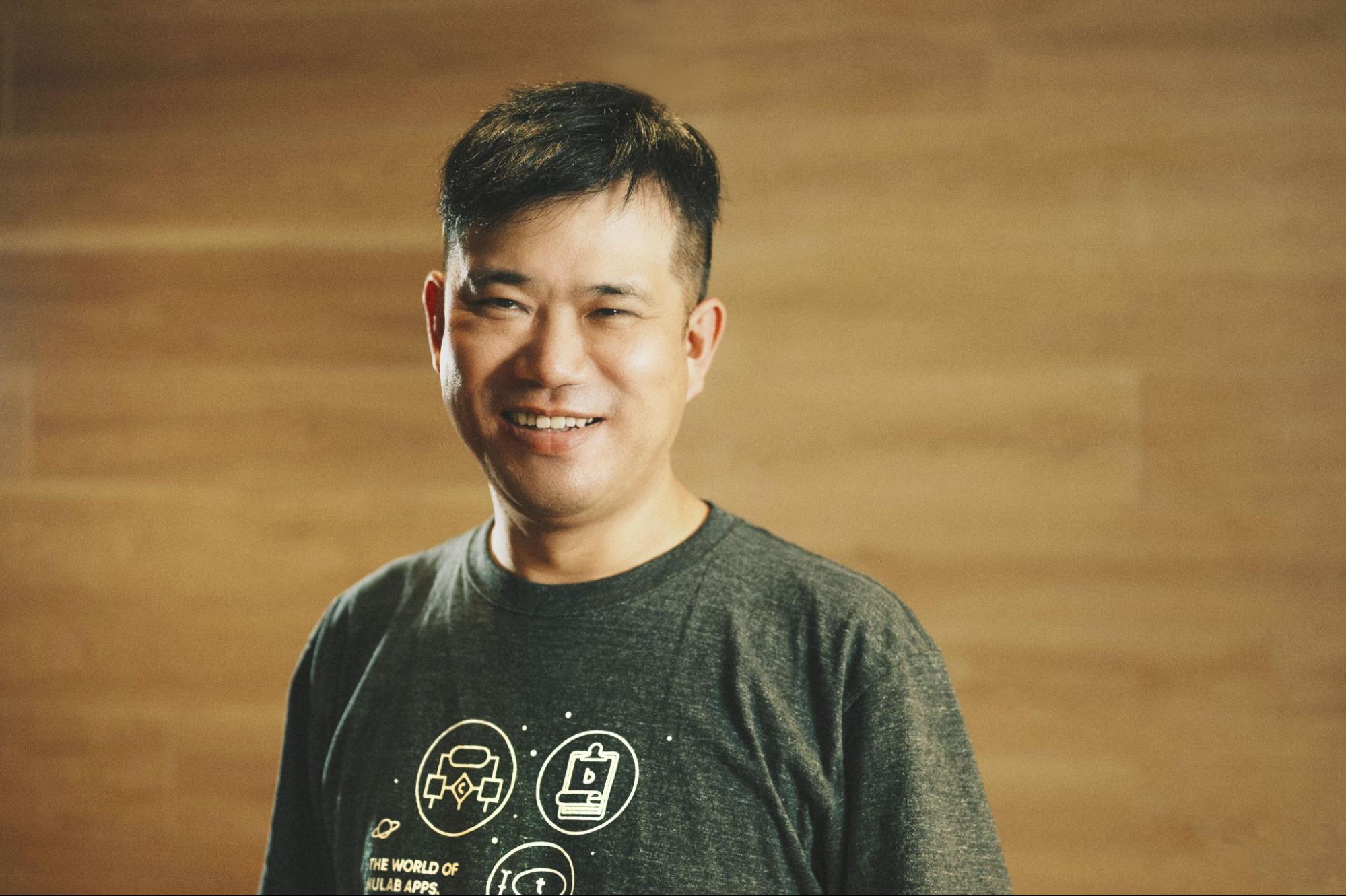
起業や資金調達、ベンチャーキャピタルといった単語が盛んに飛び交うようになる前、いわば“スタートアップ夜明け前”とも言える2004年──「ソフトウェアはアートだ」というコンセプトを掲げ、福岡で立ち上がった会社がヌーラボだ。
プロジェクト管理ツール「Backlog(バックログ)」や、オンライン作図・共有サービス「Cacoo(カクー)」、ビジネスチャットツール「Typetalk(タイプトーク)」を展開する同社は創業から約18年を経て、6月28日に東証グロース市場に上場した。
ベンチャー企業の創業5年後の生存率は15%、10年後は6.3%、20年後はわずか0.3%とも言われている中、18年間、着実に成長を遂げてきたヌーラボ。代表サービスであるBacklogの有料契約者数は102万件を突破している。この十数年の間でさまざまなコラボレーションツールが登場する中、ヌーラボはどのように成長を遂げてきたのか。上場に際し、代表取締役の橋本正徳氏にこれまでの歩みについて振り返ってもらった。
「収入を上げたい」という思いが起業の原点
──2004年の創業から18年が経ちました。
自分が起業した時代と比べると、起業環境は変わりましたね。それこそ、2004年当時は株式会社の設立には1000万円以上の資本金が必要かつ、役員として3人以上の取締役、1人の監査役が必要など起業のハードルはすごく高かった。




