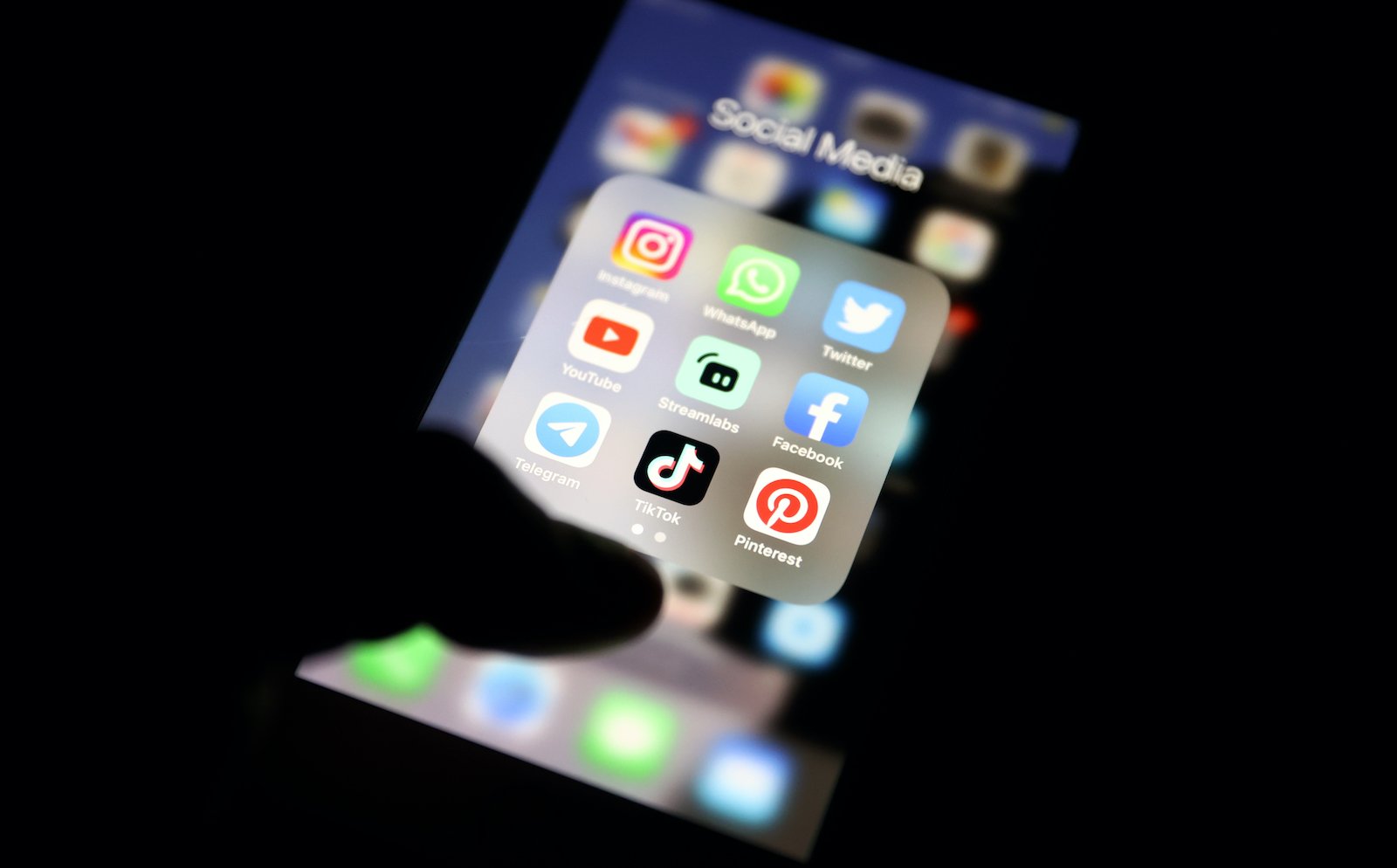
若年層女性向けSNSメディア「Sucle(シュクレ)」やSNSマーケティング事業を展開するFinT代表の大槻祐依氏が対談を通して、ヒットするモノの裏側にある法則をひも解いていく本連載。今回は特別編として、大槻氏によるZ世代の消費行動の変化に関する分析をお届けする。
企業がZ世代(1990年代後半から2000年代後半の間に生まれた世代)を意識したマーケティングをするのも、今や定番となりつつある。例えば、セレクトショップのBEAMS(ビームス)は「BeAMS DOT(ビームスドット)」というZ世代向けのオリジナルブランドを立ち上げた。同ブランドは、Z世代が抱える「オンラインショップでの買い物を失敗したくない」という課題に対して、商品写真の撮影では“リアルさ”を重視したほか、等身大のモデルが商品を着用するなど、オンラインにおける購買の負担を下げ、スムーズに買い物ができるといった点を大きな特徴としている。
FinTにもZ世代の集客や売上に悩む企業からの問い合わせが増えているが、それはZ世代のトレンドや興味関心の変化のスピードが凄まじいからだろう。
マーケティング業界では一般的に、年齢層が上がるほど商品の価値を慎重に吟味する傾向があるため、商品を認知してから購買するのに至るまで、意思決定に時間がかかると言われている。一方、Z世代はデジタルネイティブと言われているように、生まれた時から情報過多の世代であるため、一度に大量の情報を精査し、判断するのがこれまでの世代と比べて早いと言われている。
また、Z世代の特徴のひとつに「自己表現を大切にする」というものがある。彼らは消費活動を行う上でも商品やサービスを通じて自分らしさを発揮できることを重視しており、その情報収集の過程でコミュニティを作っていくという。




