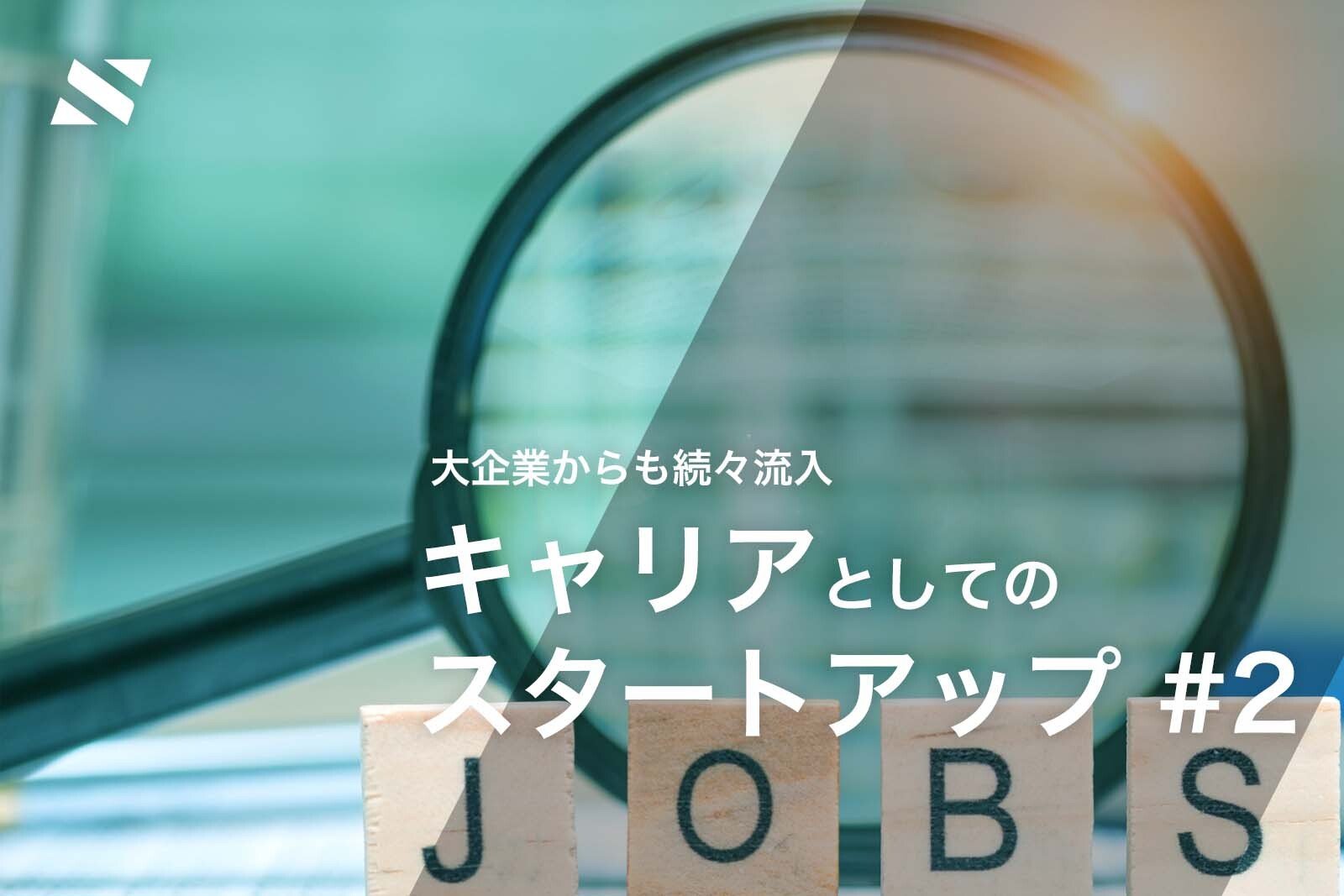
大企業からスタートアップへ──ひと昔前であれば、ハイリスクとも思われていたようなキャリアを選択する人が増えている。そこにはスタートアップへの転職が「堅実なキャリア戦略の選択肢のひとつになっている」という考えがあるという。
なぜ、スタートアップに転職する大企業出身者が増えているのか。その背景にあったのは、会社と個人のキャリアに関する認識のズレだ。特集「スタートアップ転職のリアル」の第2回では、「大企業からスタートアップへの転職が増えているワケ」について見ていく。
大企業と個人のキャリアの価値観がずれている
個人がキャリアを通して身につけたいスキルは“いつでも高い価値で雇用される“という「市場での汎用性」。一方で大企業が社員に身につけてほしいと思うスキルは「自社での汎用性」であることも多い──転職サイト「ONE CAREER PLUS」を運営するワンキャリア事業開発/キャリアアナリストの長谷川嵩明氏とEvangelistの寺口浩大氏はこう話す。「個人の求めるキャリアと企業側が用意するキャリアで得られるスキル、またチャレンジできる領域といったものがここ数年でズレてきた」(長谷川氏)。若い世代は特にこのズレを実感してしまうと、「この会社で長く働き続けるのは良くない」と考えるのだ。
さらに、コロナ禍でリモートワークが増え、マネジメントが放任気味になっていることも、若手社員を不安にさせ、転職を後押ししていると考えられる。
大手有名企業が倒産したり、海外資本に取り込まれたり、先行きが見通しにくい時代。勤める企業が大きいことは必ずしも将来の安心につながらない。仮に会社が倒産してしまっても、他社から必要とされるスキルを持ち、市場価値を高めておくこと、そのスキルセットを磨くことが安心につながると考える個人が増えているのだ。




