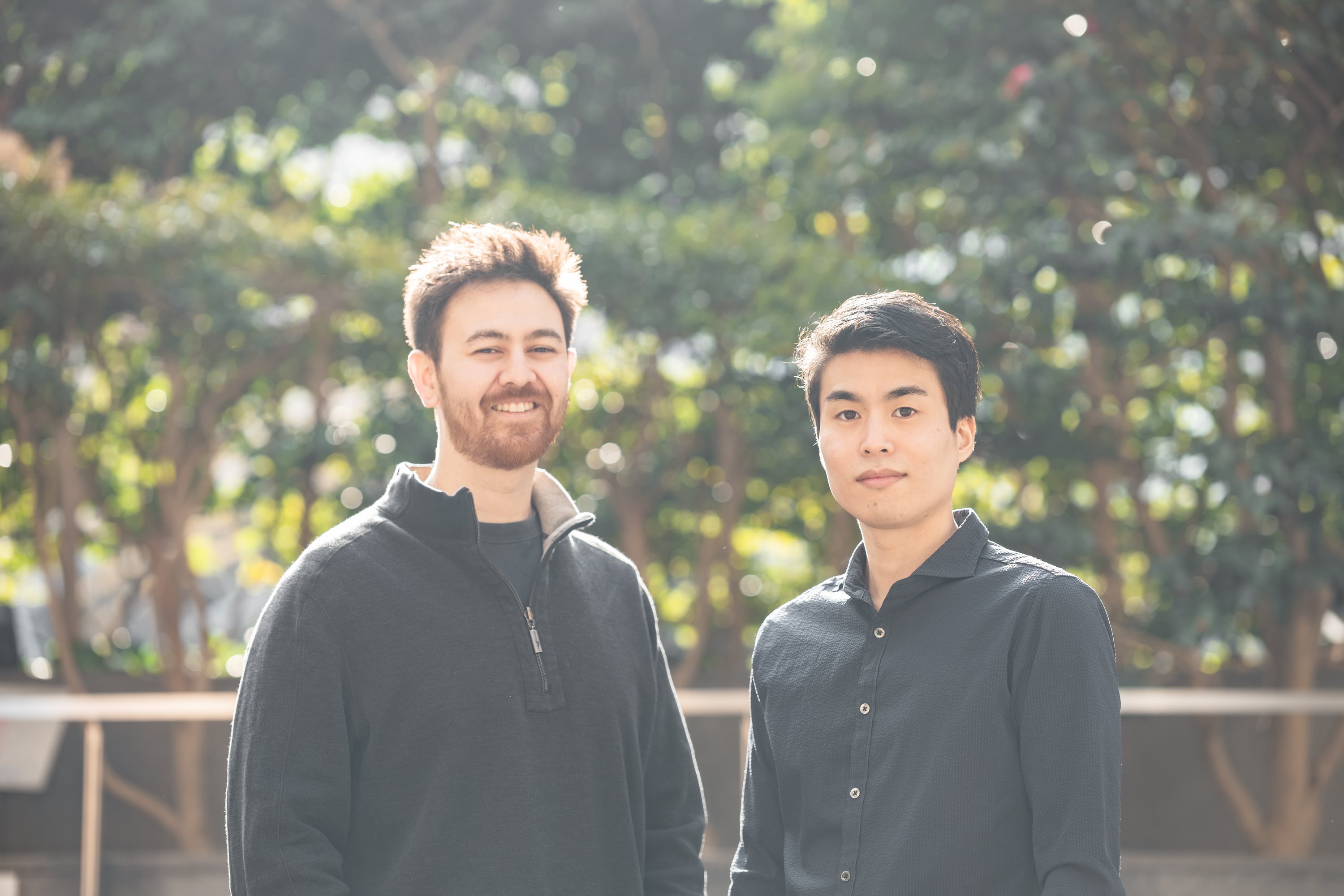
米国の大手テック企業を筆頭に、IT業界にレイオフの波が押し寄せている。次々と著名なメガベンチャーや有望なスタートアップの人員削減に関するニュースが報じられ、海外のテック系メディアではレイオフ関連の記事を見ない日の方が珍しいくらいだ。
レイオフに関する海外の記事をいくつか見ていくと、情報源として“あるサイト”の名前をたびたび目にする。「Blind(ブラインド)」という社会人向け匿名SNSだ。
Blindの特徴は実名制のSNSでは難しかったような、キャリアに関する“本音の議論”がしやすいこと。例えば実際の投稿の中には、「A社とB社からこの条件でオファーをもらったが、どちらを選ぶか」「今年の昇給額とボーナスの金額をみんなでシェアする」といったように、生々しいものも多い。直近ではまさにレイオフの情報が共有される場所として盛り上がっており、ユーザー数は700万人を超える。
そんなBlindの“日本版”とも言えるサービス「WorkCircle(ワークサークル)」が、3月8日に本格始動した。
WorkCircleはBlindと同様、企業で働くビジネスパーソンを対象とした匿名SNSだ。運営元のHonneWorksでは今回の正式リリースに先駆けて2022年12月から試験版を運用しており、すでに約250社・1300人以上のユーザーが登録している。




