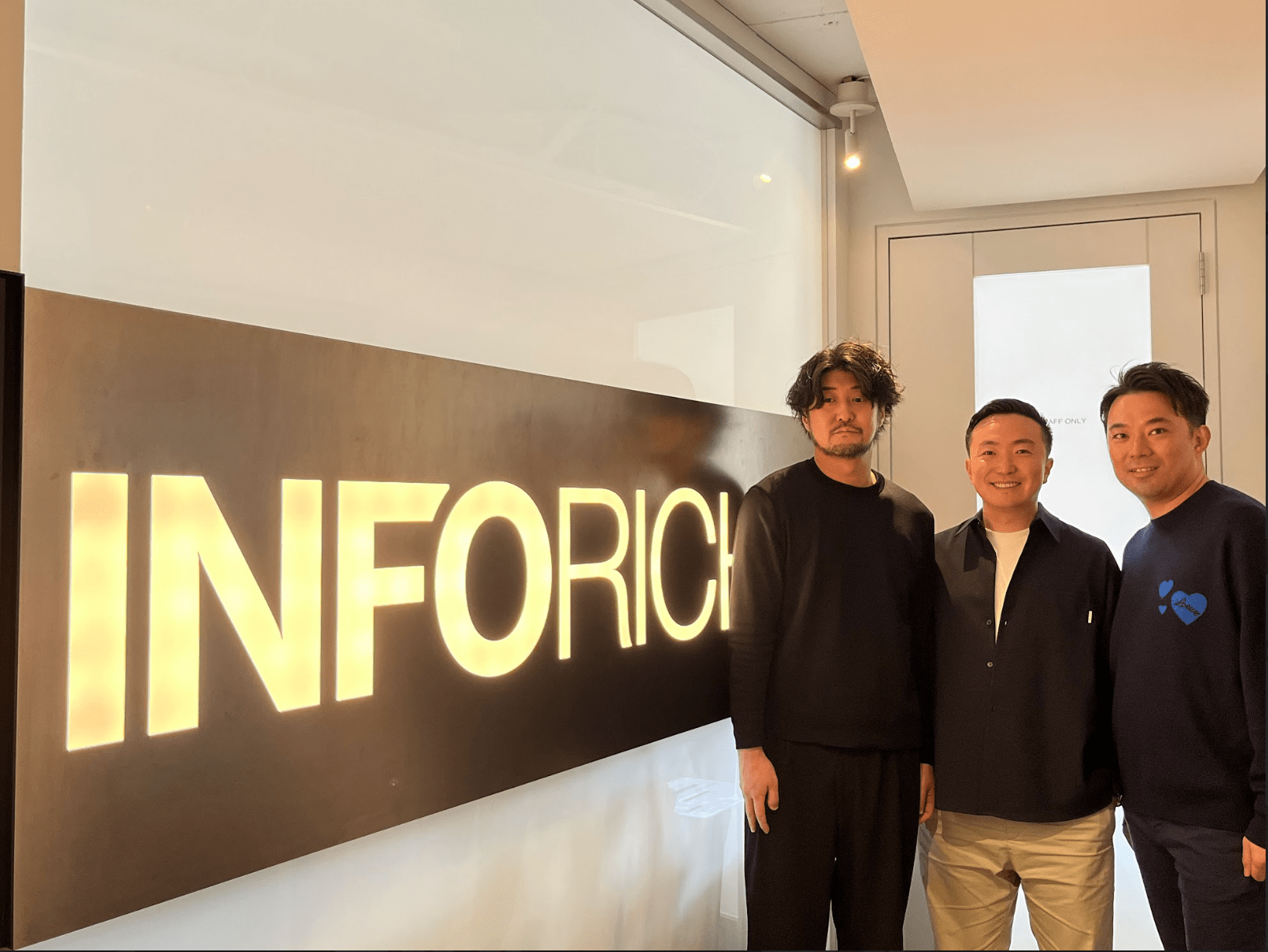
「選択と集中」。これはビジネスシーンで多々使われるフレーズであり、うまくいけば非連続的な成長へと繋がり、判断を見誤ればリスクを負うことになる。限られた経営資源で急成長を目指すスタートアップにとっては、結果的に生死を分ける判断につながることもある。
では、正しく“選択と集中”をするポイントを見極めるにはどうすればよいのだろうか。選択と集中によって急成長を遂げたスタートアップの事例として挙げたいのが、香港発のスマホ用モバイルバッテリーレンタルサービス「ChargeSPOT(チャージスポット)」だ。

ChargeSPOTは、運営会社であるINFORICH(インフォリッチ)が2018年4月から日本でのサービス展開を開始した。コンビニや駅などに設置された充電スタンドからモバイルバッテリーをレンタルでき、返却も充電スタンドがある場所であればどこでもOKとなっている。利用料は30分以内なら165円、30分以上〜6時間未満なら330円。この手軽さが受け入れられ、INFORICHは2022年12月に東証グロース市場で上場も果たした。
そんなChargeSPOTだが、サービス開始当初から順調だったわけではない。レンタル数を増やそうと試行錯誤を繰り返すが、うまく数字が積み上がらない日々が続いていた。しかし、2020年のあるキャンペーンをきっかけに、月間利用数は4倍以上の急成長を遂げ、その後も数字を伸ばし続けている。このキャンペーンを仕掛けたのは、サービスの成長を支援するチーム「Growth Camp(グロースキャンプ)」だ。




