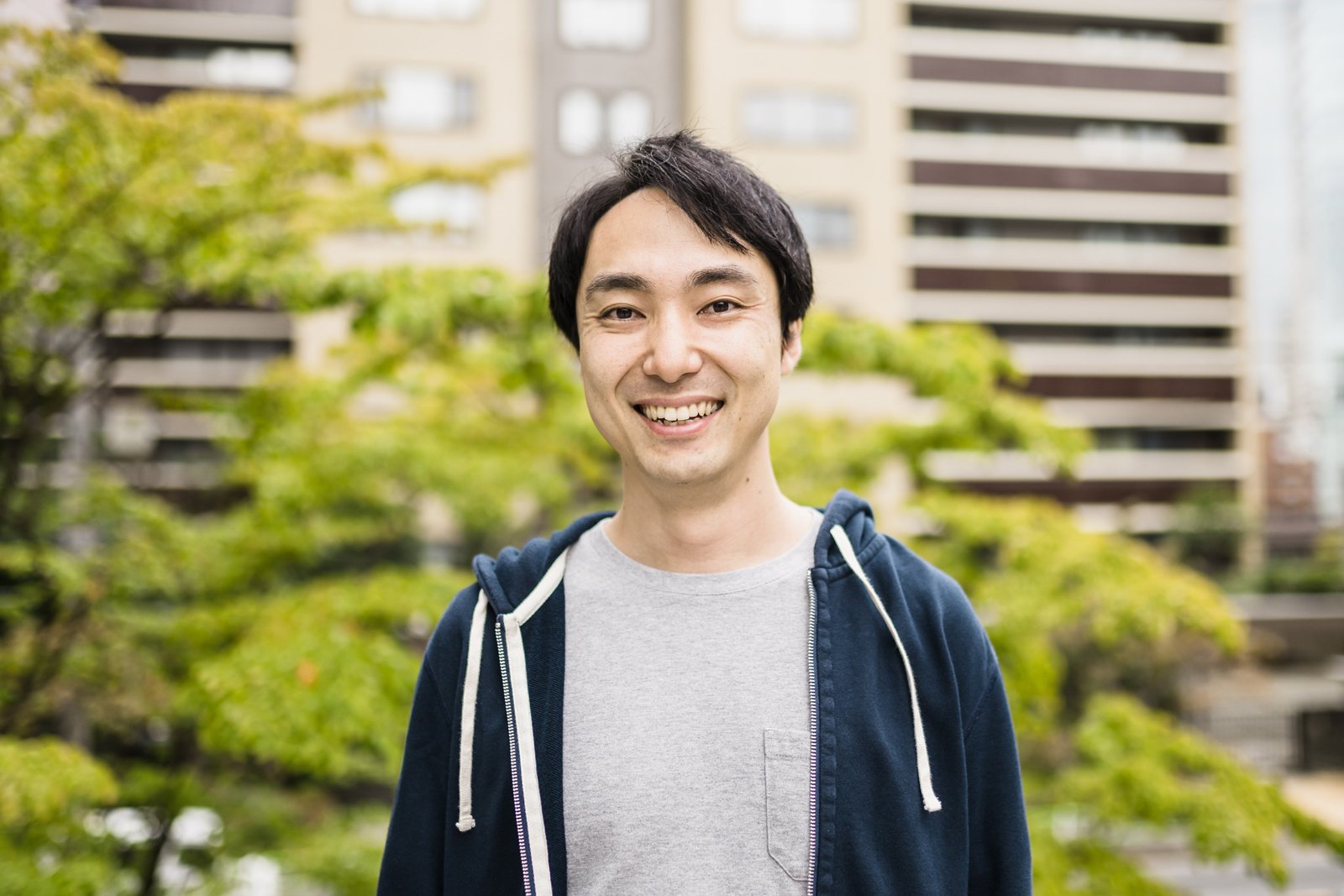
新型コロナウィルスの影響で外での食事が難しくなっている今、急速に注目を集めているのがフードデリバリーサービスだ。東京では街中でUber Eatsや出前館の配達員を見る機会が明らかに増え、芸能人を起用したテレビCMを打つ企業も出てきている。筆者はライター業と並行して都内で飲食店を経営しているが、3月末に加盟店登録を申し込んだUber Eatsは、登録完了までに2カ月もかかった。それほど申請が殺到していたということだろう。
そんなフードデリバリーサービスのマーケットに挑戦する新たな国内発スタートアップがシンだ。同社は8月6日、フードデリバリーサービス「Chompy(チョンピー)」を正式ローンチした。合わせて、合計6億5000万円の資金調達を実施したことも明らかにした。
「毎日の食事を豊かにしたい」が起業の原動力

Chompyの基本的な使い方は、Uber Eatsに代表されるフードデリバリーサービスとほぼ同じだ。アプリから好みの飲食店やメニューを選択し、決済を行えば、飲食店には専用アプリを通じて注文が入る。それと同時に、その時稼働できる配達員(契約形態は個人事業主。いわゆるギグエコノミーを活用する)に連絡が入るため、飲食店が調理した商品を配達員がピックアップし、ユーザーにとどけるというものだ。
手数料は、ユーザーが一律300円、飲食店は購入金額の30%となっている。2020年2月からベータ版としてノンプロモーションでサービス展開してきたが、正式版ローンチ時点でのサービスの対象とするのは、渋谷駅から約3km以内の飲食店。登録者数はこれまで約2万5000人、加盟飲食店は個人店を中心に約400店。
サービスを提供するシンは、2019年6月創業のスタートアップだ。今回、シードラウンドの資金調達として、ANRI、Coral Capital、DCM Ventures、Delight Ventures、GO Fundから6億5000万円を調達。創業直後に実施したDelight Ventures などからの調達と合わせて、累計で約9億円を調達したことになる。




