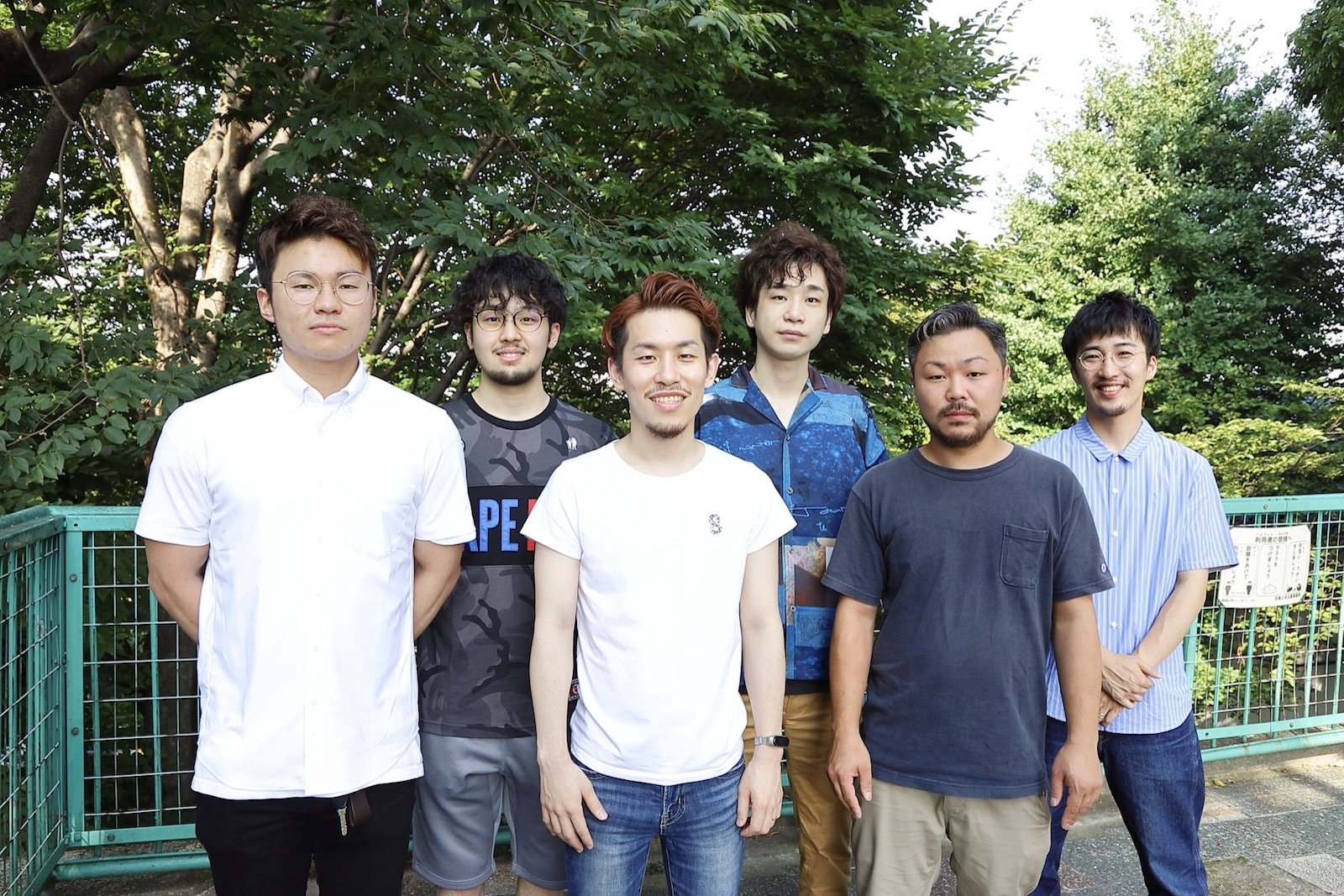
宅配便の増加はコロナ禍の巣ごもり需要で加速度的に増加している。ヤマト運輸の発表によると、6月の取扱個数は約1億7000万個で、前年同月比で18.7%の増加となっている。
宅配便の取扱個数の増加で影響を受けるのは、荷物を届ける配達員だ。財務省が2018年10月に公表した「宅配・郵便業界における人手不足について」によると、取扱個数は大幅に増加しているものの、就業者は近年横ばいの動きをしており、「結果として配達ドライバー1人あたりの取扱数が急増している」という。
宅配便ドライバー、配達員の負荷が高まる物流業界。この業界をDX(デジタルトランスフォーメーション)し、配達業務の効率化を目指すのが、スタートアップの207(ニーマルナナ)だ。同社は物流のラストワンマイル(配達業者と荷物を受け取る消費者を結ぶ最後の区間)に特化したサービスを開発し、提供する。
207は8月24日、総額8000万円の資金調達を実施したことを明らかにした。第三者割当増資の引受先は、環境エネルギー投資と、通販事業を手がけるベガコーポレーションだ。
207は2018年1月設立のスタートアップ。配達員向けの業務効率化アプリ「TODOCU(トドク)サポーター」と、荷物の受取人向けの配達通知アプリ「TODOCU」を展開する。5月からはコロナ禍で急増した飲食店のデリバリーのニーズに合わせて、ギグワーカーを活用したシェアリング型の配達サービス、「スキマ便」の提供も開始した。




