スタートアップをゼロから支援する、新しい起業支援のモデルである「スタートアップスタジオ」。世界各国のテックシーンで注目を集めているが、日本でも徐々に増えてきた。スタジオの役割や意図について、6月にスタジオを立ち上げたSun Asterisk(サン・アスタリスク)に聞いた。(フリーライター こばやしゆういち)
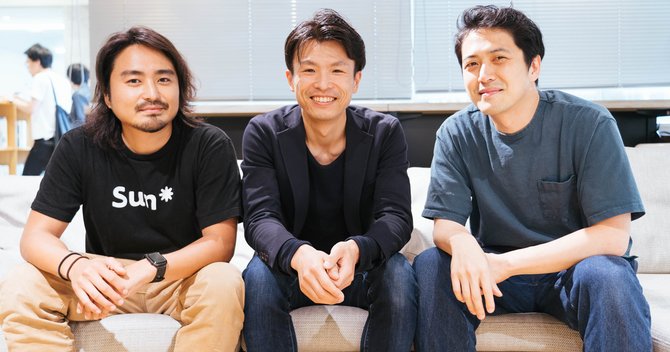 左からSun Asterisk執行役員の梅田琢也氏、テナンタ代表取締役の小原憲太郎氏、Sun Asteriskの船木大郎氏氏 Photo by Yuhei Iwamoto
左からSun Asterisk執行役員の梅田琢也氏、テナンタ代表取締役の小原憲太郎氏、Sun Asteriskの船木大郎氏氏 Photo by Yuhei Iwamoto
スタートアップを「ゼロから育てる」スタジオ
「スタートアップスタジオ」がアメリカで誕生したのは、2000年代の後半だといわれる。ハリウッドの映画スタジオが数多くの作品を制作するように、スタートアップを生み出していく組織として誕生したのが、このスタートアップスタジオと呼ばれる新しい形態だ。
スタートアップの支援という面では、これまでベンチャーキャピタル(VC)に焦点が当たってきた。彼らは、スタートアップの将来性を読み取り、その成長を助けるために資金面で支援することを主眼にしている。創業期から支援するVCやエンジェル投資家もいるが、たいていの場合は製品やサービスをリリースした後、いわゆる「アーリー期」以降のスタートアップが支援の対象になることが多い。
これに対してスタートアップスタジオは、一般に「シード期」から製品やサービスのリリースを支援し、スタートアップをゼロから育てることを目的とする組織を指す。VCとは異なり、資金面だけではなく起業に必要な人的資源や開発環境なども含めて多面的に支援するというのが大きな特徴だ。
映画スタジオを例にとるとわかりやすい。ワーナー・ブラザーズやユニバーサルといった大手スタジオが映画を制作する場合、優秀な映画監督をスタジオに招き、優秀なスタッフや資金を提供して1本の作品を作る。これと同様に、映画監督の代わりに「起業家」を招き、作品の代わりに「スタートアップ」をつくるのが、スタートアップスタジオというわけだ。




