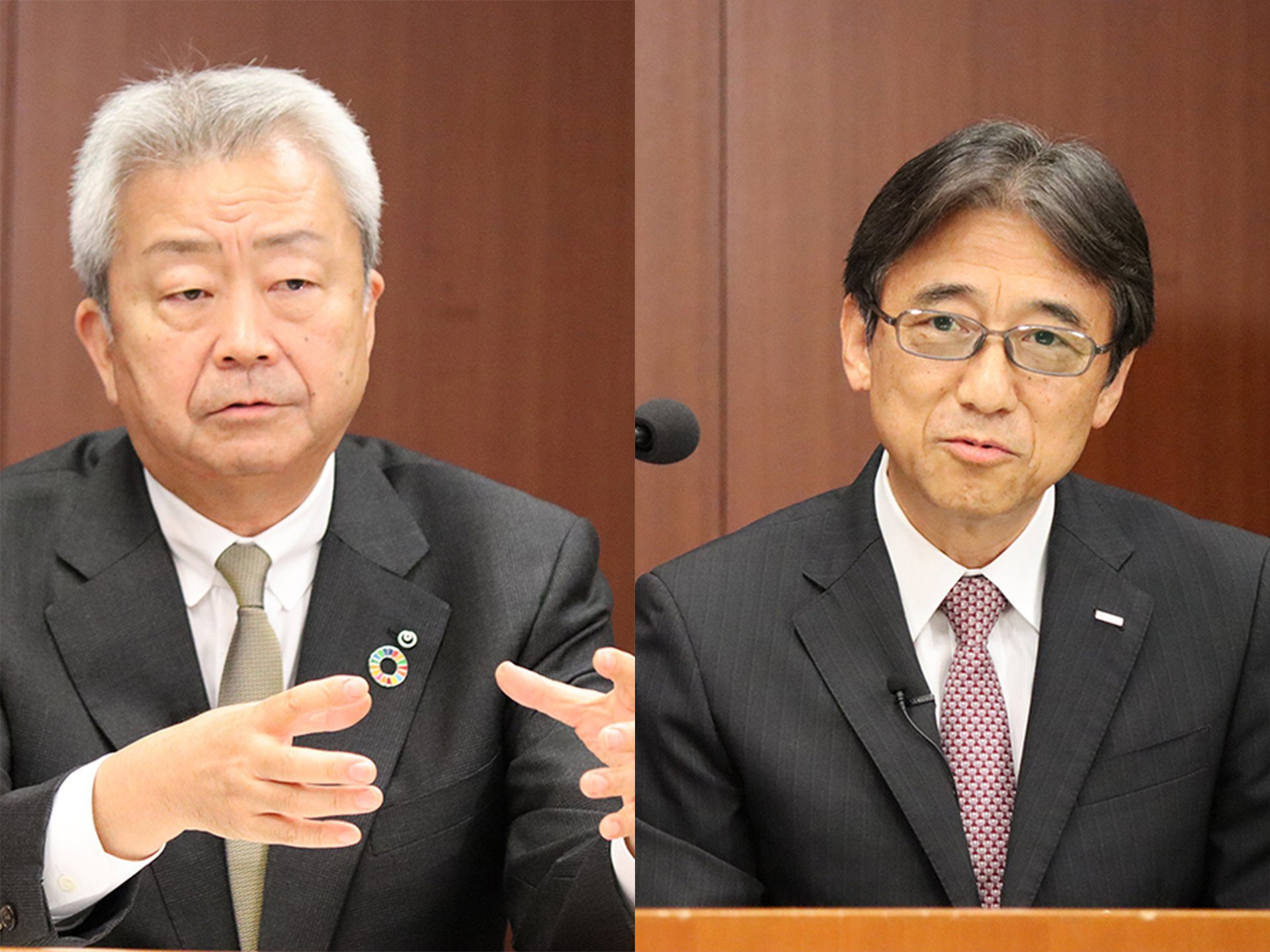
NTT(持株会社)は9月29日、NTTドコモを完全子会社化すると発表した。現在NTTはドコモの株式を64%程度保有しているが、残りの株式も株式公開買い付けにより取得する。2020年度内に完全子会社化を完了する見込み。両者は9月29日にオンライン会見を実施し、完全子会社化を決めた経緯や今後の方針を説明した。
子会社化の完了後、ドコモはグループ内のNTTコミュニケーションズ(NTT Com)やNTTコムウェアとの事業連携を深め、グループ内の経営リソースの最適化を図る。研究開発体制ではNTTとドコモのR&D組織の連携を強化し、“5Gの次”に向けた技術開発を加速する。
あわせて、NTTドコモの社長交代も発表された。現社長の吉澤和弘氏は12月1日をもって退任し、NTT出身で現ドコモ副社長の井伊基之氏が代表取締役社長に就任する。
世界一の会社の“社内ベンチャー”誕生から30年
NTTドコモはもともと、NTTグループの“社内ベンチャー”的な存在だった。前身のエヌ・ティ・ティ・移動通信企画株式会社が設立されたのは1991年。日本中が好況に沸いたバブル景気から、後に“失われた20年”と呼ばれる停滞期への転換点となった年だ。
旧電電公社から民営化されたNTTは、バブル景気のさなか時価総額で世界一を記録する。そんな時代に生まれた子会社ドコモは、自動車電話やポケベルから、携帯電話事業を手がけ、大きく成長。1998年には東証一部上場を果たす。




