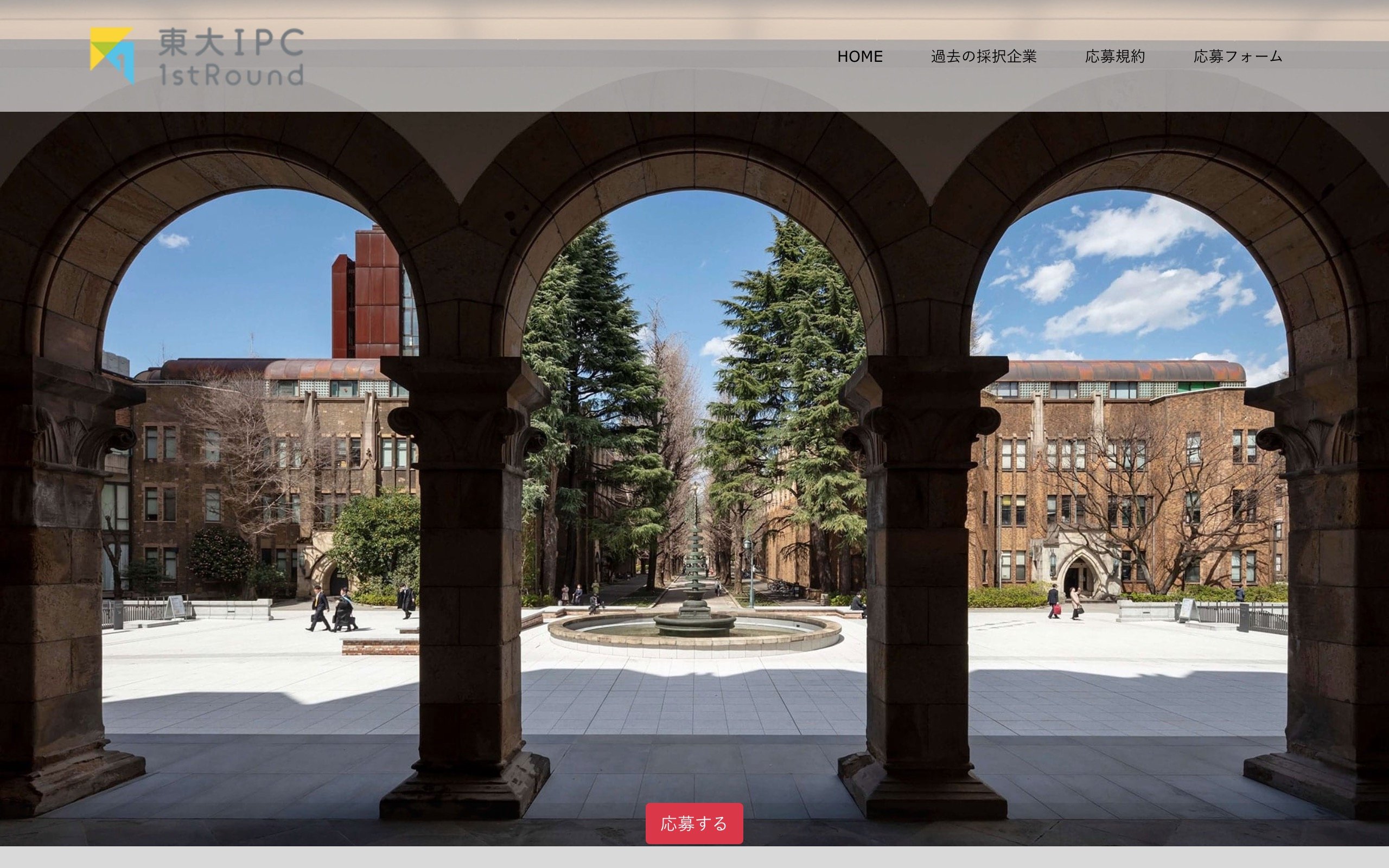
東大系VCのインキュベーションプログラムに新たに7社が採択
起業を目指す卒業生・教員・学生などの東京大学関係者や、ユニークな事業のタネを持つ東京大学関連のシードベンチャーを対象にしたインキュベーションプログラム「東大IPC 1st Round」。
運営元の東京大学協創プラットフォーム開発(東大IPC)は10月20日に3回目を迎える同プログラムの新たな支援先7社を発表した。
東大IPC 1st Roundでは各社に対して最大1000万円の活動資金が提供されることに加え、東大IPCが6ケ月間に渡って事業の垂直立ち上げに伴走する。JR東日本スタートアップやトヨタ自動車を始めとする国内大手企業がパートナーとして参加しており、各社と協業や実証実験のチャンスがある点なども特徴だ。
また東大IPCでは今年7月に職業紹介事業者許可を取得し、1st Round支援先とその卒業生、および投資先スタートアップに向けた人材支援プラットフォーム「Deep Tech Dive(ディープテックダイブ)」を展開。対象スタートアップが手数料なしで起業志望者やCxOなどの幹部志望者、研究者・エンジニアなどの副業志望者といった人材にダイレクトにアプローチできるシステムの提供も開始している。
前身のプログラムも含めると過去2年間の間に累計29チームが採択され、そのうち17社がすでにベンチャーキャピタルなどからの資金調達に進んでいるという。




