
2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されていることに伴い、労働時間や従業員の健康など、規模の大小にかかわらず企業が留意すべき責務の範囲が広がっている。
こうした変化を背景に、従業員の健康管理を企業が経営的視点から考え、戦略的に健康に投資する「健康経営」の考え方も拡大。企業の取り組みを支援するソリューションも増えている。2016年3月にサービスを開始した人事担当者向けの健康管理システム「Carely(ケアリィ)」もそのひとつだ。
Carelyを提供するiCARE(アイケア)は12月9日、JICベンチャー・グロース・インベストメンツ(産業革新投資機構:JIC傘下の認可ファンド)を筆頭に、三井住友海上キャピタル、SFV・GB投資事業有限責任組合(ソニーフィナンシャルベンチャーズとグローバル・ブレインが共同設立したファンド)、Salesforce Ventures、SMBCベンチャーキャピタルから、総額15億円の資金調達を実施したことを明かした。
働き方改革で増えた人事担当者、産業医らの負担を軽減
iCARE代表取締役CEOの山田洋太氏は、産業医の資格を持つ医師でもある。労働者の健康課題について「産業医だけでは解決しない」との思いから、iCAREを2011年6月に創業した。
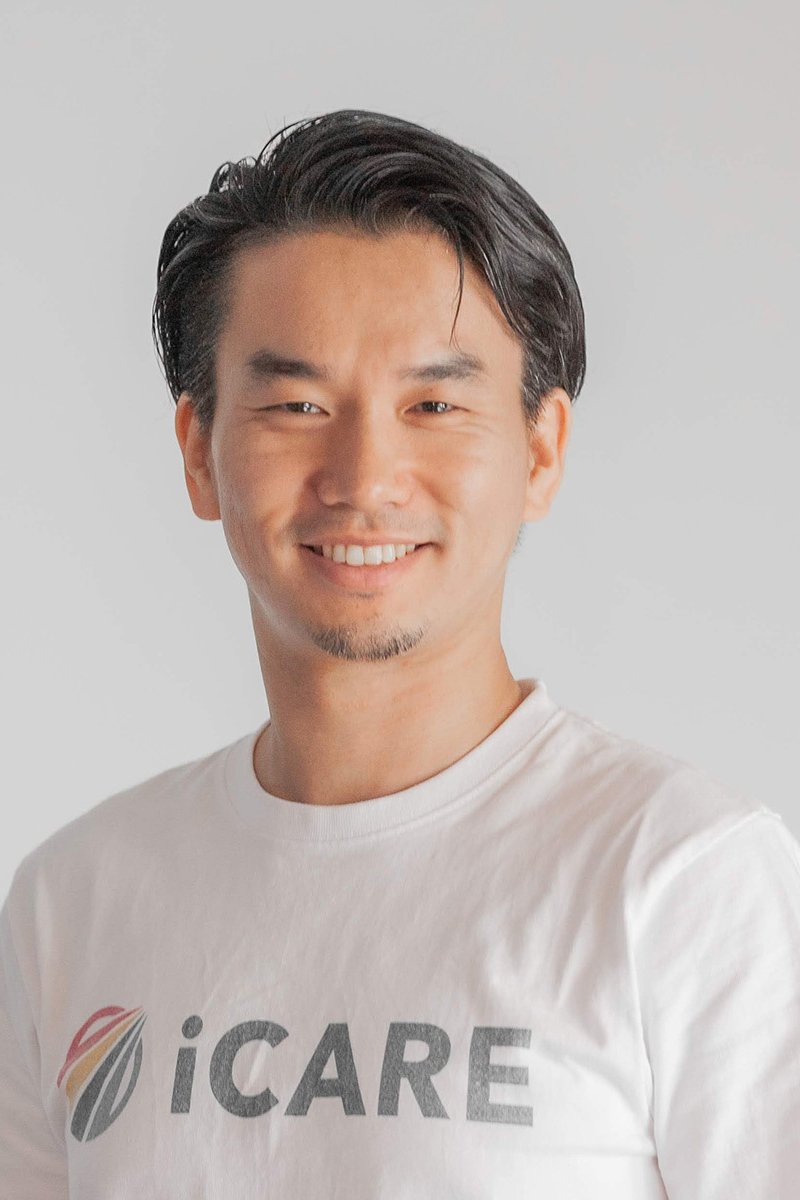
「健康管理の領域はアナログで、産業医や産業看護師の頑張りによる属人性が強い。自分ひとりでは、自分が診ている人たちの範囲でしか、世の中を変えられません。テクノロジーを使って複雑・煩雑な作業を減らして、産業医や看護師、人事担当者も含めた関係者が考える時間をもっと作れば、健康な人を増やせるはずと考えました」(山田氏)




