資金調達にサービスの立ち上げ、上場や事業売却と、ポジティブな側面が取り上げられがちなスタートアップだが、その実態は、失敗や苦悩の連続だ。この連載では、起業家の生々しい「失敗」、そしてそれを乗り越えた「実体験」を動画とテキストのインタビューで学んでいく。第3回はツクルバ共同創業者で代表取締役CEOの村上浩輝氏の「失敗」について聞いた。(聞き手/ダイヤモンド編集部副編集長 岩本有平、動画ディレクション/ダイヤモンド編集部 久保田剛史)
ツクルバは2011年の設立。新卒で入社したリクルートコスモス(現:コスモスイニシア)で出会った村上氏と共同創業者で代表取締役CCOの中村真広氏。リーマンショックを期に会社を離れた2人だが、その後村上氏はネクスト(現:LIFULL)、中村氏はデザイン事務所でそれぞれ働いた後、2人で起業するに至った。
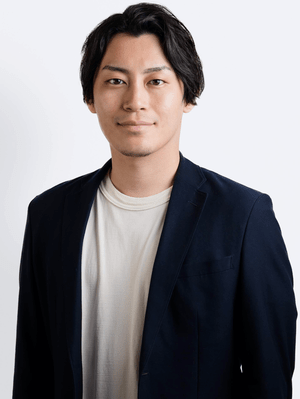 ツクルバ代表取締役 CEO 村上浩輝氏(提供:ツクルバ)
ツクルバ代表取締役 CEO 村上浩輝氏(提供:ツクルバ)
創業当初は東京・渋谷にコワーキングスペース「co-ba(コーバ)」を開設したツクルバ。スペースの運営やデザインファームとしてのクライアントワークで実績を詰んできたが、2015年にはリノベーション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」を開始。ベンチャーキャピタルや事業会社から資金を調達し、自社サービスを展開する“スタートアップ”としての事業を展開するに至った。
学生時代から交差していた2人の創業者
僕は学生時代から事業をやっていました。ダンスが趣味だったんですが、大学生ダンサーの地位向上に寄与できないかをずっと考えていました。それで、ダンスコンテストを主催したりしました。イベントをきっかけに、ナイキなど企業からの仕事を受けるようになったんです。
ただし「事業」とは言っても労働集約型なもの。貯金は1000万円くらいになったんですが、お金を積んでいくことには価値を感じられなくて。もっと、「仲間と未来を作る」ということに挑戦したいと思っていました。




