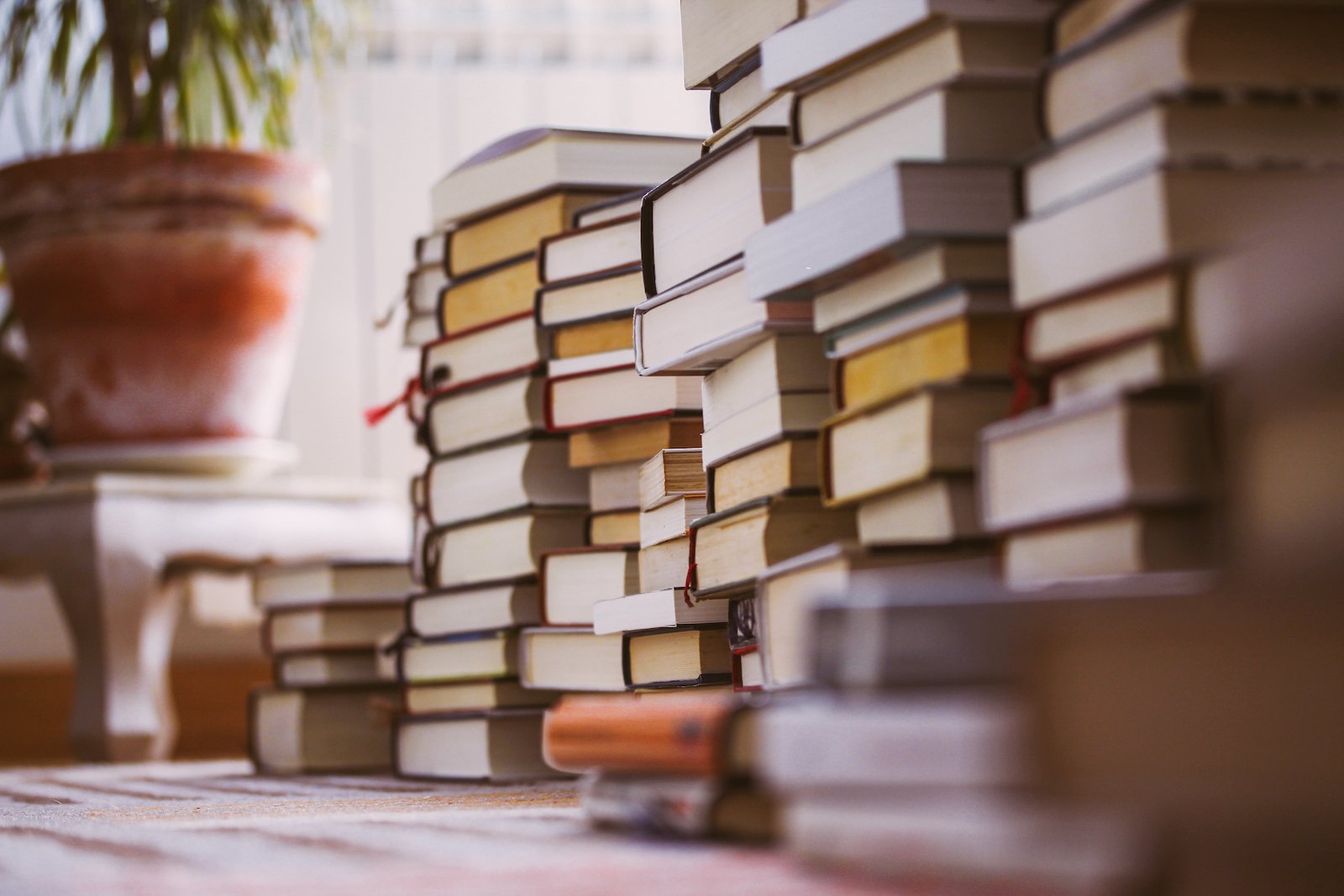
ビジネス書や小説を読んだり、NetflixやAmazon Prime Videoでドラマや映画を見たり──年末年始はゆっくり読者やコンテンツを楽しむ時間に充てよう、と考えている人も多いのではないだろうか。とはいえ、数多ある書籍やコンテンツの中で何が面白くオススメなのか、分からずにいる人も多いはずだ。
今回、DIAMOND SIGNAL編集部では起業家たちにアンケートを実施。2020年に読んで良かったと思う本、漫画、コンテンツを聞いた。掲載は五十音順。
React共同代表 青木穣氏
・「ザ・ファブル」(講談社)
理由:主人公の妹役のヨウコがタイプすぎるからです。
ミラティブ代表取締役CEO 赤川隼一氏
・「悲しみとともにどう生きるか」(集英社新書)




