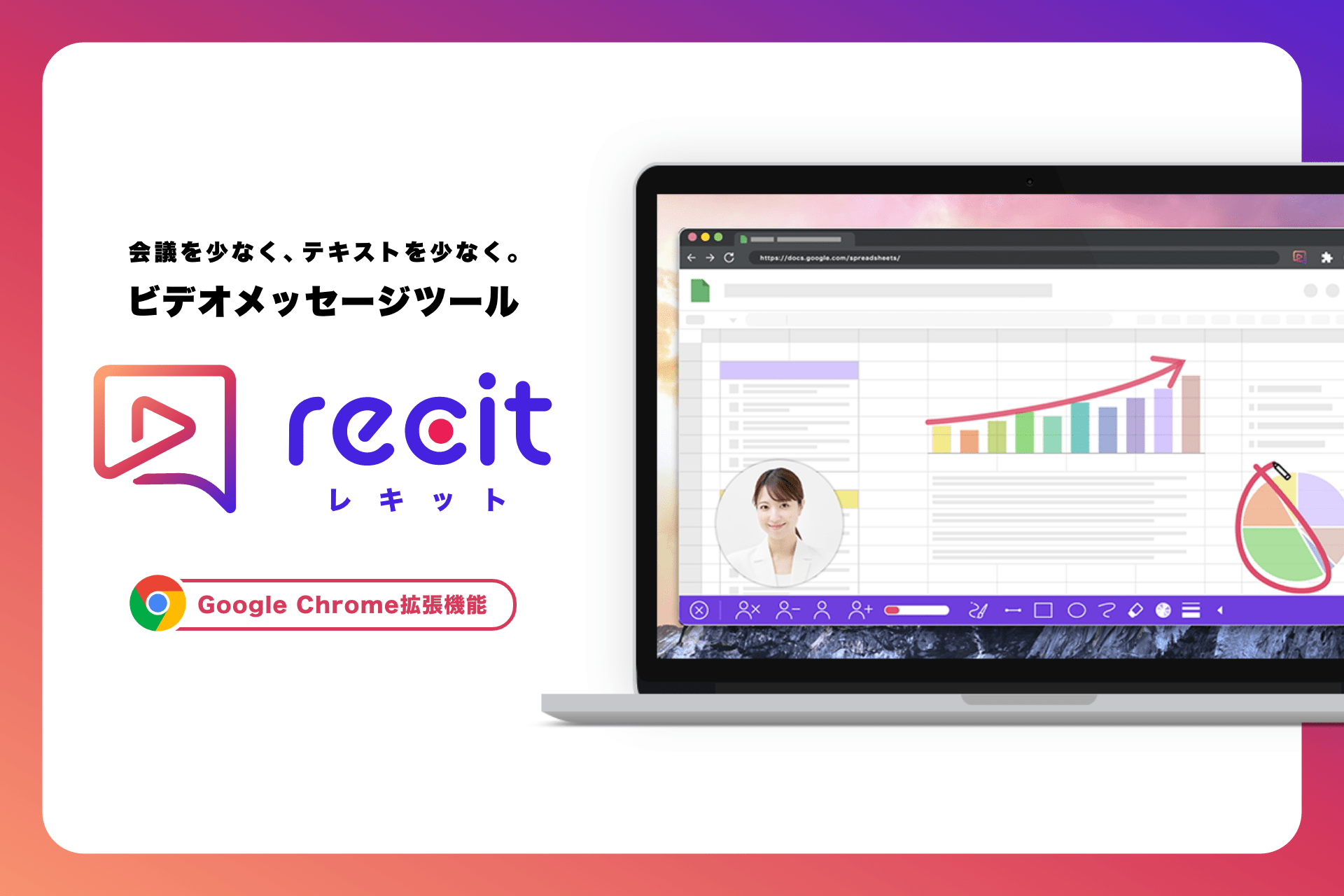
新型コロナウイルスによってリモートワークが主流となったこの1年強で人々の働き方も大きく変わった。“会議のオンライン化”、ビデオ会議もその1つだろう。
通常の会議はもちろん、従来であれば口頭で行っていたちょっとした相談や報告、雑談などもチャットツールやビデオ会議ツールを使って行うようになった。移動時間がなくなったことなども合わさって、以前に比べて会議の時間自体が増えたという人もいるはずだ。
そういった状況下において、グローバルでは「asynchronous meeting」領域への注目度が高まりつつある。日本語では「非同期ミーティング」などと訳されるが、文字通りリアルタイムで実施していた会議を非同期に変えることを指す。たとえば動画共有ツールを用いることで会議そのものを、もしくはその一部を非同期に置き換えていくケースがわかりやすい。
ツールを活用して相談事項や報告事項をウェブ上で録画し、動画形式で参加者に“事前共有”する。簡単な報告事項であれば、わざわざ会議を開かずとも動画を見るだけで十分かもしれない。参加者間で何かを議論して決める必要がある場合にも、報告の工程を動画に置き換えることで会議時間の短縮や質の向上が見込める。
実際にこの領域では先日1億3000万ドルの大型調達を発表した米国スタートアップのLoomを筆頭に、複数のプレーヤーが台頭し始めている状況。狭義の会議に留まらず営業やマーケティング、カスタマーサポートの分野など幅広い用途で活用できる余地があるため、今後さらに各企業が事業を広げていく可能性もある。




