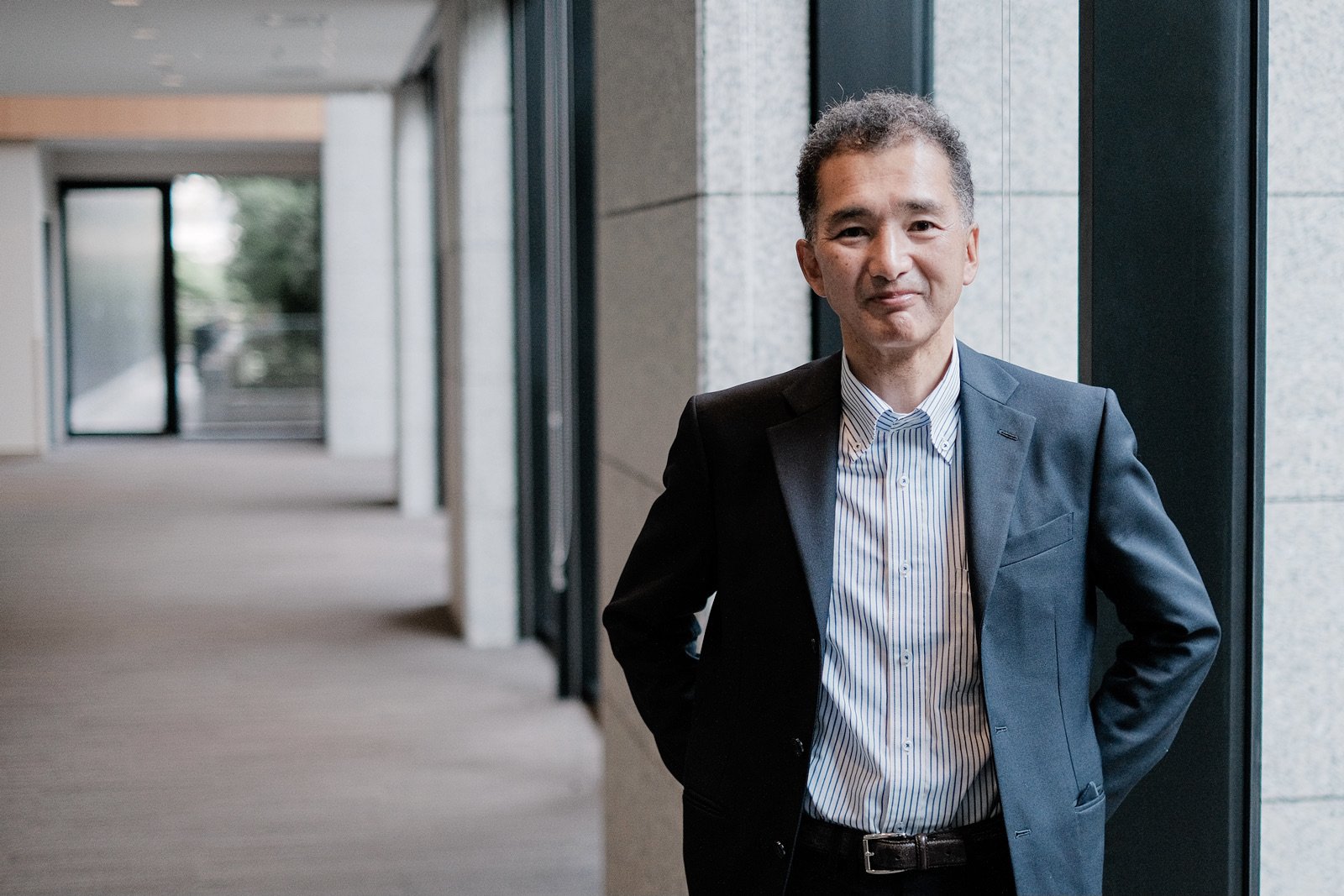
急速な成長を遂げ、企業価値が1000億円を超える未上場スタートアップを指す「ユニコーン企業」。日本では今年、後払い決済サービスのPaidyとクラウド労務ソフトのSmartHRがユニコーン入りを果たしたが、その数は海外の「スタートアップ大国」と比較するとはるかに少ない。
スタートアップやベンチャーキャピタル(VC)に関するデータベースを展開する米CBインサイツによると、米国には300社以上、中国には100社以上のユニコーン企業が存在する。一方、日本には6社しかいないのが現状だ。
日本政府は2018年、第3次安倍内閣の成長戦略である「未来投資戦略2018」において、2023年までに企業価値が1000億円を超えるユニコーン企業、または上場ベンチャーを20社創出することを目標に掲げた。その目標を達成するプロジェクトとして、同年には経済産業省主導のスタートアップ支援プログラム「J-Startup」もスタートした。
ローンチから約3年──J-Startupではこれまでの成果をどのように捉えているのだろうか。経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室長の石井芳明氏に話を聞いた。
なお、石井氏は7月1日付けで出向先である内閣府(科学技術・イノベーション担当 企画官を担当)から出向元である経産省に帰任している。本取材は6月と7月の2回に分けて敢行したが、石井氏の肩書は現在のもので統一している。




