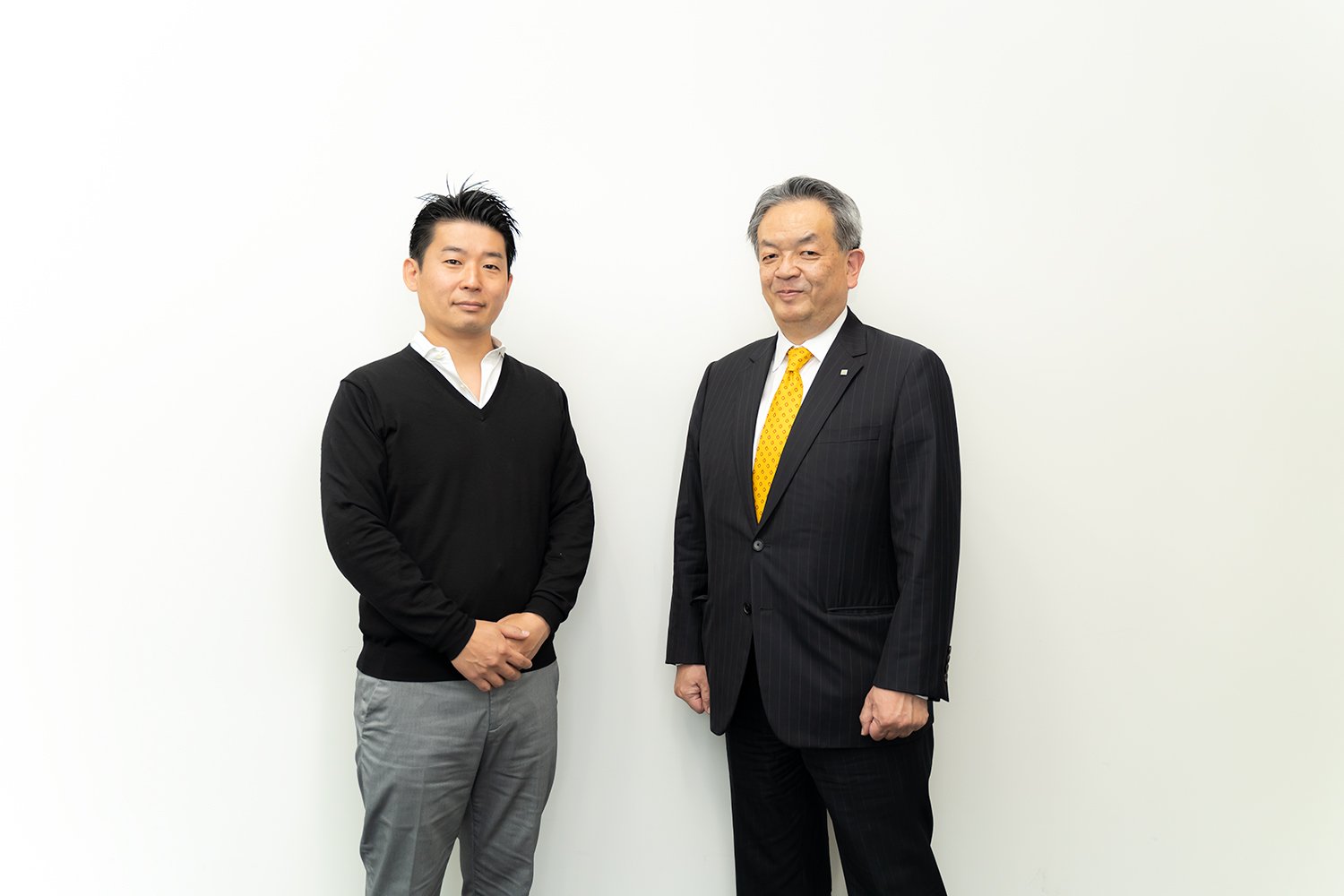
近年「DX」という言葉がさまざまなシーンで使われ始めているように、あらゆる業界で急速にデジタルの活用が進んでいる。
「食品卸業界」もその例外ではない。従来、食品卸企業と飲食店の間の受発注業務(企業間取引)には電話やファックスといったツールが数十年もの間にわたって使われ続けてきた。その結果として取引の量が増えるほど煩雑な作業も増え担当者が疲弊していただけでなく、属人的な仕事であるが故にミスがつきものだった。
その課題にいち早く目をつけ、事業を拡大してきたのがインフォマートだ。同社では2003年に「BtoBプラットフォーム 受発注(旧フーズインフォマート)」をローンチ。受発注業務をデジタル化することで、発注側・受注側双方の業務を劇的に効率化するとともに、余計なミスが生まれる原因を解消した。
現在同サービスは4万社以上が有料で用いる“業界のデファクトスタンダード”に拡大。2006年に東証マザーズ上場、2016年に東証一部に市場変更するなど成長を続けてきたインフォマートの主力サービスにもなっている。
そんなインフォマートが2021年2月、卸売業者に寄り添った受発注システム「TANOMU」を展開するタノムと資本業務提携を締結した。




