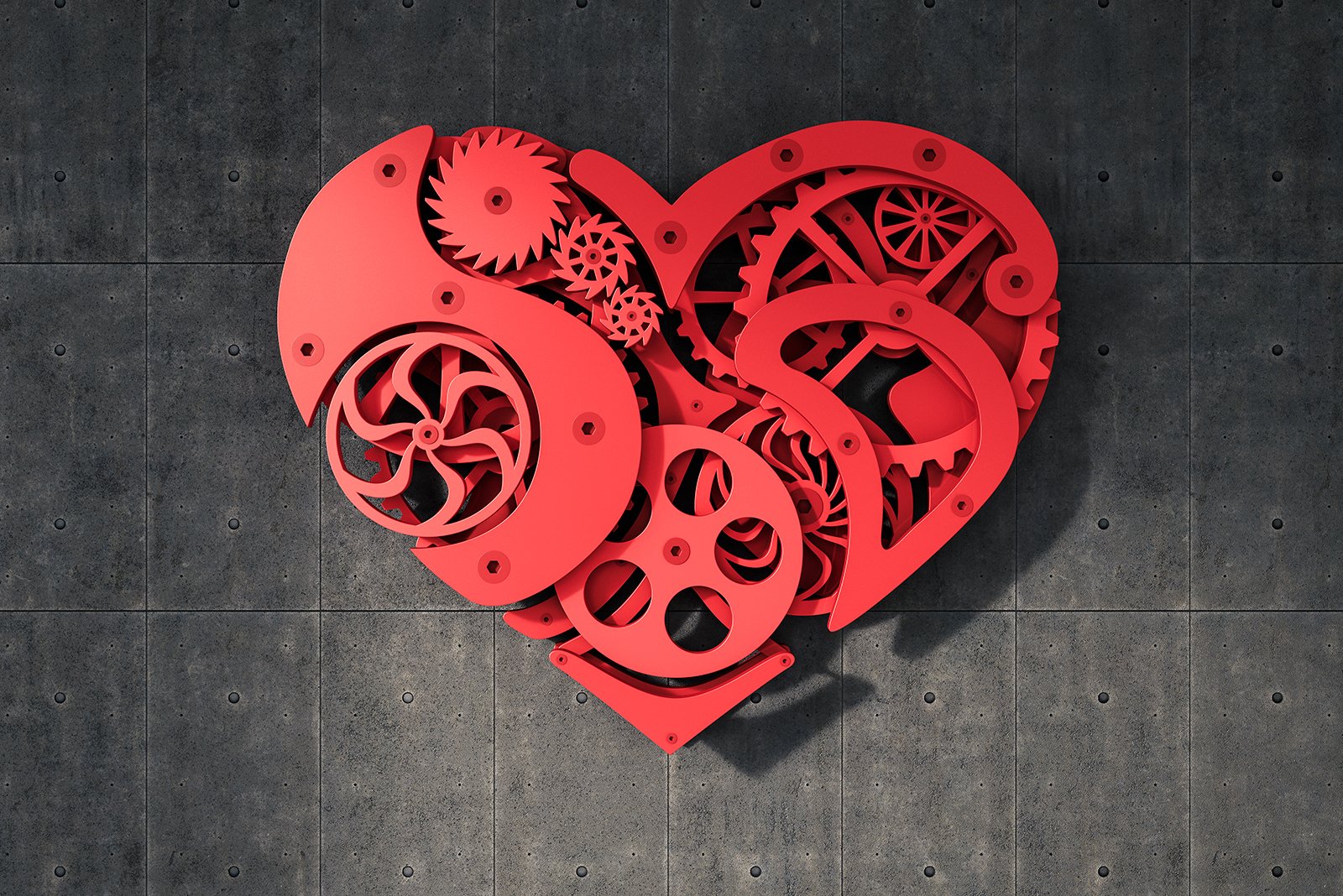
スタートアップの成長に、組織づくりは欠かせない。多くのスタートアップは経営者ひとりか、その仲間数人という、ミニマムな体制で産声を上げる。
その後、事業が軌道に乗ると、会社の規模は拡大していく。メンバーが30人を超えるくらいの段階で、経営者の目が行き届かなくなる「30人の壁」のように、経営と個人のミッションの連動性が弱まり、成長の壁に直面する時期は必ずやってくる。
会社の成長段階でこのような状況に陥る背景として、経営者とメンバーの間に「事業部」という組織のレイヤーが挟まることで、経営者の掲げるビジョンやメッセージが届きにくくなること、個人連携で成果を上げる組織体系から、チーム間連携で成果を上げる組織体系に変化していることなどが挙げられる。
これらの課題と向き合う手法として、米国の社内SNS提供企業で2012年にマイクロソフトが買収したYammerや、オンライン決済大手のPayPalは「ケイデンス経営」という概念を導入してきた。
本稿では、経営管理クラウド「Loglass」を開発・提供するスタートアップ、ログラス代表取締役CEOの布川友也氏が、SaaSベンチャーに特化した投資・支援を行う「ALL STAR SAAS FUND」マネージングパートナーの前田ヒロ氏、イネーブルメントパートナーの神前達哉氏らの協力を得てケイデンス経営の基本を解説。ログラスでのケイデンス経営実践例や、メリット、開始時の注意点なども紹介する。




