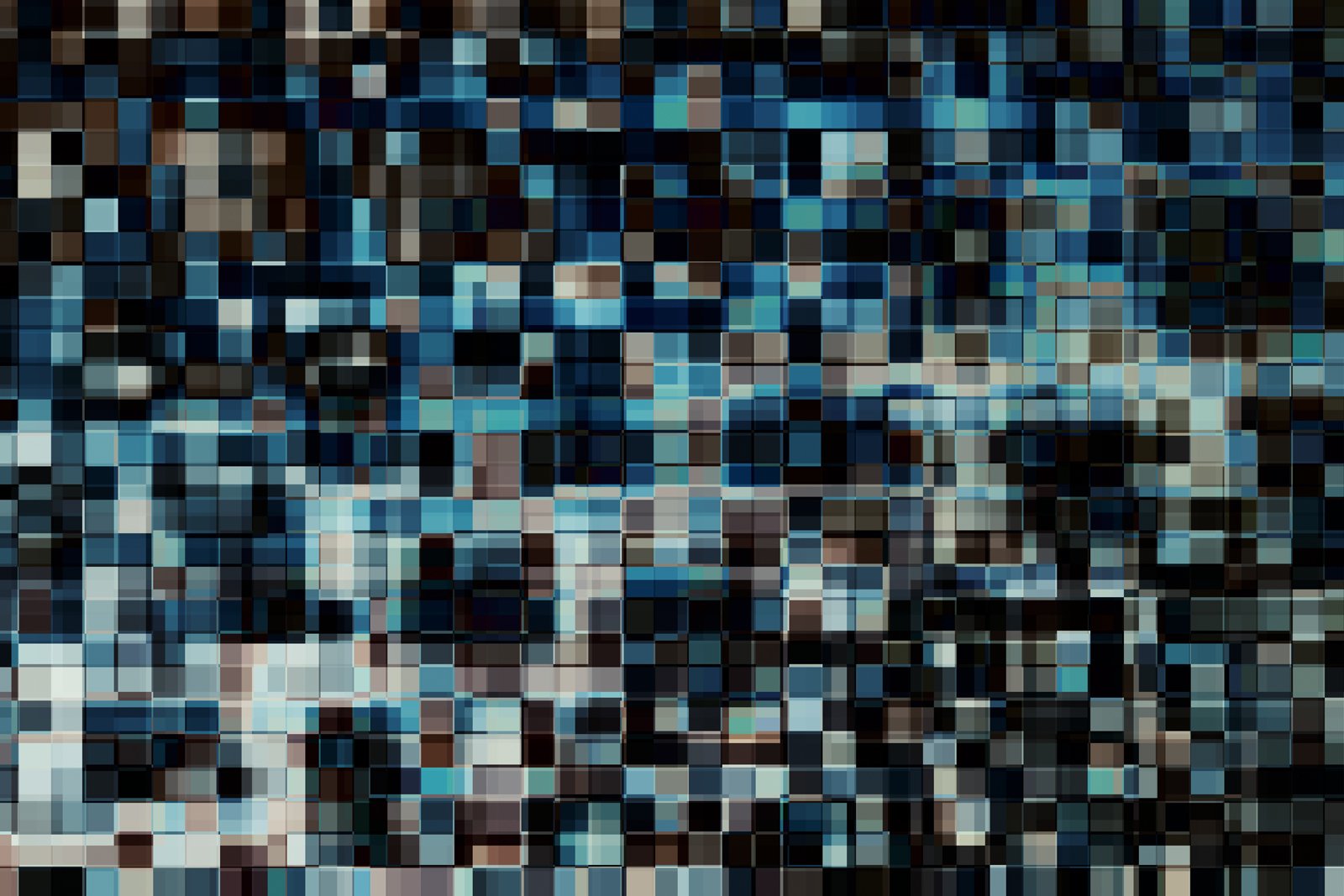
スクウェア・エニックスの家庭用ゲーム機向けソフトに、販売方法の変化が起きている。2021年4月以降、同社がパッケージ版ソフトを販売せずに、ダウンロード専売にするタイトルが増えつつある。
同社はすでに2020年末から『サ・ガ コレクション』(Nintendo Switch(以下Switch)、iOS、Android、Steam)や『サガ フロンティア リマスター』(PlayStation4(以下PS4)、Switch、iOS、Android、Steam)、『聖剣伝説 レジェンド オブ マナ』(PS4、Switch、Steam)など、過去の名作を現行ハード向けに移植したタイトルはダウンロード専売としてきた。いくら過去の大ヒット作とはいえリメイク(リマスター)作では何十万本級の大ヒットは狙えないため、リスクを抑えられる販売方式を選択したのだろう。
これは本サイトの過去記事「世界的ヒット『モンハン』のカプコンも急ぎかじを切る、PCゲームビジネスの破壊力」で解説した、在庫リスク軽減を狙ったものだ。
ところが同社は2021年10月に新作ソフトを2本、ダウンロード専売タイトルとして発売した。この点に注目したい。
スクウェア・エニックスの完全新作RPGが、3520円という破格値で発売されるという衝撃
スクウェア・エニックスの新作ソフト『DUNGEON ENCOUNTERS』と『Voice of Cards ドラゴンの島』は、どちらも完全新作ながら3520円。なぜこんな価格設定ができたのかと言えば、おそらく開発費を抑えたからに違いない。




