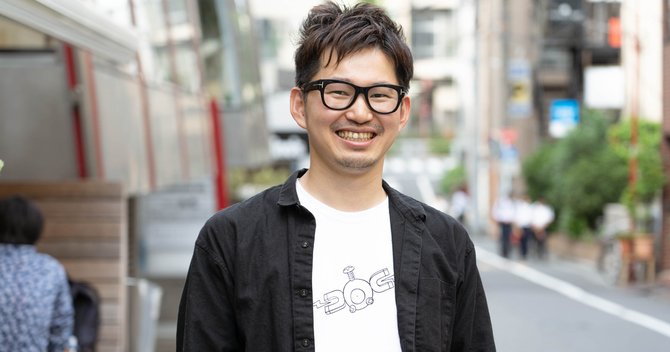 アル代表取締役の古川健介氏 Photo by Yuhei Iwamoto
アル代表取締役の古川健介氏 Photo by Yuhei Iwamoto
学生時代からインターネットサービスを開発してきた連続起業家・古川健介氏が現在取り組むのは「マンガ」をテーマにしたサービスだ。マンガに関する「好き」を熱量を込めて語る、また新しいマンガと出合う。このサービスを開発する背景にはある「騒動」があったという。古川氏に話を聞いた。(ダイヤモンド編集部副編集長 岩本有平)
「マンガのファンって熱量の高い人がとても多いんです。ですがマンガを応援する方法って、単行本を買うくらいしかありません。そういう人たちが応援してくれるほどに、マンガがより売れるサービスになればいいと思っています」
そう語るのは、「けんすう」の名で発信を続ける連続起業家・古川健介氏。古川氏が今注力しているのが、マンガファン向けの投稿サービス「アル」だ。
古川氏は2004年に、自身が開発した掲示板サービス「したらば」をライブドア(当時)に売却。その後リクルートを経てnanapi(当初の社名はロケットスタート)を起業。14年には同社をKDDIに売却した経験を持つ。古川氏はその後、Supership(nanapiと、同じくKDDI子会社だったスケールアウト、ビットセラーが合併した会社)の取締役として、新サービスの開発やブランディングなどを担当。その後19年1月にアルを立ち上げた。
アルは、ウェブとiOS向けアプリで利用できるサービスだ。それぞれで機能の差はあるが、いずれの基盤にもなっているのは、合計3万5000シリーズを超えるというマンガのデータベースだ。ユーザーはこのデータベースから好みのマンガを探し、「このマンガの好きなところ」や「このマンガを読んだ人にオススメのマンガ」といった情報を投稿できる。また、出版社から許諾を受けたマンガについては、お気に入りのマンガの「コマ」の投稿も可能だ。それぞれのマンガには、無料掲載サイトや単行本、電子書籍の販売サイトへのリンクもつけており、気に入ったマンガを試し読みしたり、購入したりもできる。保有するマンガの新刊発売日を通知する機能もアプリ限定で提供する。




