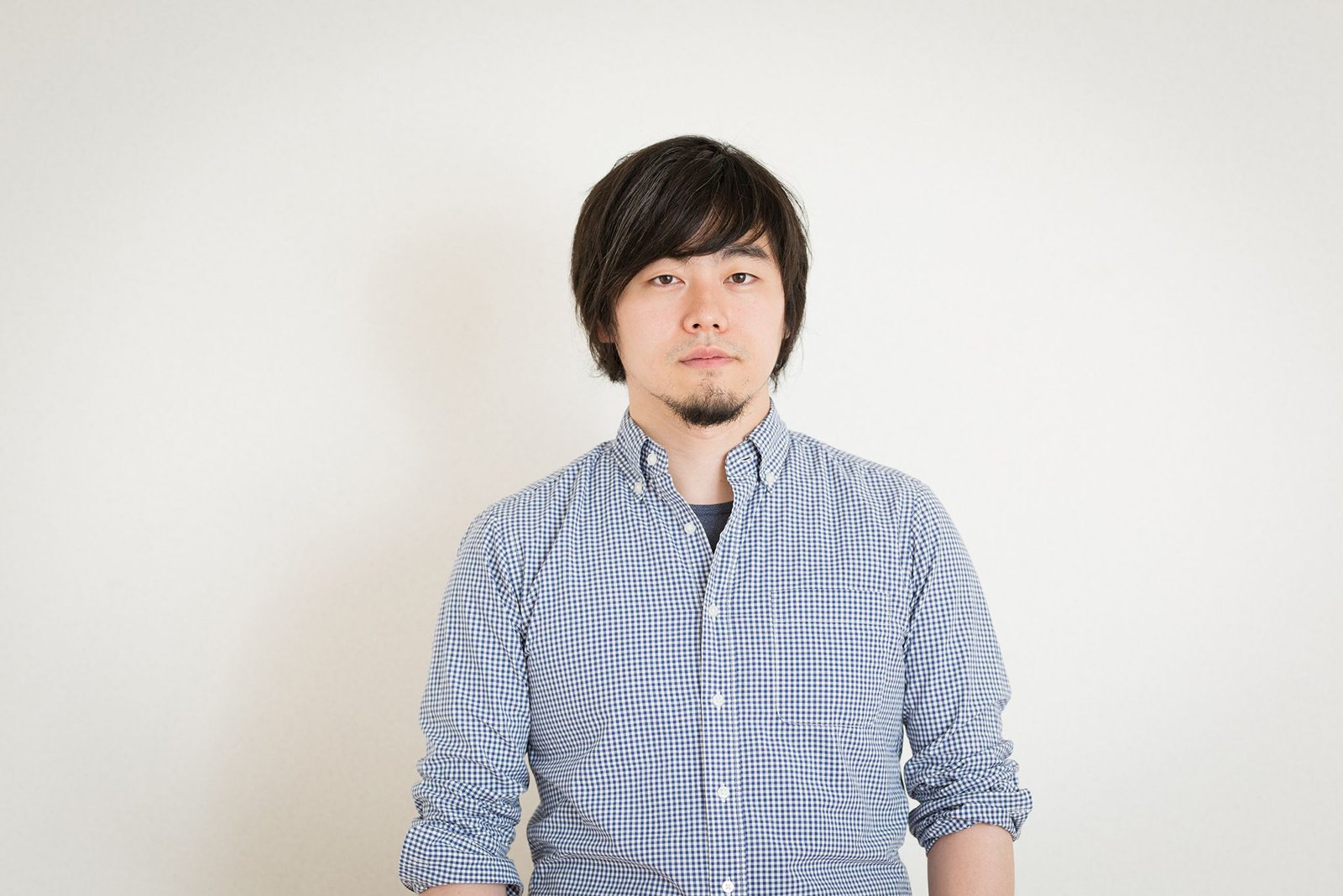
日本ではなかなか浸透してこなかったリモートワークだが、コロナ禍というやむを得ない理由からにせよ、導入企業はこの2年で一気に増えた。2020年4月に発令された最初の緊急事態宣言が解除された後の実施率は減少しているものの、ツールの普及や社会的な理解の広がりもあって、ある程度、リモートワークは定着したとみられる。
ただ、リモートワーク普及の波は、必ずしも関連するツールの浸透や事業の拡大に追い風になっているとは限らない。むしろツール開発やプロモーションのための組織やコストを急速なリモート化に合わせて拡大しすぎた企業は、状況がやや落ち着いた今、縮小せざるを得なくなっている。
そうした状況の中でも変わらずに業績を伸ばしているのが、オンラインアシスタントサービス「CASTER BIZ(キャスタービズ)」をはじめとするリモートワーク中心の人材事業を展開するキャスターだ。コロナ禍以降は引き合いも増え、2年弱の間に売り上げを2倍以上に伸ばしたという。
「リモートワークを当たり前にする」のミッションを掲げ、2014年9月の創業以来、全社でフルリモートワークを導入するキャスター。2月2日には、シリーズDラウンドとして総額約13億円の資金調達実施を発表した。
キャスターがコロナ禍におけるリモートワーク事業で勝ち抜けた理由を探るべく、同社代表取締役の中川祥太氏に話を聞いた。




