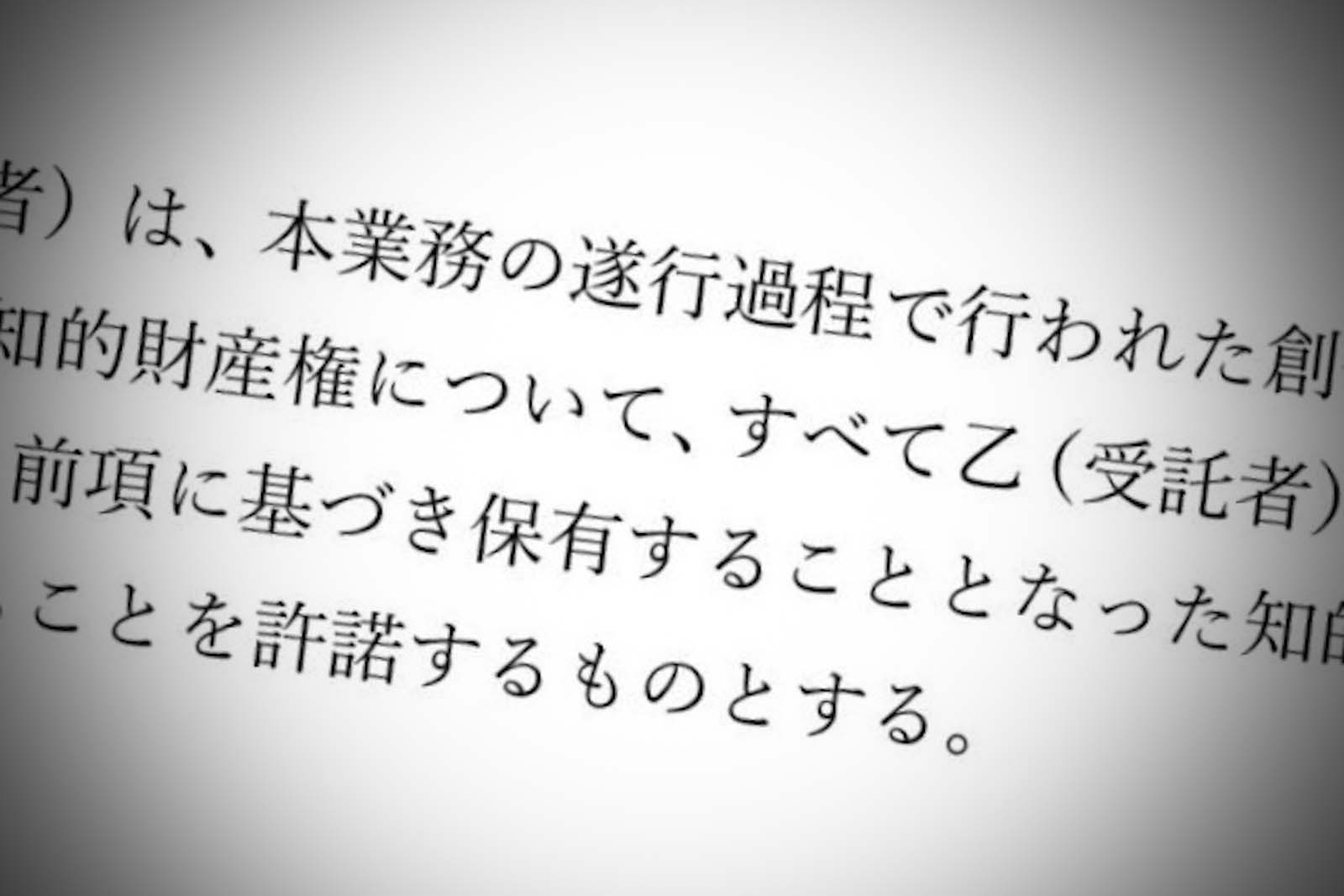
スタートアップが交わす契約書の中には、見落とすことで致命的なダメージになり得る条項がある。
「ヤバい契約書」に引っかからないためにはどうするべきなのか──連載「スタートアップを陥れる“ヤバい契約書”」では実際にあった約書を参考にした架空のストーリーをもとに、スタートアップの法務支援を専門とするGVA法律事務所・代表弁護士の小名木俊太郎氏による監修のもと、読み解いていく。
今回はシステム開発の「業務委託契約書」を取り上げ、解説していこう。
(このストーリーは実際にあった契約書を参考にしたフィクションです。実在の人物・団体・サービスなどとは関係ありません)
開発を委託したプロダクトの「知的財産権」が自社にない──何が起きたのか
舞台となるのは、飲食業界に特化した業務改善SaaSの提供を検討しているスタートアップのシグナル・テクノロジーズ。代表取締役の岡田淳平は、システム開発のためにCTOやエンジニアの採用を急いではいるのだが、はじめてのエンジニア採用に苦戦していた。そこで岡田は知人起業家からのアドバイスを受け、大手SIerのダイヤモンド・ソリューションズにシステム開発を委託した。




