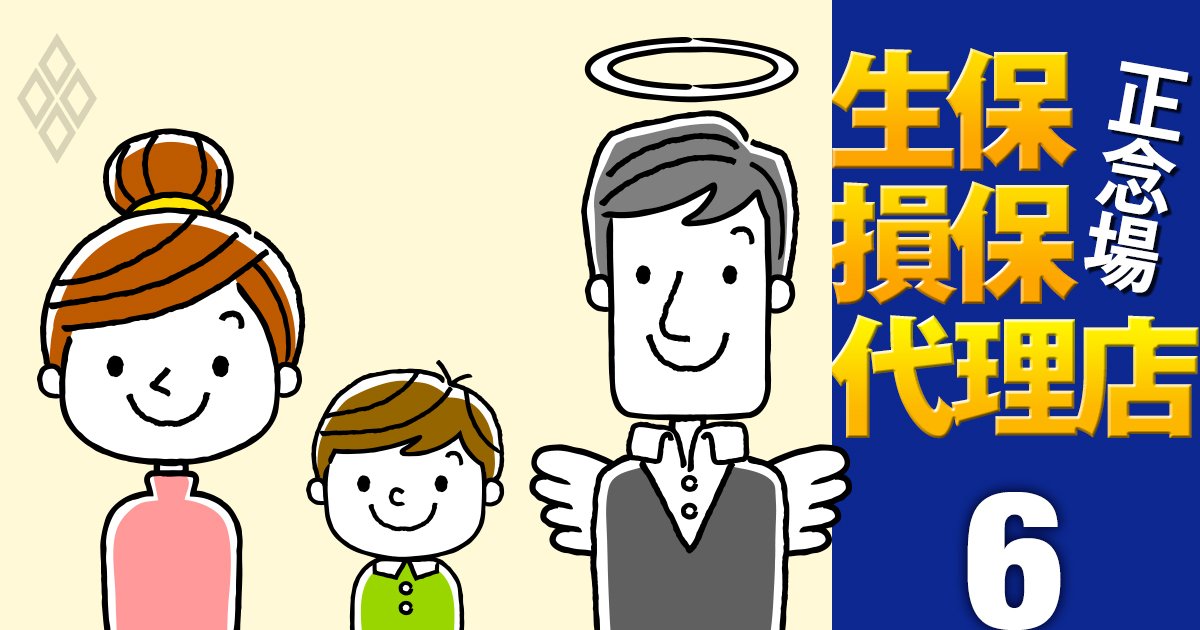ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のサブスクリプション(サブスク)サービス「PlayStation Plus(PS Plus)」が、グループ収益の柱として大きく成長している。その勢いは、同グループがゲーム&ネットワークサービスセグメントにおける2022年度3月期の営業利益の業績予想を2400億円から3000億円に引き上げた理由として説明するほどだ(最終的に営業利益は前期比43億円増の3460億円となった)。3月末にアナウンスがあった新プランは、日本では6月2日にスタートする。
新サブスク「PS Plus」料金設定を任天堂と比較
PS Plusの新プランは、これまで提供してきたサービスに、上位料金プランを追加するというものだ。
基本プランは名称を「PlayStation Plus エッセンシャル」(月額850円)へ変更。これにPlayStation(PS) 4/5用のソフトが数百本フリープレイで遊べる権利を付与した上位プランが「PlayStation Plus エクストラ」(月額1300円)。さらに、初代PS、PS2、PS3やPlayStation Portable(PSP)用のソフトが数百本フリープレイで遊べるようになる権利が付与された「PlayStation Plus プレミアム」(1550円)も加わる。
PlayStation Plus新プラン一覧(2022年6月2日~)
- PlayStation Plus エッセンシャル(月額料金 850円):従来のPlayStation Plusと同じ
-
PlayStation Plus エクストラ(月額料金 1300円):上記+PS4/5ゲーム数百種の遊び放題
-
PlayStation Plus プレミアム(月額料金 1550円):上記+PS/2/3/Portableの遊び放題
この課金方式は、任天堂がニンテンドースイッチ用に用意したサブスク「Nintendo Switch Online」用に用意した2プランに近い印象を受ける。Nintendo Switch Online+追加パックは年額料金プランしか用意されていないため、PlayStation Plusの年額料金と比較してみよう。