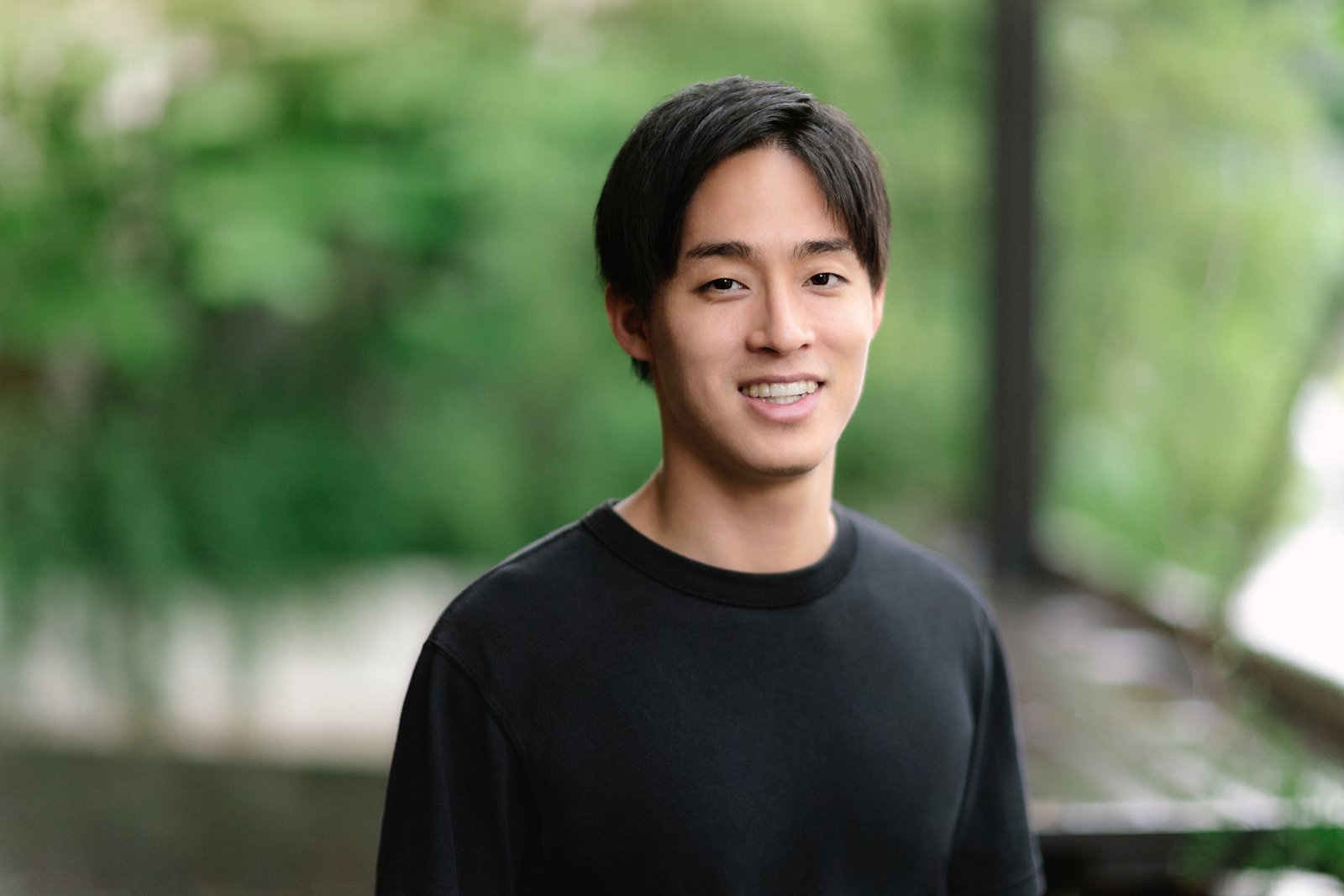
「ユーザーにとって、何かのインセンティブにはならないと思う」
今から4年前の2018年。日本国内の投資家の多くがトークン(代替通貨)に対して、懐疑的な見方をする一方、アメリカではdApps(Decentralized Applications:分散型アプリケーション)を筆頭に、トークンをもとにした経済圏、いわゆる「トークンエコノミー」が大きな盛り上がりを見せていた。
そうしたアメリカの動向を見て、「今後日本でもあらゆるウェブサービスにトークンが組み込まれるようになる」と感じた人物がいる。techtec(テックテク)代表取締役の田上智裕氏だ。同社は現在、“学習するほどトークンがもらえる”をコンセプトにした、暗号資産・ブロックチェーンのオンライン学習サービス「PoL(ポル)」を展開している。
2018年の設立から4年が経ち、投資家たちのトークンに対する見方も変化。トークンエコノミーなどの新たな経済圏は「Web3」と呼ばれるようになり、今や大多数の人たちが「Web3は次なるビッグトレンド」と大きな可能性を感じるようになってきている。
スタートアップ業界を中心にWeb3に対する熱が高まっていく中、techtecは本格的な事業の拡大に向けて、大手企業の傘下に入る決断を下した。同社は6月15日、レアゾン・ホールディングスの子会社となり、グループ入りしたことを発表した。買収金額は非公表。子会社化に伴う、techtec側の経営体制に大きな変更はないという。




