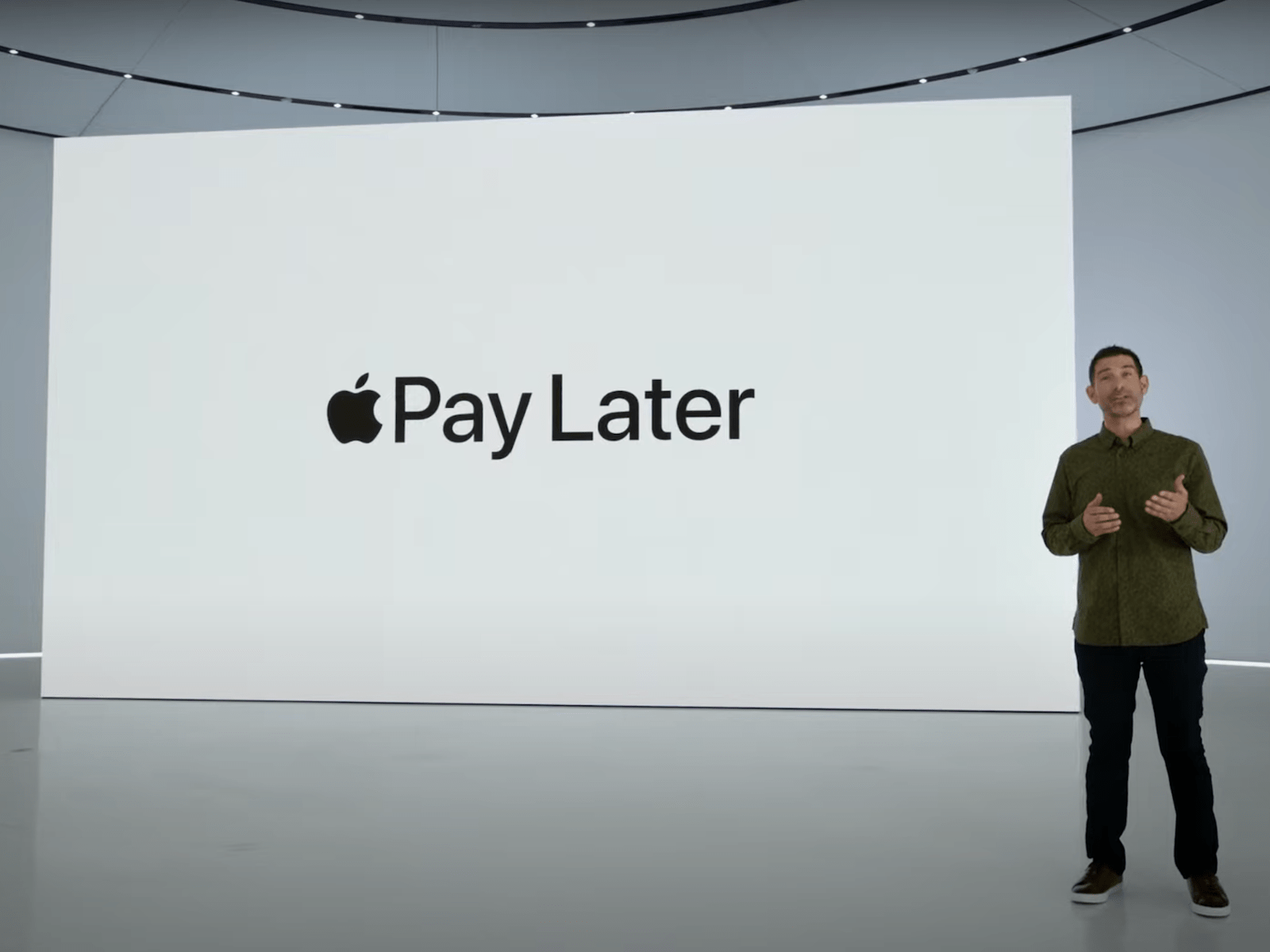
Appleがついに「Buy Now Pay Later(BNPL)」に本腰を入れる。6月初旬に開催された開発者向けのカンファレンス「WWDC2022」で、Apple Payの大きなアップデートとして後払い機能の「Apple Pay Later」を発表した。
この機能を用いると、ユーザーはApple Payでの購入代金を6週間にわたり4回に分割して支払うことができる。金利や手数料などはかからない。Apple Payの導入店舗であればどこでも使える。
“後払い”サービスを意味するBNPLは、近年ECを中心に新たな決済手段として急速に広がっている。グローバルではAfterpayやKlarna、Affirmといったプレーヤーがこの市場を切り開きながら事業を急拡大。日本国内でも「NP後払い」を展開するネットプロテクションズが昨年上場し、「Paidy」を運営するPaidyがPayPalに買収されるなど、関連する事業者のニュースが注目を集めた。
“AppleのBNPL参入”に関しても2021年夏頃から複数のメディアで噂されていたが、今回のタイミングで正式に発表されたかたちだ。
なぜAppleがBNPLに参入するのか。その背景や既存の事業者への影響、今後予想される中長期的な事業展開などについてFinTechスタートアップのFinatextホールディングス取締役CFOの伊藤祐一郎氏に解説してもらった。




