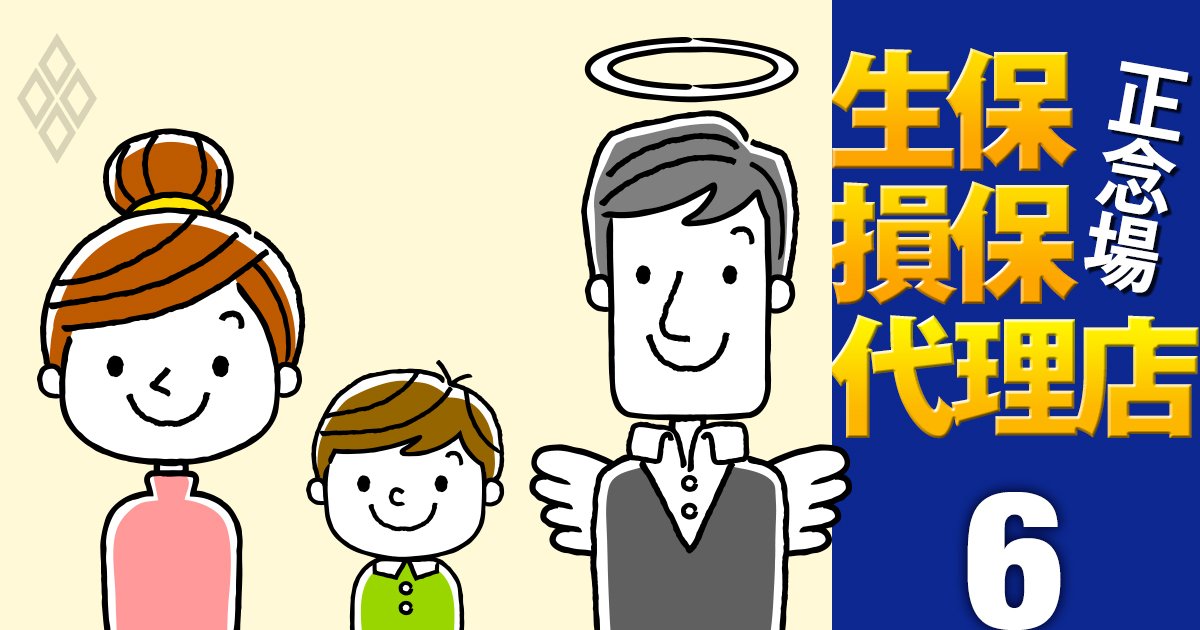ダンボールを軸とした梱包材領域の専門ECサイトとして事業を拡大し、年商約60億円を誇るダンボールワン。同社は少々“異質”な経歴を持ったIT企業だ。
代表取締役社長として長年成長をけん引してきた辻俊宏氏(2022年8月1日付で代表を退任)は、19歳の時に食品ECを運営する会社を起業し、22歳で売却を経験した。その辻氏が次なる挑戦の場として選んだのが“ハローワークでたまたま見つけた”能登紙器だ。
1978年創業の能登紙器は石川県七尾市でダンボールの製造販売を手がけていた町工場で、辻氏が2005年に入社した当時の社員は5人のみ。社内にはパソコンが1台もない状態だった。そこで約半年後、辻氏はゼロからECサイトを開設し、ダンボールのオンライン販売を始める。これがダンボールワンの原点だ。
最初の半年間の売上はわずか7000円で、獲得できた顧客は1社だけ。苦しいスタートとなったが、ユーザーの声をヒントにサービスを改善しながら実績を積み重ねていくと、2017年には会社の売上の8割をECが占めるまでになった。
同年10月には、すでに代表に就任していた辻氏がMBOというかたちで会社の経営権を取得。“プラットフォーム化”を推進しながら事業を広げていく中で、2020年にラクスルから出資を受け、2022年2月に同社の100%子会社となった。