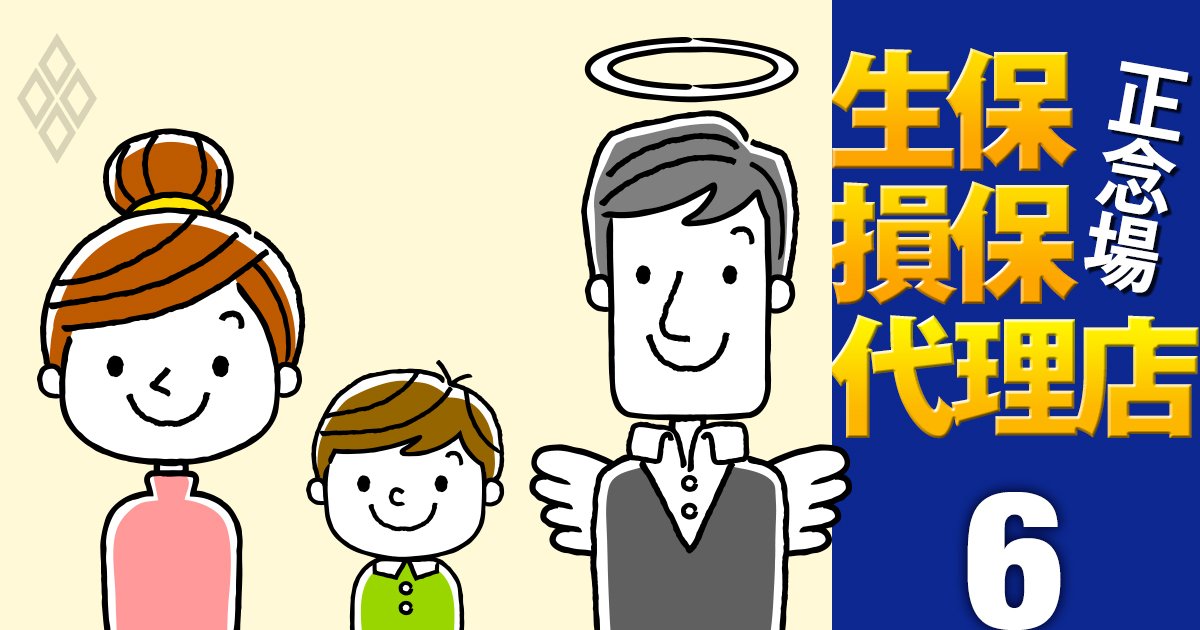「ノンデスクワーカー」──。デスクでPCなどを使って仕事をするのではなく、製造工場や飲食チェーンなど“現場”で働く人々のことだ。調査データなどによって分類の仕方や細かい割合は異なるが、日本国内では就業人口の半数以上、実に3900万人以上がノンデスクワーカーと言われる。
便利なデジタルツールが普及しているオフィスワーカーとは異なり、ノンデスクワーカーの現場では現在でも“紙”を用いた作業が主流だ。オフィスワーカー向けに作られた既存のサービスが必ずしも合致するわけではなく、デジタルやペーパーレスの恩恵を十分には享受できていなかったとも言えるだろう。
そんなノンデスクワーカーの現場が、“現場向けにデザインされたサービス”の広がりによって変わり始めている。
2016年創業のカミナシは、現場向けのDXサービスを展開するスタートアップだ。同社の展開する「カミナシ」は、プログラミング知識なしで業務アプリが作れる“ノーコード”型のソフトウェア。食品工場やホテル、飲食店など現場で働く人々が自らアプリを作り、これまで紙帳票を使って進めていた業務をデジタル化している。
その名の通り「現場の紙をなくす」ことにより、業務効率化や生産性の向上を後押しするサービスだ。