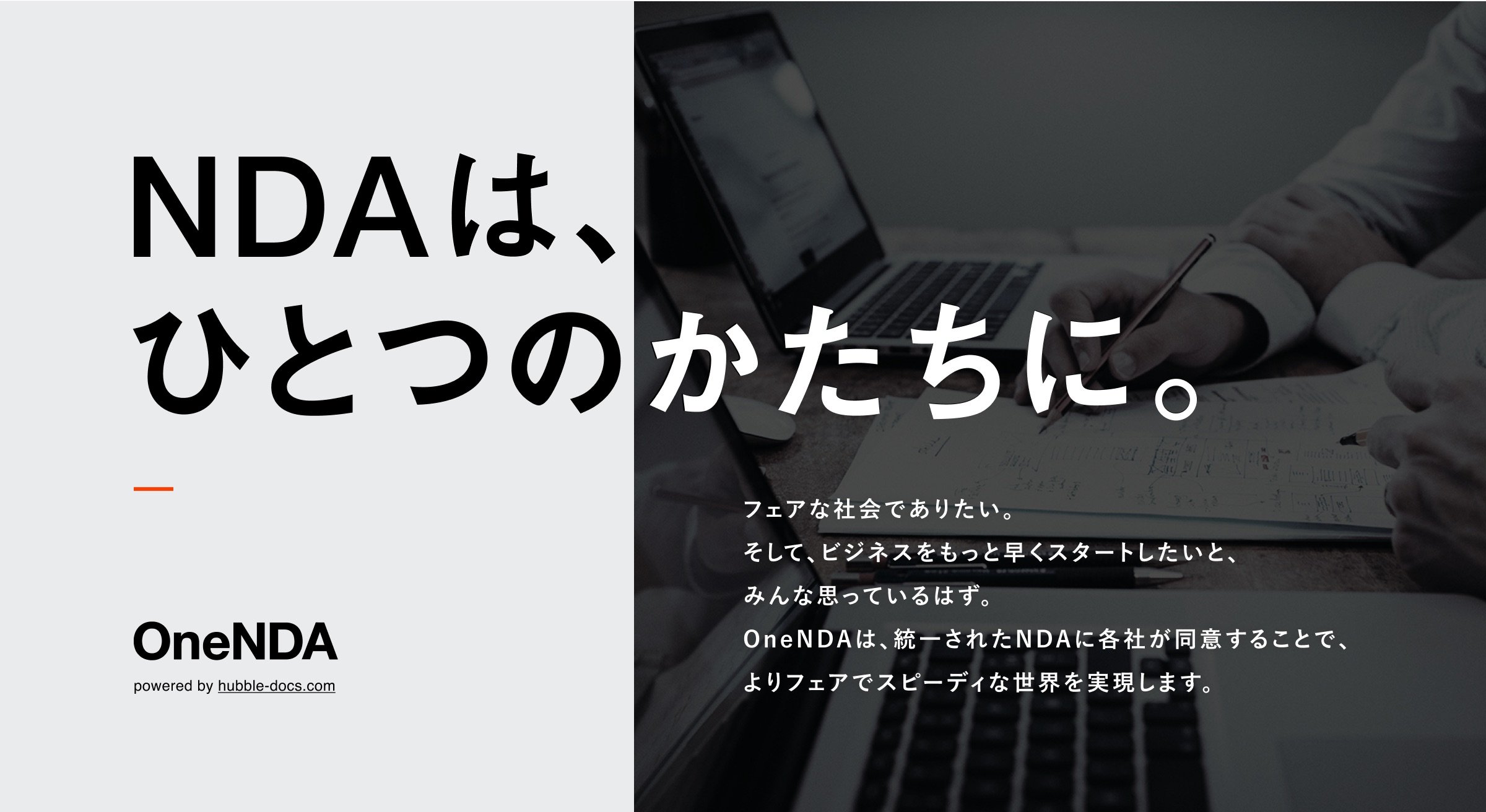
企業にとって自社が保有するノウハウや情報は競争力の源泉にもなりうる重要な資産だ。だからこそ他社と取引をする際にはNDA(秘密保持契約書)を締結し、情報の漏洩を防いだ上でビジネスを進めるのが基本になる。
一方でNDAを結ぶプロセスでは契約書の作成、レビュー・修正、当事者間でのやり取りなどが発生するため、時にはビジネスのスピードを遅くしてしまう場合もある。少なくともそこまでリスクが大きくないものや、慣習的に締結されているようなものに関しては一連の進め方を再発明できる余地があるかもしれない。
リーガルテックスタートアップのHubbleはそのような考えから、NDAを統一化する取り組み「OneNDA」を立ち上げた。
「秘密情報に関する取り決めが重要であることは大前提としながらも、取引の当事者双方が事前に共通認識を持った上で、今まで以上にスピーディーに取引を開始できる状態を作ることができないか。それがこのプロジェクトの大きなテーマです」
弁護士でHubble取締役CLO(最高法務責任者)の酒井智也氏はOneNDAのコンセプトについてそう話す。




