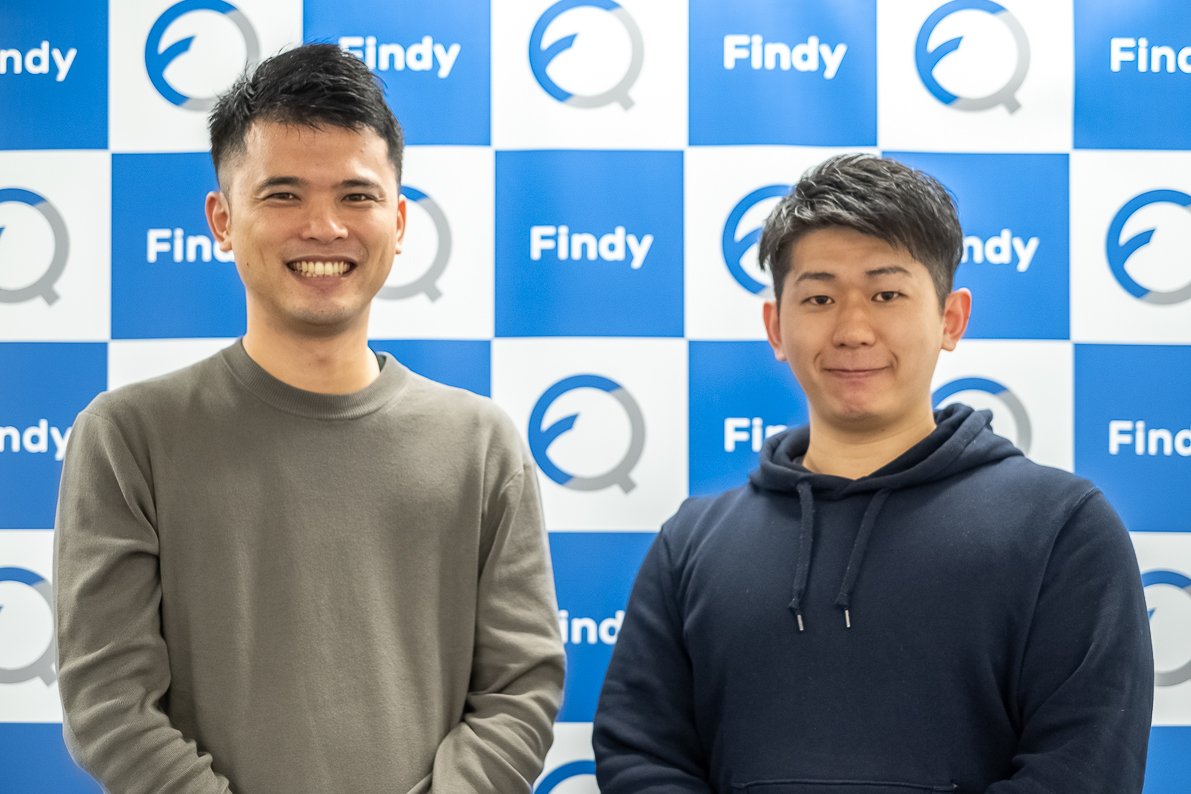
受験生にとって「偏差値」は自分の実力を把握したり、志望校を検討したりする際に重要な指標となる。同じように“エンジニアのスキル”を偏差値という形で可視化することで、キャリアアップを支援しているのがHRスタートアップのファインディだ。
学力偏差値は模擬試験の結果などを基に算出されるが、ファインディのエンジニア偏差値ではソフトウェア開発プラットフォーム「GitHub」を情報源として用いる。
これまで書いてきたコードの量、他のプロジェクトへの貢献度、他者からのコードの支持やアカウントの影響力といったポイントを中心に、エンジニアごとのGitHubを独自のアルゴリズムによって自動で解析。トータルでの偏差値、開発言語ごとの偏差値をそれぞれ割り出す。下図のように「Total 67、Ruby 67、Java 63」といった具合で表示する。

ファインディではこのスキル偏差値を軸にエンジニアと企業をマッチングする仕組みとして2017年12月に「Findy」、2018年2月に「Findy Freelance」をローンチした。
現在2つのサービスを合わせた登録エンジニアの数は約3万人。Findyは日本マイクロソフトやソニー、三菱重工、日本経済新聞社といったエンタープライズ企業からITスタートアップまで約300社が、Findy Freelanceも同じく様々な規模の企業約200社が活用する。




