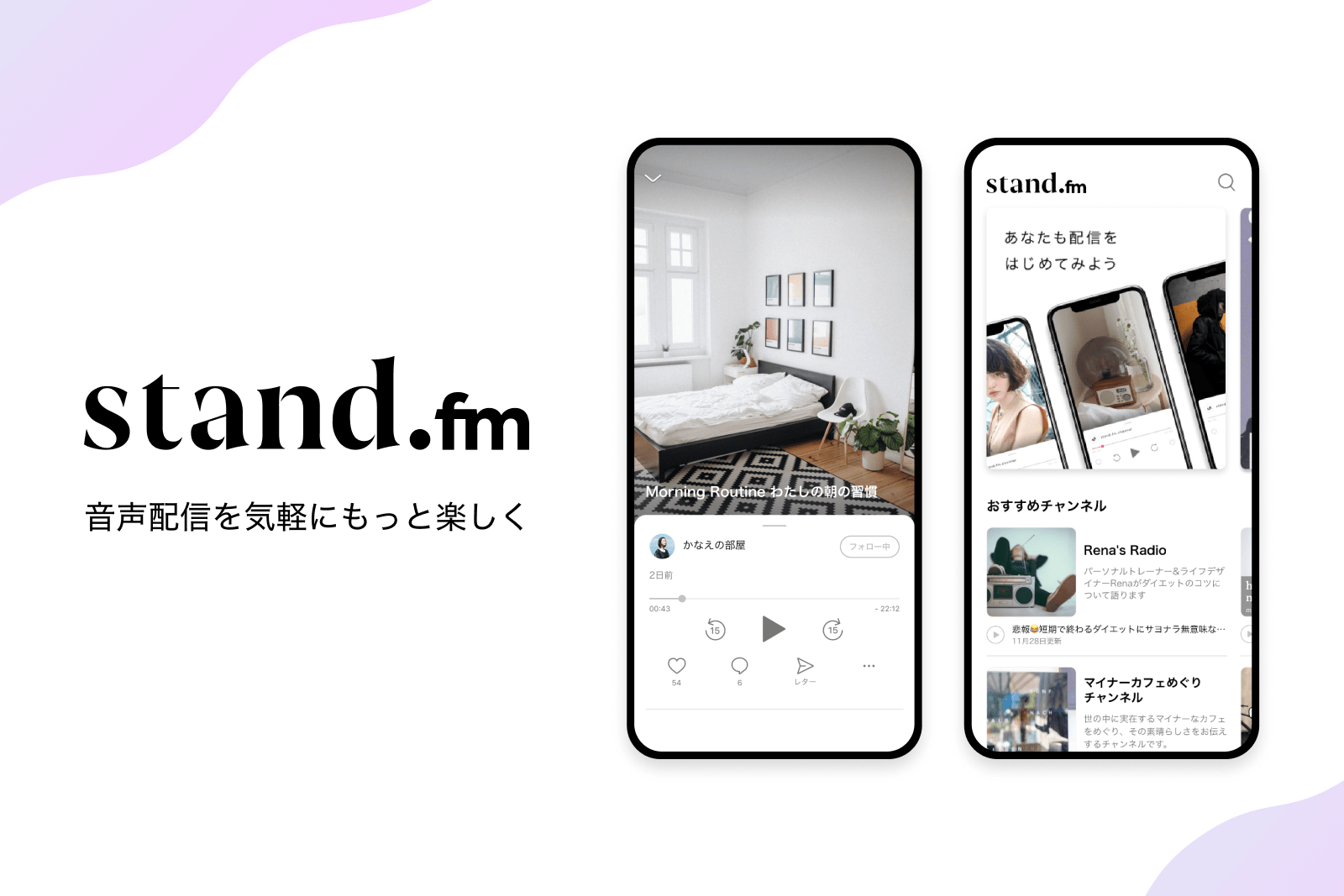
好きなことで、生きていく──2014年、動画共有サービス「YouTube(ユーチューブ)」が実施したCMは大きな話題を呼んだ。趣味で投稿していた動画に広告が表示されるようになったことで収益が生まれ、それが仕事になる。YouTubeに動画を投稿する人たちは「YouTuber(ユーチューバー)」と呼ばれるようになり、小学生がなりたい職業ランキングの上位にランクインにするなど、今や市民権を得ている。
その流れが、今後は「音声サービス」にやって来るかもしれない。音声配信アプリ「stand.fm」を手掛けるstand.fmは8月20日、配信者の収益化を支援する「stand.fmパートナープログラム(以下、SPP)」を開始した。シードラウンドでYJ Capitalを引受先として総額5億円の資金調達を実施したこともあきらかにした。
プログラムの第1弾として、配信者に対して再生時間に応じた収益還元を開始する。審査を通過した配信者は、再生時間に応じた収益を受け取ることが可能になる。2020年内はキャンペーンとして、再生1時間につき4〜6円の収益還元を計画しているそうで、例えば60分の音声コンテンツが2万回再生された場合、10万円前後の収益を受け取れる。今後は単価の調整、音声広告の挿入、ライブ配信時の収益還元なども視野に入れる。
審査に関しては誰でも応募可能だが、配信者の「stand.fm」、YouTube、SNSなどのフォロワー数や発信内容など総合的な角度から審査される。
またstand.fmは今後、配信者が価格を自由に設定し、音声コンテンツを販売できる「コンテンツ販売」や、応援してくれる有料月額ユーザー(サポーター)向けに限定コンテンツを配信する「サポーター機能」も実装する予定とのこと。なお、今回調達した資金はSPPの拡充、マーケティング強化、エンジニア採用に充てる予定だという。




