
新型コロナウイルスの影響で半ば強制的な変化がもたらされ、私たちは「新しい生活様式(ニューノーマル)」への変更を余儀なくされた――そんな人々の生活の変化に合わせて、LINEがサービスを拡大させている。
9月10日、LINEは年次イベント「LINE DAY 2020」をオンラインで開催。オンラインが当たり前の時代に向けた新サービスを発表した。
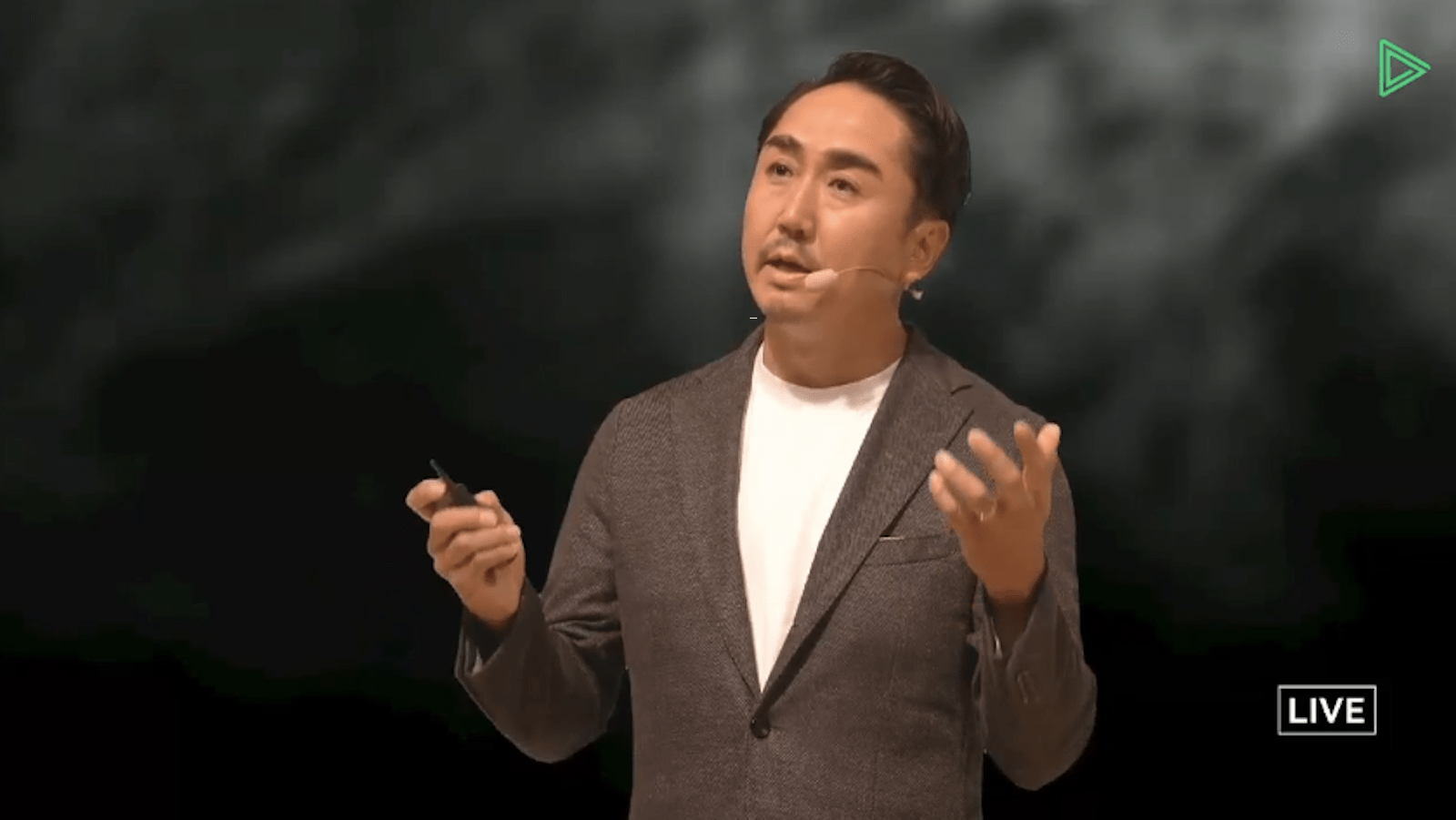
LINEの代表取締役社長兼CEOを務める出澤剛氏は新型コロナを「戦後最大の変化」とし、この変化を元には戻れない「不可逆」なものと形容する。
「コロナを克服した後には、戻ることのない本質的な変化がある。社会を変身させる変化がニューノーマルを形作ります。当たり前を根本から見直すことによって真の意味のパラダイムシフトが起きると思っています」(出澤氏)
実はコミュニケーションサービスの「LINE」自体、2011年の東日本大震災で誕生した経緯を持つ。当時、ネイバージャパンで新しいアプリの開発を検討していた、上級執行役員LINEプラットフォーム企画統括の稲垣あゆみ氏はこう振り返る。




