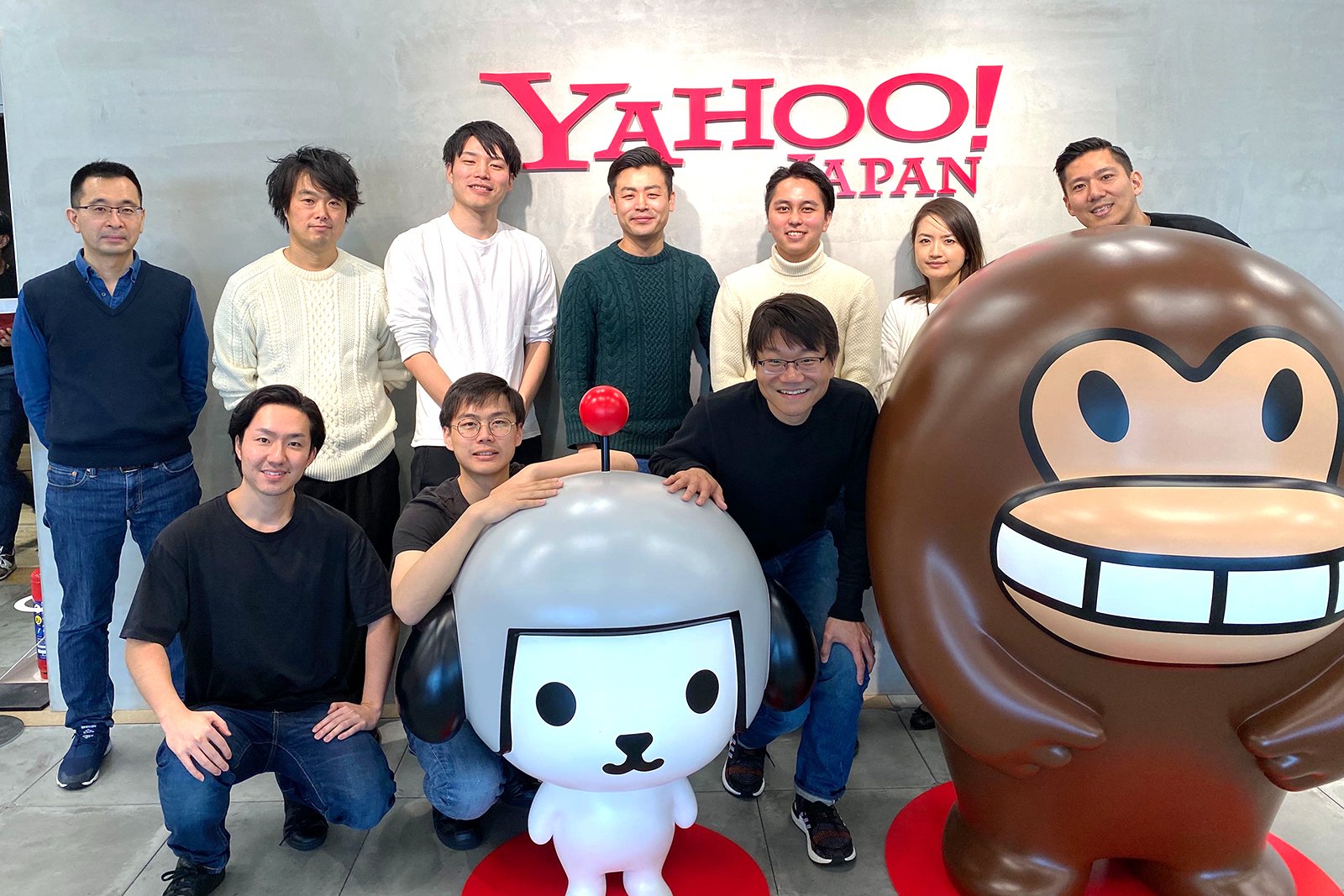
新型コロナウイルス感染症は国内経済にも打撃をもたらしたが、2020年上半期の国内スタートアップの資金調達動向を見ると、企業数では減少しているものの、総額では3359億円と昨年同時期の3188億円を上回る調達が実施されている。
2020年8月には決済・EC事業を展開するヘイが約70億円、自動運転システム用ソフト開発のティアフォーが約98億円を調達するなど、大型調達も行われた。資金調達環境が完全に復調したとは言えないまでも、非常事態宣言が解除され、先の見えない状況からは徐々に抜け出しつつある今、事業成長が見込めるスタートアップには投資家からの注目も集まる。
一方「投資家にとっては、競争は近年激化している」とヤフーの投資子会社、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)であるYJキャピタル代表取締役社長の堀新一郎氏は語る。
堀氏にCVCやスタートアップ投資を取り巻く環境、YJキャピタルの近況や、ZHDとスタートアップとの連携で期待されるシナジー、LINEとの経営統合に寄せる期待などについて話を聞いた。
最初に声をかけてもらうVCになるため投資領域・戦略発信を強化
コロナ禍直前の2018〜2019年は、CVCの設立やファンドの組成も相次ぎ、起業家にとっては投資家を選びやすい状況が生まれていた。堀氏は当時から「YJキャピタルは起業家から一番最初に声をかけてもらうVCにならなければならない。そのためにはファンドの知名度はもちろん、個人でもバイネームで指名されることが重要だ」と考えていた。




