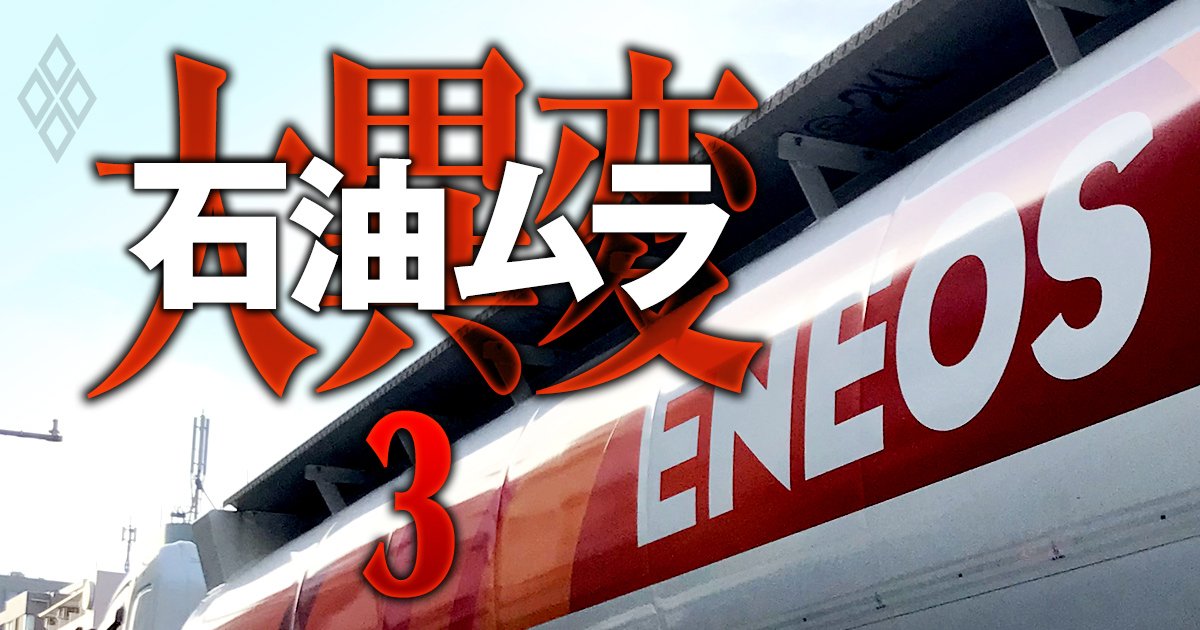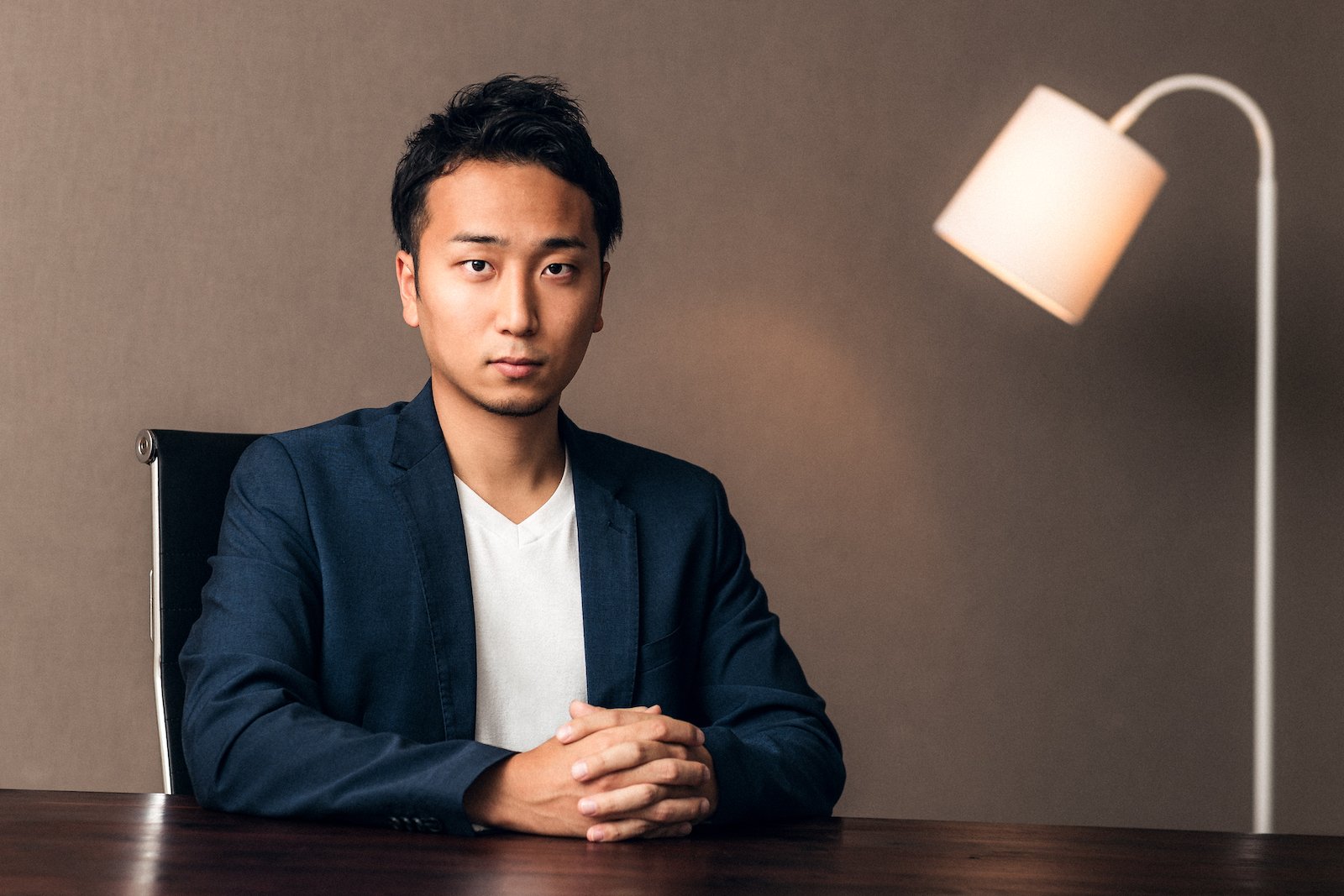
「僕たちは決してクックパッドを倒したいわけではありません」(堀江氏)
レシピ動画サービス「kurashiru(以下、クラシル)」を運営するdely。その代表取締役の堀江裕介氏は取材の冒頭、こう切り出し、続けて自身の考えを語り始めた。
「リスクをとって、新しいマーケットをつくっていく。僕はそれこそがベンチャー企業の使命だと思っています。だからこそ、マーケットシェアを奪い合うことに意識を向けるのではなく、10年後に確実に来るであろう大きな波に対して、早い段階からリスクをとって新しい事業を展開する。大きな勝負に出ることにしたんです」(堀江氏)
これまでレシピ動画サービスのほか、店舗販促デジタル化支援サービス「クラシルチラシ」を展開していたdelyは2020年8月、ネットスーパー支援サービスを新たに立ち上げた。それが「クラシルリテールプラットフォーム」だ。
同サービスは初期費用無料、システム開発不要で小売事業者のネットスーパー垂直立ち上げを支援するというもの。具体的には基幹システムの構築、アプリ・ウェブの注文に関するフロントの設計、ピッキング作業管理、配送ドライバー管理まで一気通貫でシステム開発し、運用段階では専門人材によるプロフェッショナルサポートを提供する。