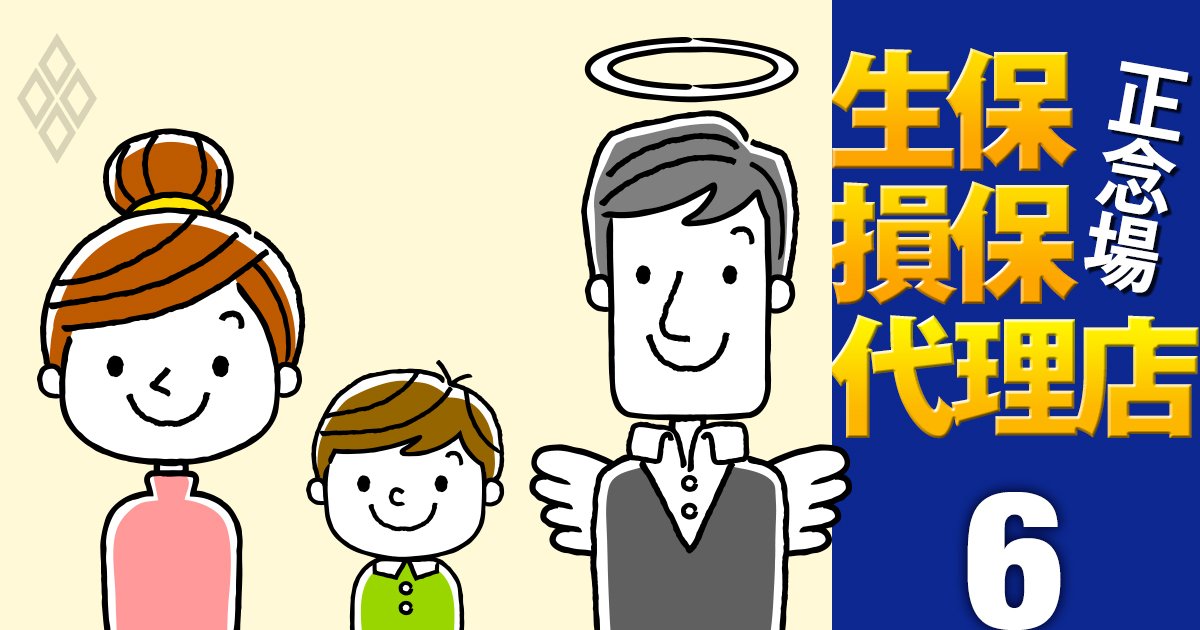日本各地が観光客で賑わう春の大型連休(ゴールデンウィーク)も、今年は新型コロナウイルスの感染拡大で状況が一変した。4月7日の緊急事態宣言の発令に伴い、施設の使用停止(休業)要請や外出自粛の協力要請などで、多くの人が“巣ごもり”を余儀なくされた。その結果、大きなダメージを受けた業界の1つが観光業だ。
例えば、総務省が発表した「家計調査」によれば、2020年5月はホテルなどの宿泊費支出が97.6%減少したほか、パック旅行費も95.4%減少。また航空各社が発表したゴールデンウィークの利用実績は軒並み9割以上の減少となっているほか、JR各社によれば新幹線や在来線特急列車の利用者も9割以上の減少を記録するなど、惨憺たる結果となっている。
「緊急事態宣言の発令で会社の売り上げは正直、99.5%減りました……」
数カ月前の状況を、こう振り返るのはHotspring代表取締役の有川鴻哉氏だ。同社は旅行予約サービス「こころから」、チャット旅行相談・予約サービス「ズボラ旅 by こころから(以下、ズボラ旅)」を運営しているが、コロナ禍で需要は激減。一時は存続の危機に追い込まれた。
政府が国内観光需要喚起を目的として、約1.7兆円の予算を投じた「Go To トラベルキャンペーン」が7月22日に開始されてから、観光需要も少しずつ回復。有川氏によれば、Hotspringの売り上げも7月は前年同月比と同じくらい、8月に関しては数倍の数値を記録したという。