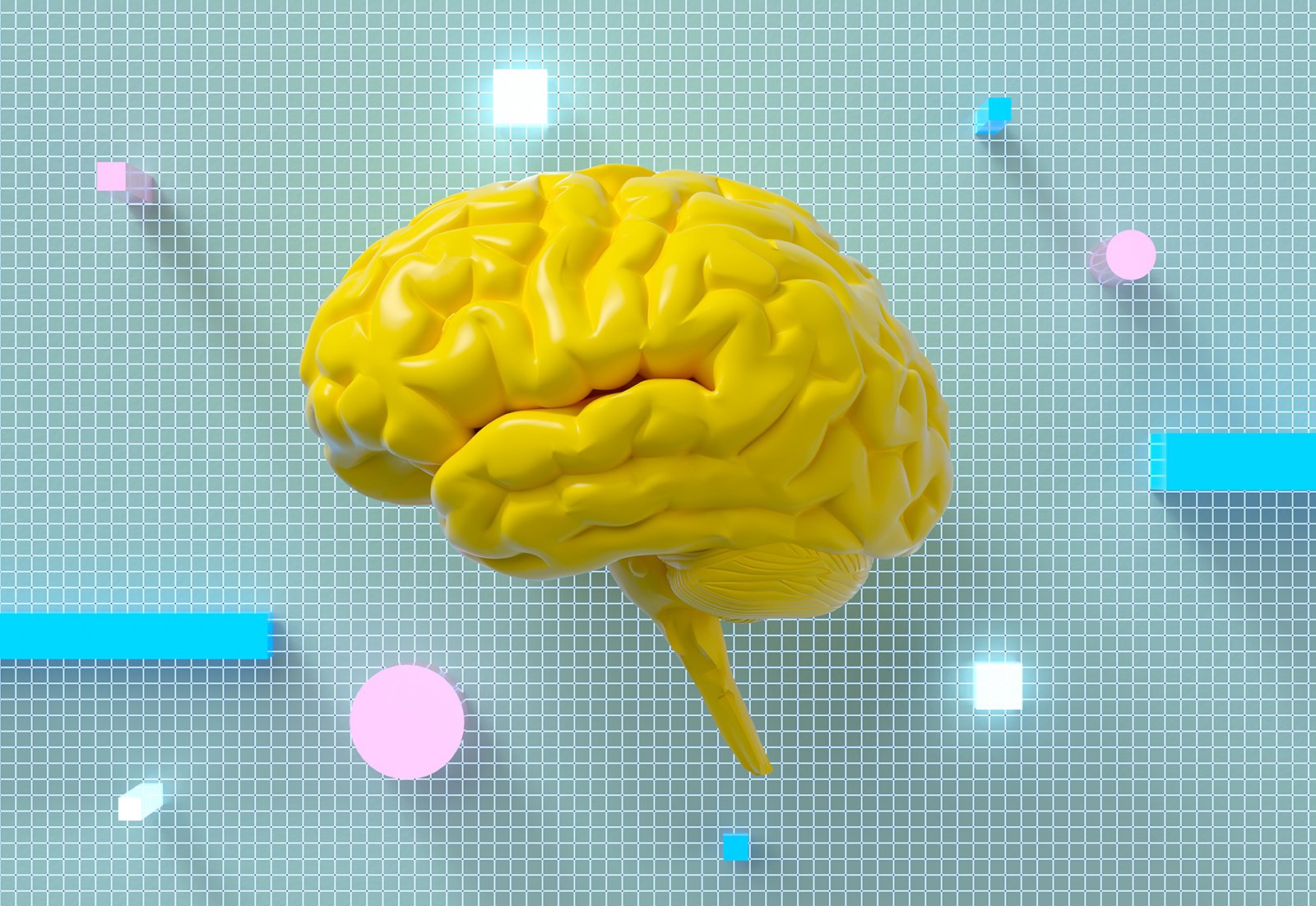
成人の脳卒中・脳梗塞・脳出血の生涯発症リスクは、グローバルでは約25%。4人に1人が脳血管疾患にかかると推定されている。日本でも、死亡率こそ多少下がってきたとはいえ、いまだに死因の第4位を占めている。
また新型コロナウイルス感染者では、30代〜40代で無症状または軽症の人でも脳血管疾患にかかりやすくなると見られており、感染症の影響下では脳梗塞などの患者が7倍に増えたという報告もある。ウィズコロナ時代における患者増の可能性に加えて、高齢化による疾患増加も考えると、今後さらに多くの患者への対応が必要となることが予想される。
脳梗塞やくも膜下出血などを治療する手術方法としては近年、カテーテルを使った「脳血管内手術」が増えている。この手法は従来の開頭手術と比べて患者の体への負担が少ないこともあって、手術件数は年率10%以上で増加している。ただし、脳血管内手術を執り行う医師にとっては、複数の部位を同時に確認しながらミリ単位の繊細な操作が必要で、高い技量と長時間の集中力が求められる。
この脳血管内手術をディープラーニング技術で支援しようという「手術支援AI」を開発するのが、脳神経外科医で脳血管内治療の指導医も務める現役医師、河野健一氏が率いるiMed Technologies(アイメッドテクノロジーズ)だ。
「より安全な脳血管内手術」実現のためにAIが医師をサポート
iMed Technologies代表取締役CEOの河野氏は、脳神経外科医として16年間、医療現場で手術を行ってきた。手術支援AI開発の背景には、河野氏が手術の最中、見落としによりステント(血管を内側から広げるチューブ状の医療器具)で血管を突き破りそうになったという現場での原体験がある。河野氏は同僚からも、時折同じような「ヒヤリ」体験を聞くことがあるという。




