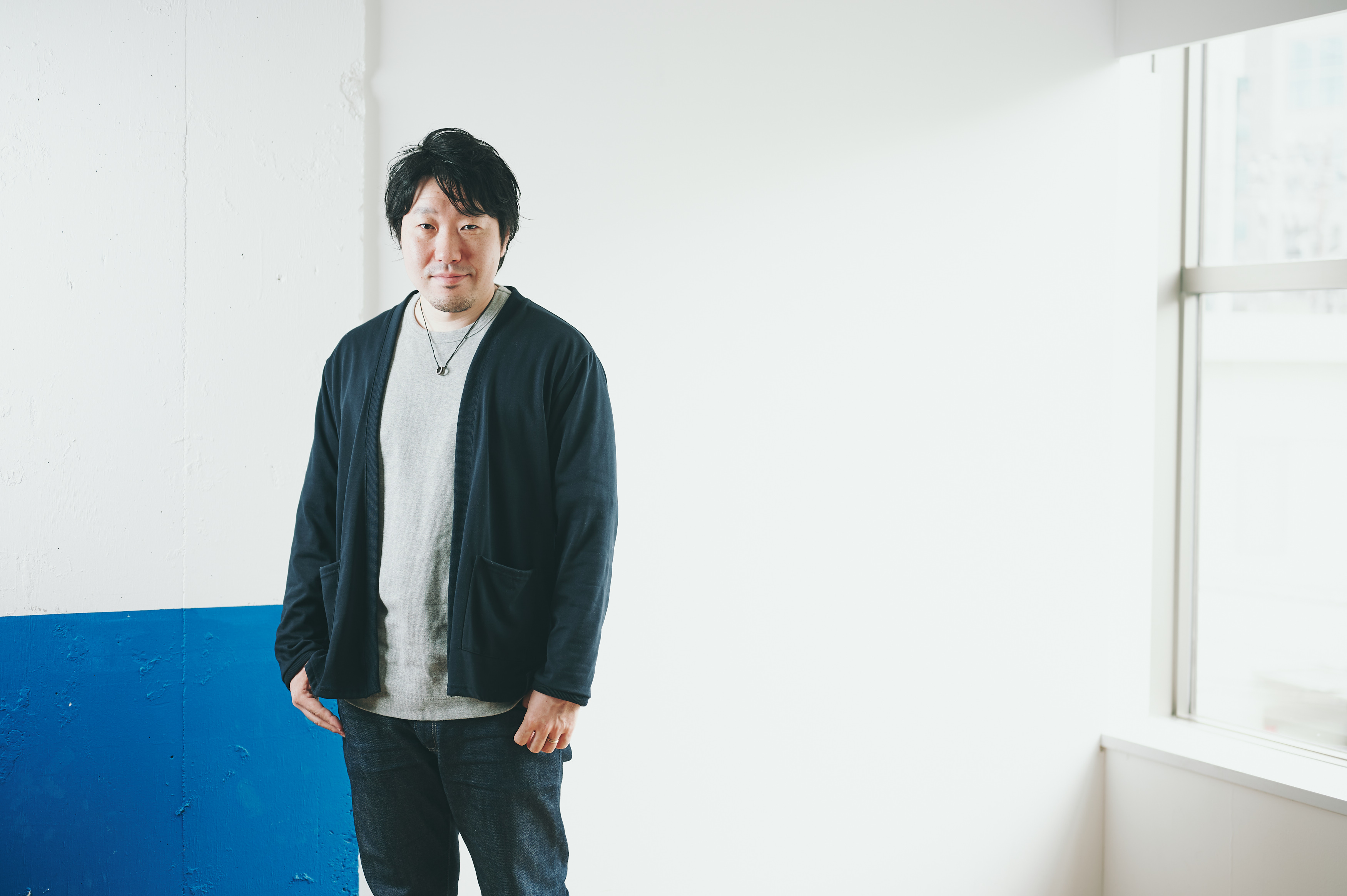
「グッドパッチを会社として残し続ける手段が、上場だったんです」
そう話すのは、2020年6月に東証マザーズに上場したグッドパッチ代表取締役社長兼CEOの土屋尚史氏だ。グッドパッチは「デザインの力を証明する」をミッションに掲げて、ソフトウェアのUI/UXのほか、組織・ビジネスのデザインなどを行ってきた。
10月には上場後初となる2020年8月期の通期決算を発表した。売上高は21億4300万円(前年同期比27.3%増)、営業利益は2億1600万円(同187.3%増)、経常利益は2億1100万円(同153.3%増)、純利益は2億1500万円(同275.9%増)。下半期にコロナ禍の影響を受けつつも、業績予想に対して95.8%で着地。堅調な成長をアピールしている。また、スタートアップへの出資からデザインまでを支援する「Goodpatch Design Fund」も立ち上げた。
コロナ禍でも成長を続けるグッドパッチだが、彼らも他のスタートアップ同様、これまで数多くのハードシングスを乗り越えてきた。中でも大きかったのは、「壊滅的な組織崩壊」だったという。スタートアップにおいて難しいフェーズと言われる「50〜100人の壁」で起こったその“事件”と、それを超えて上場を目指した理由を聞いた。
創業当時は「出資してもらうイメージもなかった」
グッドパッチの創業は、2011年9月。きっかけは、サンフランシスコで働いていた土屋氏が、次々と立ち上がるスタートアップのサービスにおいて「デザイン」が重要な役割を果たしているところを目の当たりにしたことだった。




