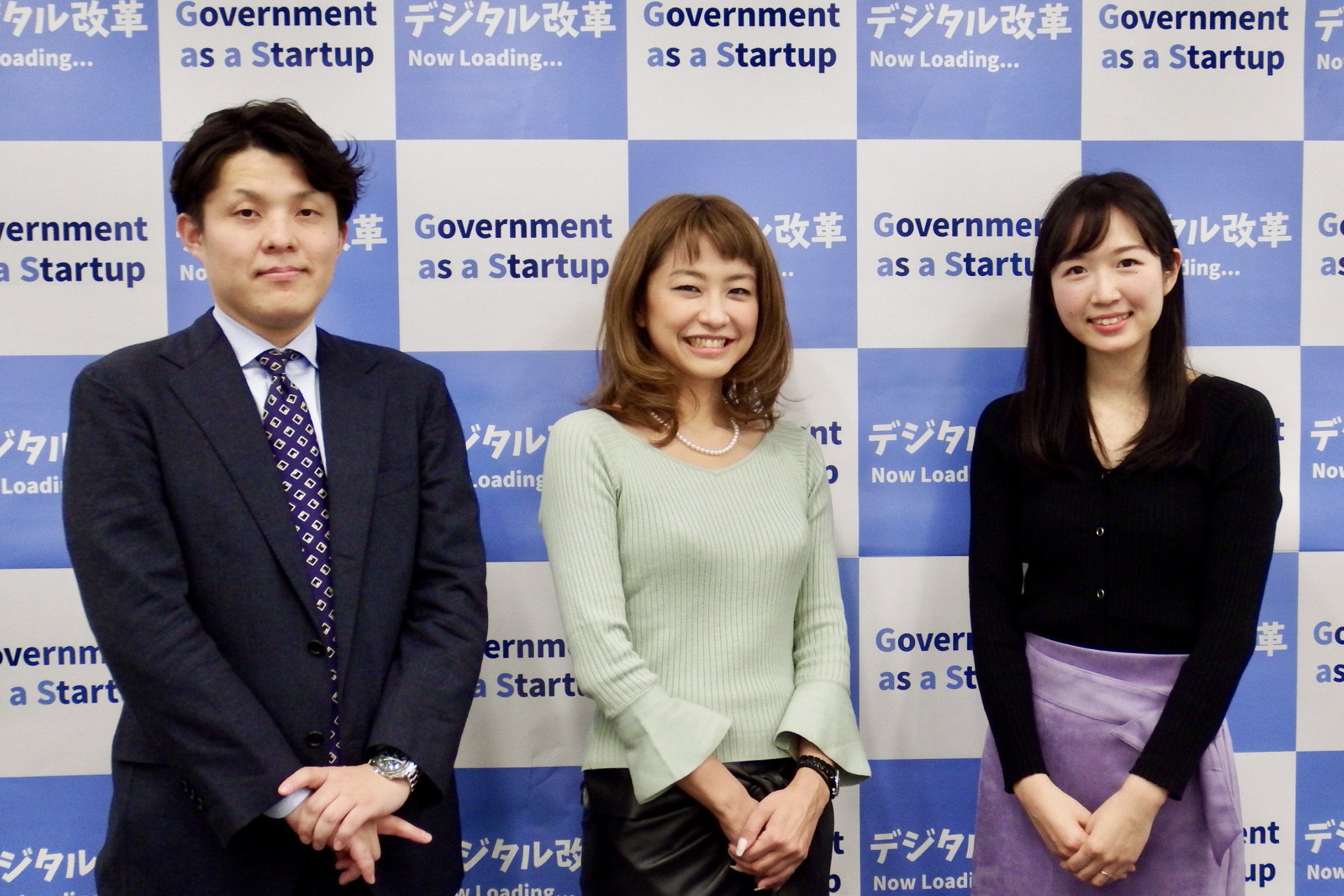
2020年9月に発足した菅内閣。矢継ぎ早に様々な政策が打ち出される中、同内閣が“目玉政策”として掲げたのが「デジタル庁」の設置だ。
デジタル庁は行政のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進する新たな行政機関。年内にも基本方針が策定され、2021年1月の通常国会での関連法案の提出を経て2021年9月に発足する予定となっている。行政手続きのデジタル化を進め、「豊かな国民生活と誰一人取り残さない社会」の実現を目指していく。
デジタル庁の設置を主導する平井卓也デジタル改革担当大臣は、デジタル庁長官には民間人を充てる方針を示している。また、デジタル庁はエンジニアなどのIT人材を民間から100人ほど起用し、500人規模の体制でスタートする予定だ。
来年9月のデジタル庁発足に向けてデジタル改革関連法案準備室は12月21日、民間人材の公募を開始することを発表した。今回、募集するのは、各省の情報を一気通貫で検索できる「政府統一ウェブサイト」、政府情報システムのクラウド化に向けた「ガバメントクラウド」や社会の基幹となるデータベースの「ベースレジストリ」といったプロジェクトの構築業務を担当するポジション。公募は2021年1月上旬より開始する予定だ。
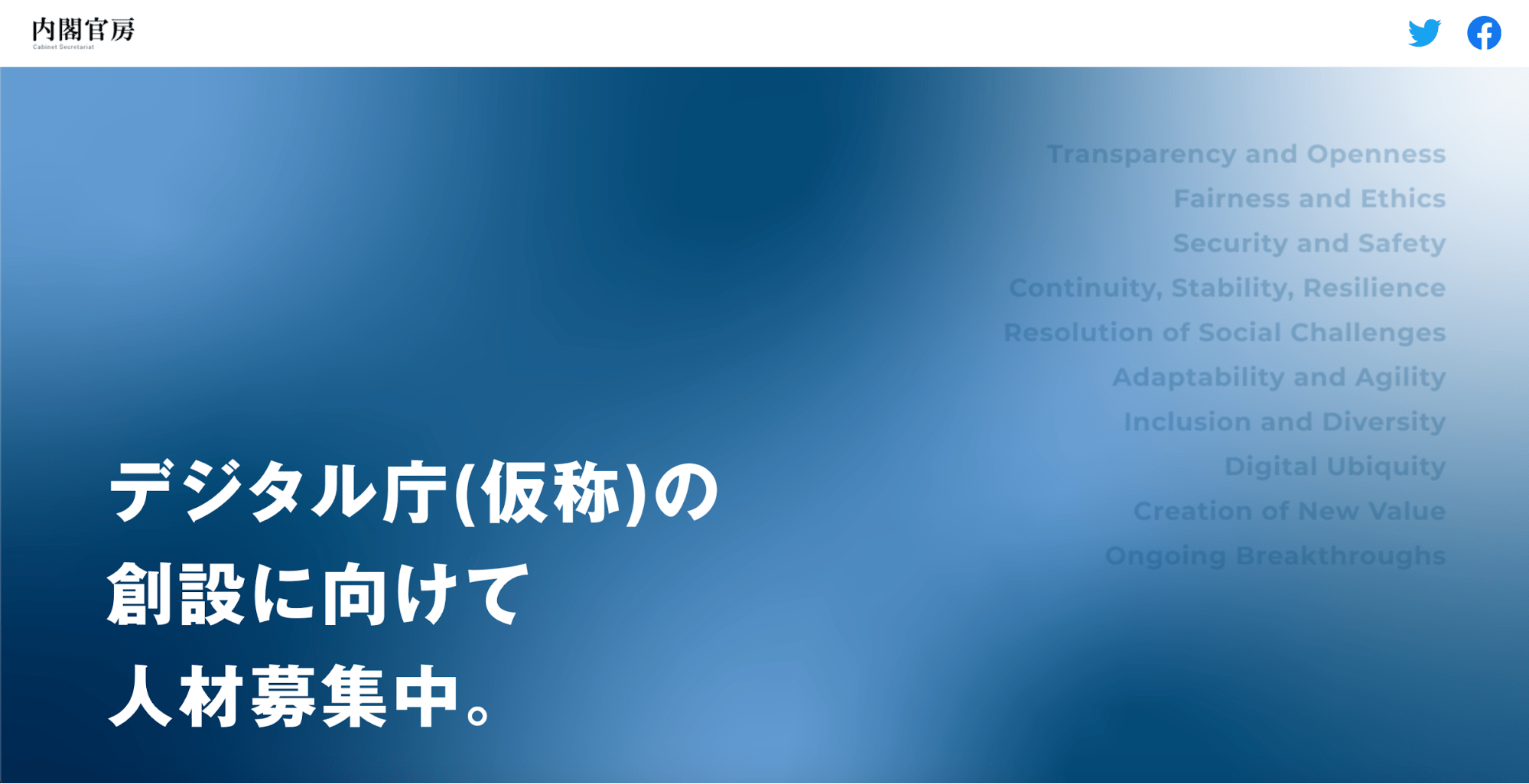
採用された人材は2021年4月に開設予定の“デジタル庁準備室”への配属となり、先行して各プロジェクトを進めていく。なお、デジタル庁では今回の募集にあたり、採用サイトをスタートアップのHERPと共同で開設。同社が提供するATS(採用管理)ツール「HERP Hire」を導入したという。




