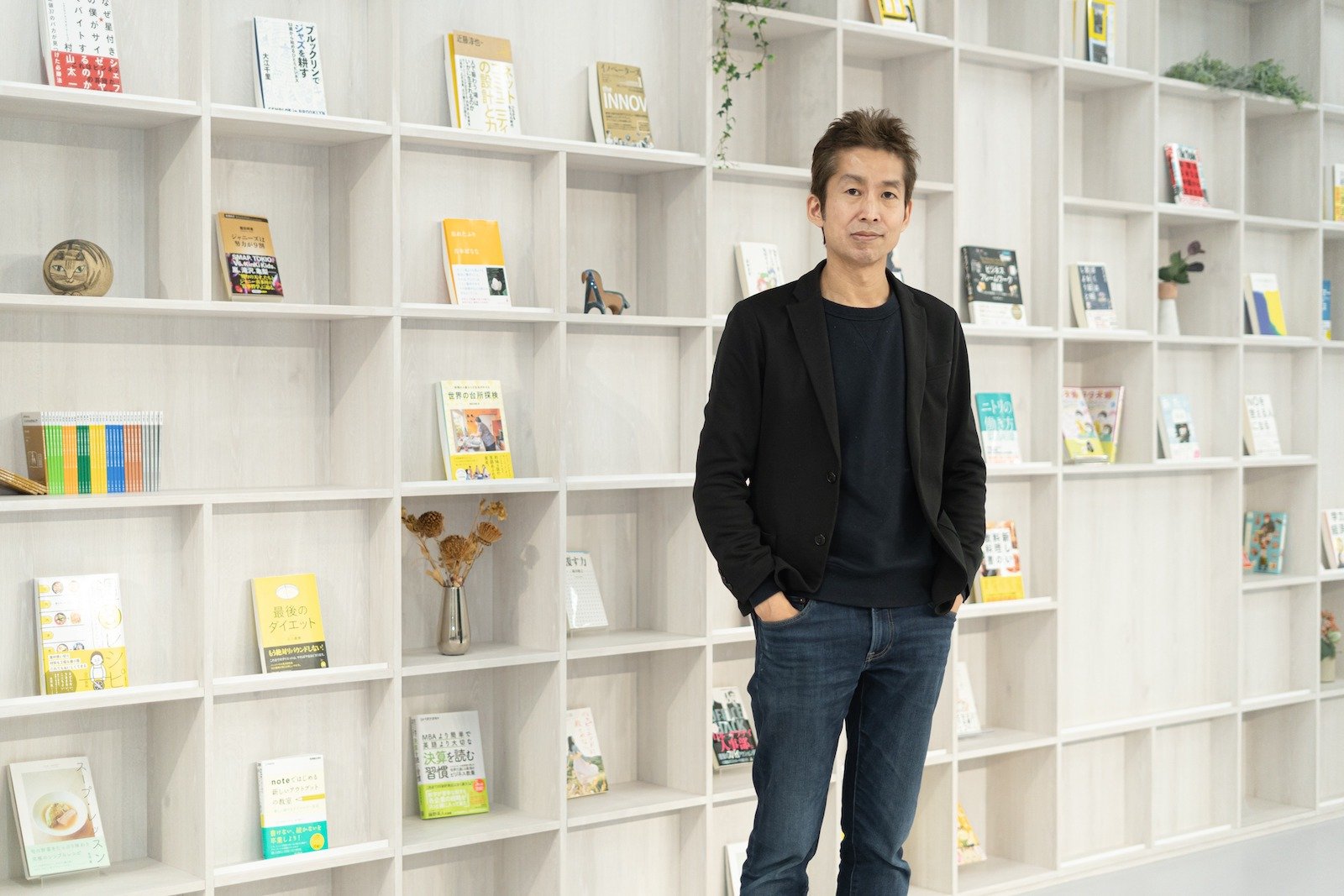
文章、写真、イラスト、音楽、映像といった作品を個人のユーザーが配信できるメディアプラットフォームの「note」。月間アクティブユーザー数(MAU)が6300万人を超える(2020年5月時点)人気プラットフォームだが、2020年には「炎上騒ぎ」が相次ぎ、運営元であるnoteは批判を浴びた。
一連の炎上は昨年の8月に始まる。noteユーザーのIPアドレスが記事詳細ページのソースコードから確認可能になっていたことが明らかとなり、「IPアドレス漏洩問題」と騒がれた。10月以降はnoteが運営する有料ウェブメディアの「cakes」に対する批判が相次いだ。
2020年にはプラットフォームとしての資質が問われる騒動も相次いだnoteだが、運営体制・方針を改めるとともに、更なるサービス拡充のための動きを急速に進めている。
2020年12月にはクリエイターの発掘および育成や社員交流などを目的とし、大手出版社の文藝春秋との資本業務提携を締結。そして2021年1月12日、ECプラットフォームのBASEとの資本業務提携を明らかにした。BASEからnoteへの出資額は非公表となっている。なお、文藝春秋との資本業務提携は発表時には非公開だったが、登記情報によれば約2億円。今回の資本業務提携も文藝春秋との提携同様、パートナーシップ強化の意味合いの強いものだという。
ベンチャーキャピタルや事業会社に加え、日本経済新聞社やテレビ東京ホールディングスなどの伝統メディア企業からも資本提供も受け、信頼性高いプラットフォームの確立を続けるnote。一方で昨年はその成長痛が顕著に表れた年にもなった。BASEとの提携の狙い、そして炎上騒動を越えた今後の展開についてnote代表取締役の加藤貞顕氏に聞いた。




