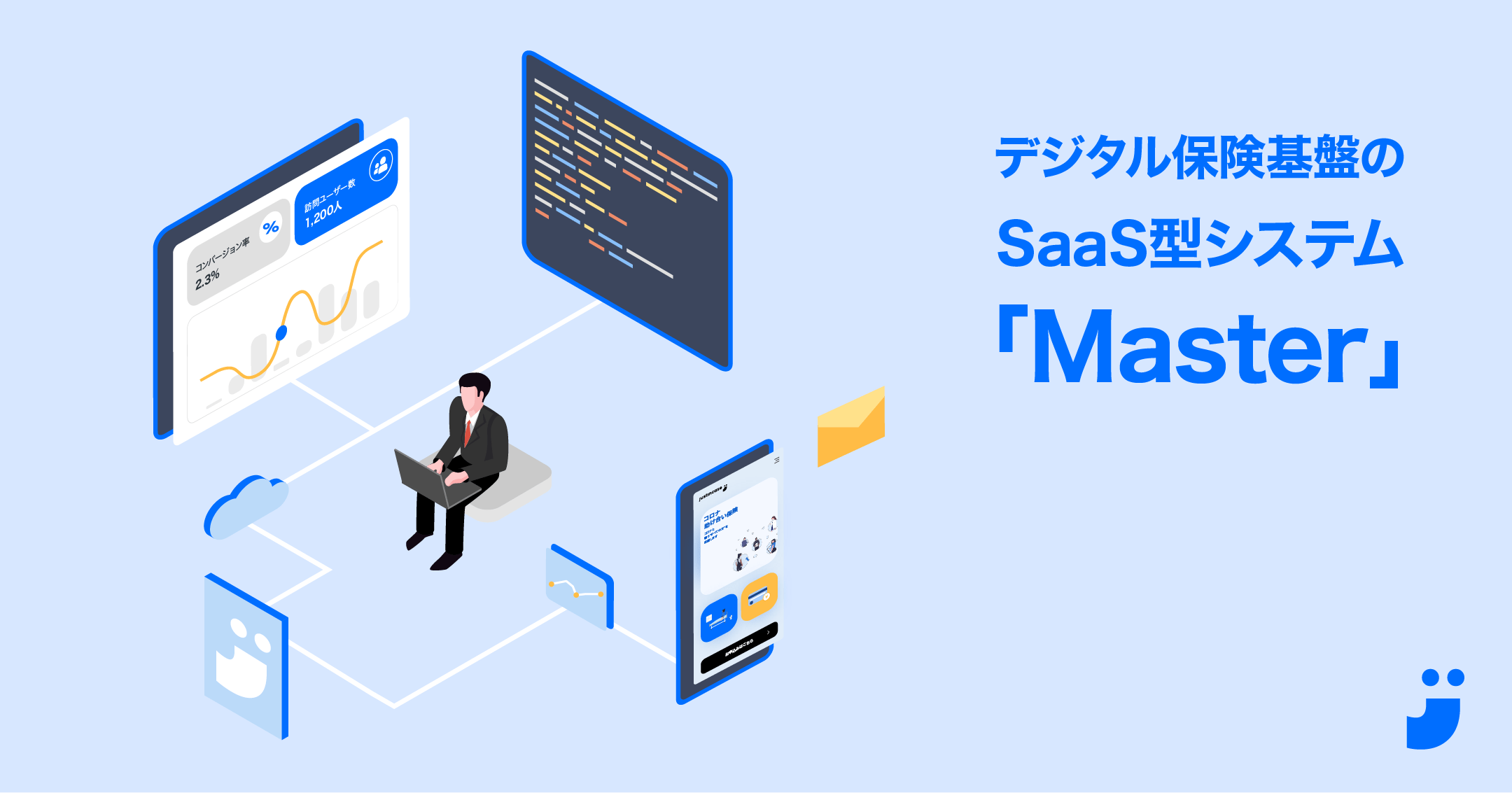
保険金を加入者同士で“わりかん”する後払い型のがん保険(わりかん保険)を筆頭に、独自の商品を複数展開してきた保険テックスタートアップのjustInCase(ジャストインケース)。これまで少額短期保険業者として個人向けのサービス開発に力を入れてきた同社が、新たな一歩を踏み出した。
兄弟会社であるjustInCaseTechnologiesを通じて、1月21日より保険会社向けにSaaS型のデジタル保険基盤「Master(マスター)」の提供を始める。
Masterは保険システム基盤、アプリ基盤、マーケツール基盤という3つの機能を用いて、保険会社を後押しするソフトウェア。このサービスのローンチはjustInCaseが自ら保険商品を開発することから、“イネイブラー”として既存の事業者をサポートする方向へと事業の軸をシフトしたことを意味する。
justInCaseおよびjustInCaseTechnologiesで代表取締役を務める畑加寿也氏の話では、約2年半にわたって複数の保険サービスを運営する中で見えてきたこと、そしてコロナ禍での業界の変化が今回の意思決定にも大きく影響を与えたという。
テクノロジーを活用し、独自の保険商品を次々展開
justInCaseは保険領域でのビジネス経験が豊富な畑氏が、2016年12月に立ち上げたスタートアップだ。畑氏は数理コンサルティング会社Millimanで保険数理に関するコンサルティングに従事した後、投資銀行やミュンヘン再保険を経てjustInCaseを創業。起業前は一貫して保険会社向けのサービスに携わっていた。




