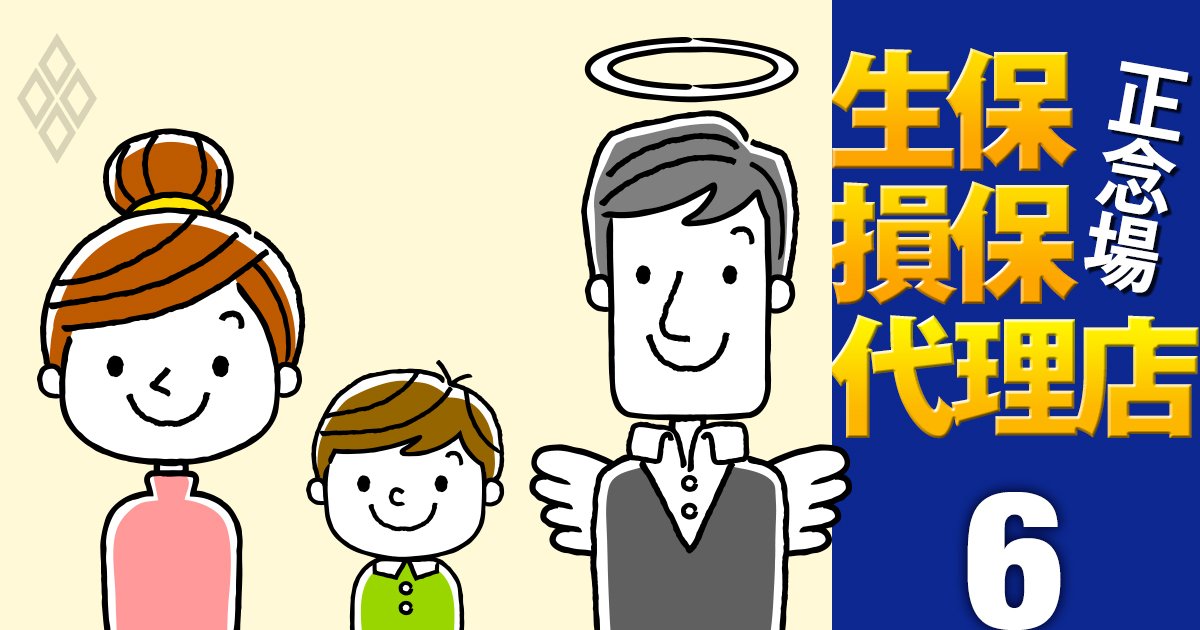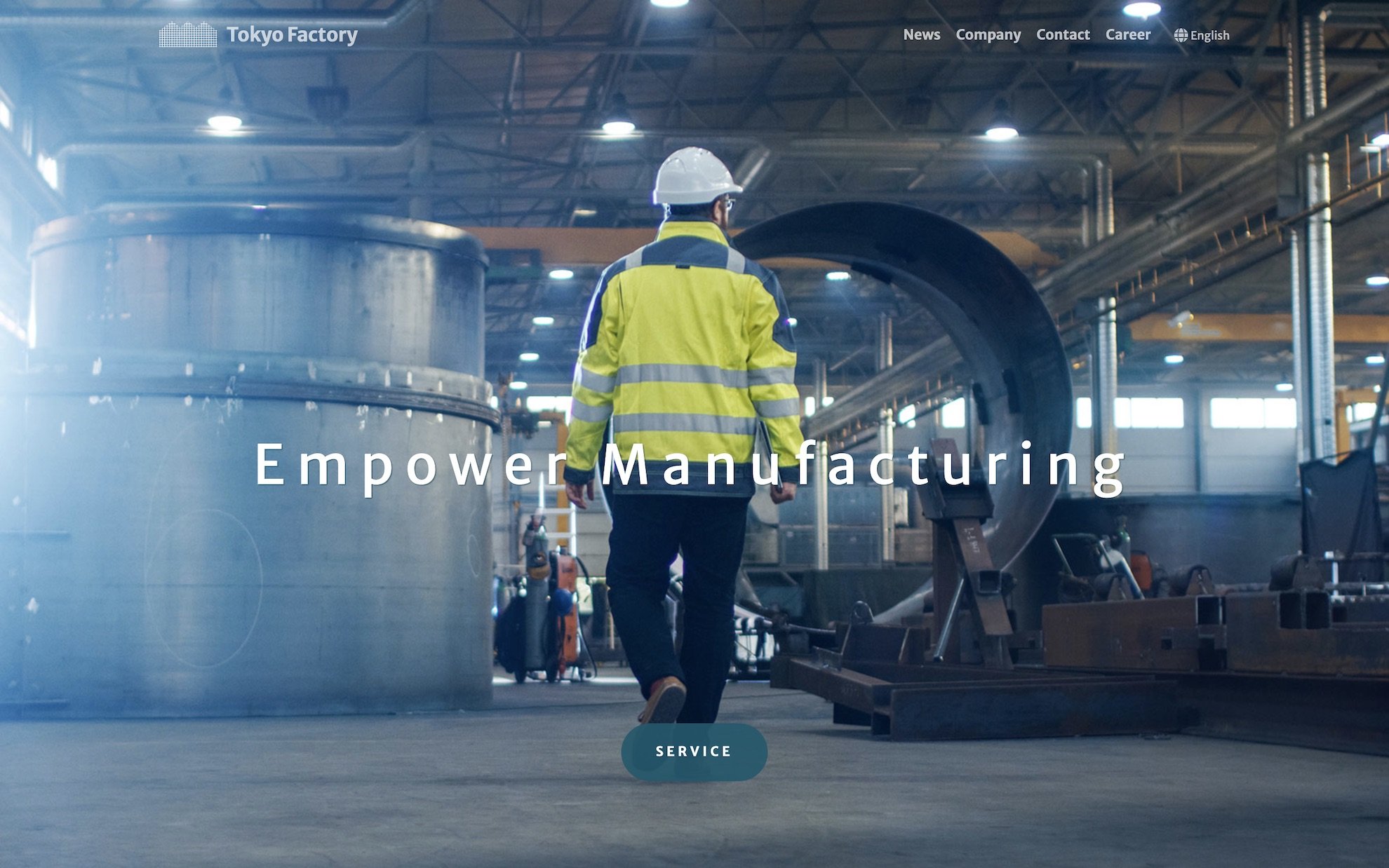
「一貫して製造業のキャリアを数年間歩んできた中で気づいたのが、製造業の中でも特に重工業がレガシー産業であり、現場でのデジタル活用が遅れていること。(プロセス系製造業や電子系製造業など他の分野に比べても)作業の標準化が難しいためどうしても労働集約型になりがちで、デジタルの恩恵を受けることができていませんでした」
そう話すのは製造業の生産現場を支援するSaaS「Proceedクラウド」を開発する東京ファクトリー代表取締役の池実氏だ。
池氏は新卒で川崎重工業へ入社後、ボストンコンサルティンググループ(BCG)を経て2020年4月に東京ファクトリーを立ち上げた。
現在同社が手掛けるProceedクラウドでは生産現場で撮影される“工程写真”を基に、製造情報のデータベースを構築。これによってサプライチェーンの見える化と技能継承をサポートする。
目指しているのは、デジタルツールの提供によって「今後も日本の重工業が世界ナンバーワンであり続けること」に貢献すること。これまで現場で十分に活用されてこなかった工程写真とテクノロジーを用いて、プラント機器や船舶、大型構造物などを製造する重工業のDXを推進していく計画だ。