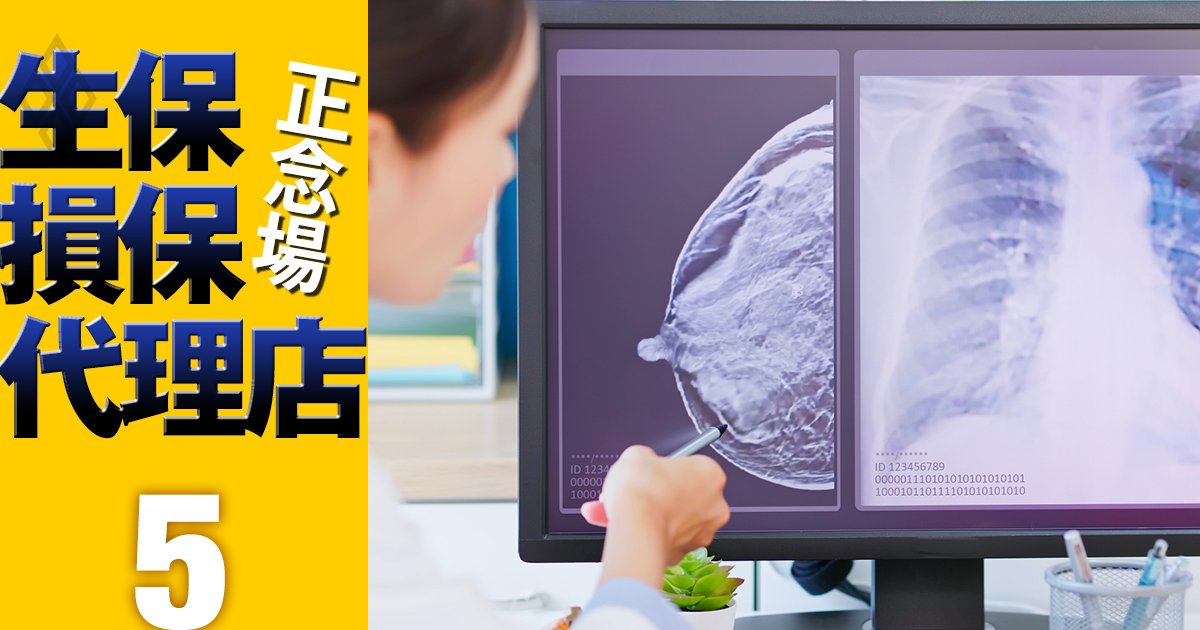2021年に入り日本でも音声SNSアプリ「Clubhouse」が急激に台頭したことで、“音声”というフォーマットが改めて評価され始めている。それに伴い以前から次のトレンドとして注目されていた「常時接続SNS」の時代も本格的に近づいてきたような印象だ。
昨年1月にナナメウエが公開した「Yay!(イェイ)」もまさにその時流に乗るような形で短期間のうちにユーザーを増やしてきた。代表取締役の石濵嵩博氏が「たとえるならmixiのコミュニティのような場所を今のZ世代向けにリビルディングしたようなイメージです」と話すように、Yay!では世代や趣味趣向の近いユーザーが繋がり、新しい人間関係が生まれるコミュニティとして人気を集める。
主要な機能の1つが最大12人で楽しめるグループ音声通話だ。もともとはユーザー同士の交流を深める仕組みの1つとして実装した機能だが、コロナ禍では「家にいる時間はとりあえず通話を繋いで長時間雑談をする」という使い方が浸透。まさに常時接続SNSの文脈で使われるサービスになりつつある。
12月1日時点で登録ユーザー数は200万人を突破し、直近ではClubhouseの登場に伴って1日あたりのアプリインストール数も以前の2倍になっているというYay!。同サービスの実態や今後の展望について石濵氏に話を聞いた。
音声通話が人気、数時間つなぎっぱなしのユーザーも
上述した通り、Yay!は世代や趣味趣向の近いユーザー同士がオンライン上で交流できる匿名性のSNSだ。Twitterアカウントや電話帳と連携することもできるが、基本的にはリアルな友人同士をマッチングするような仕様にはなっておらず、新しい繋がりが生まれることを重視して設計されている。