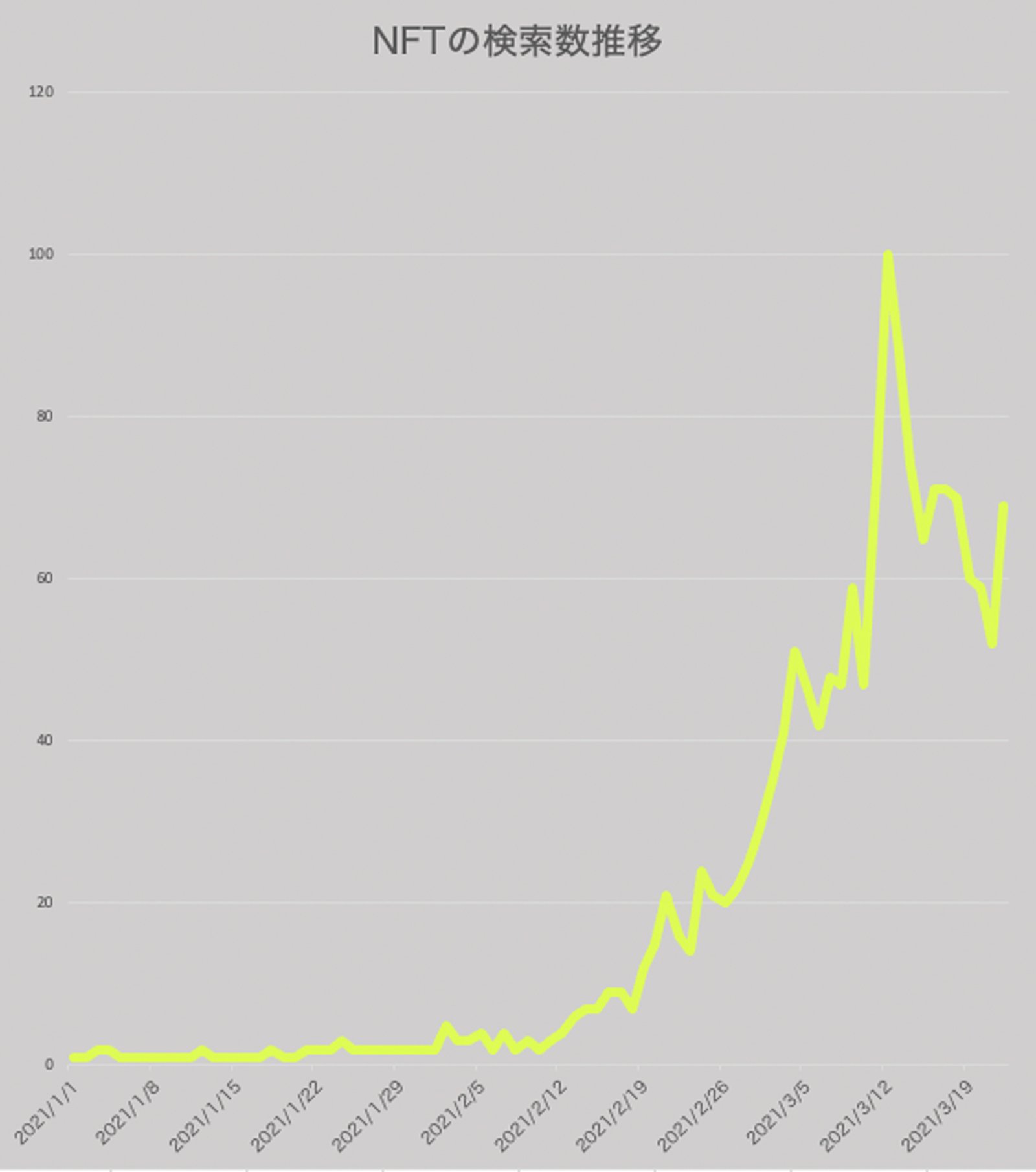宇宙人の画像が8億円以上もの価格で落札された──ネット上で誰でも見られる画像や投稿が「NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)と呼ばれるデジタルアイテムとして、高額な値段で取引をされているというニュースが相次いでいる。一体何が起きているのかと疑問に思った方も多いのではないだろうか。
そもそもNFTという言葉自体、最近になって初めて聞いたという方も多いだろう。だが実は、暗号資産業界を中心にここ1〜2年でジワジワと注目を集める存在だった。NBAプレイヤーの名シーンがデジタルカードとしてNFTで販売されたり、英老舗オークションハウスのChristie's(クリスティーズ)でNFTを用いて制作されたデジタルアートが競売にかけられたりと、誰もが知っているような企業や団体が相次いでマーケットに参画したことで一気にマス化しつつある。
この記事では、今注目のNFTとは何かという基礎知識からこれまでの歴史、そして今後の可能性について解説する。
“世界に1つだけ”を生み出すトークン「NFT」
前述のとおり、NFTとはNon-Fungible Tokenの略称であり、ブロックチェーンテクノロジーを活用して、唯一無二の「一点もの」を生み出せるトークンだ。ブロックチェーン技術を活用する事でコピーできないデジタルデータを作成することができ、データの所有者は自由に二次流通を行うことができる特徴がある。
NFTは一体どのように生まれたのか。それは2016年頃にさかのぼる。Bitcoin(ビットコイン)ブロックチェーン上にメタデータを付与することで、それぞれのビットコインに一意性(ユニーク性)を持たせる実験が行われたのだ。これは一意性を持たせることで、ビットコインのブロックチェーン上に実世界の資産を表現・管理することができるのではないかという試みで、今振り返って考えてみるとNFTのような存在だったのかもしれない。しかしながら、この試みはうまくいかず、続かなかった。