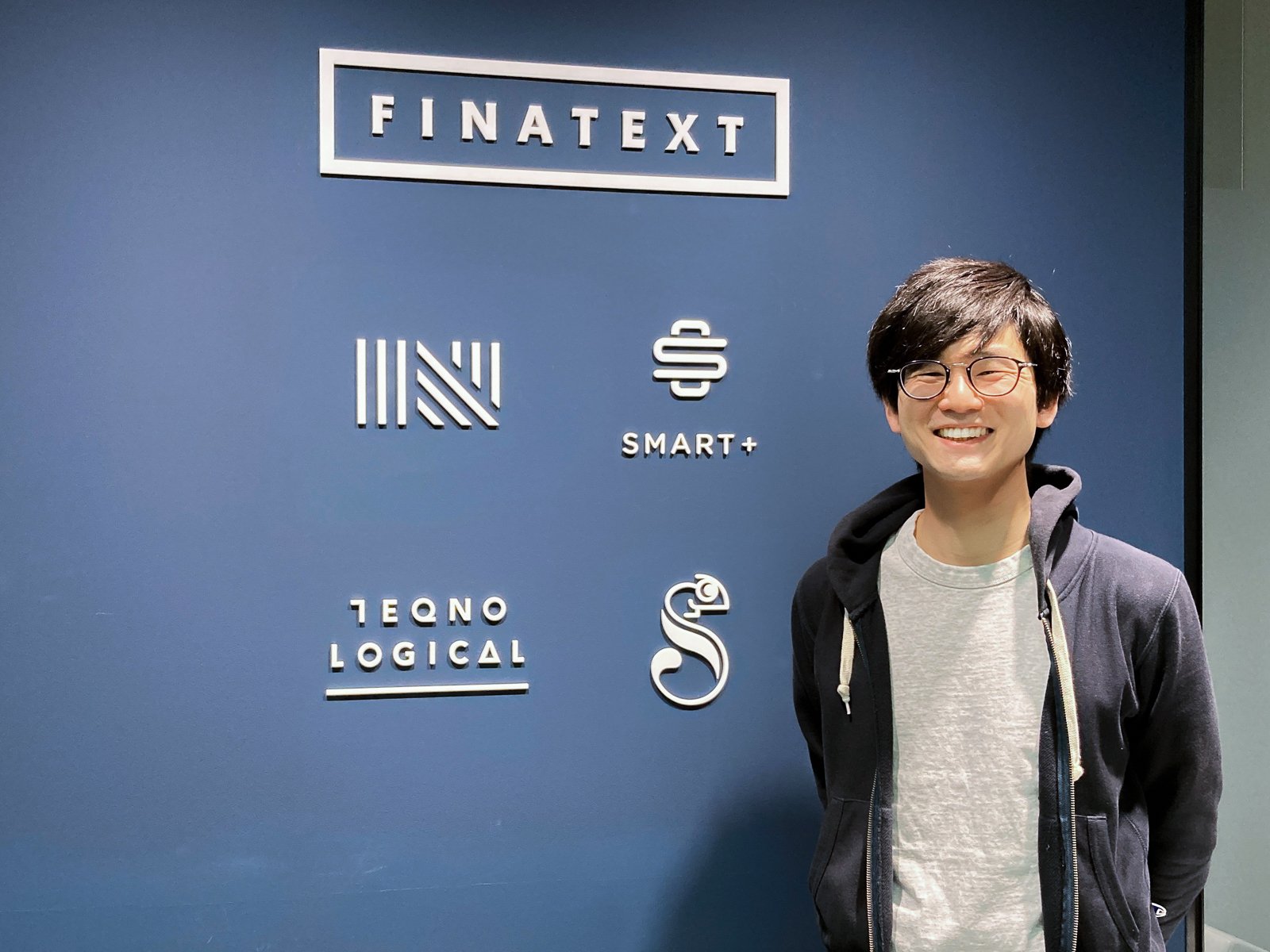
「金融サービス」は銀行や証券会社といった金融機関が運営するもの──。その前提が大きく変わりつつある。
Uberがドライバー向けの金融サービスを開発したり、LINEが決済や資産運用など金融サービスを続々とローンチしたり。“顧客との接点”を持つ事業会社が金融領域に進出する流れが国内外で広がってきた。
その中で注目を集めているのが「Embedded Finance(エンベデッド・ファイナンス)」という概念だ。
組み込み型金融やプラグイン金融などとも訳されるこの言葉は「非金融系の事業者が既存サービスに組み込む形で、金融サービスを提供すること」を意味する。まさに上述したUberやLINEの取り組みがその一例だ。
近年はさまざまな事業者が低コストで金融サービスに挑戦できるように、APIを通じて必要な基幹システムをまるっと提供するプレイヤーも増え始めた。




