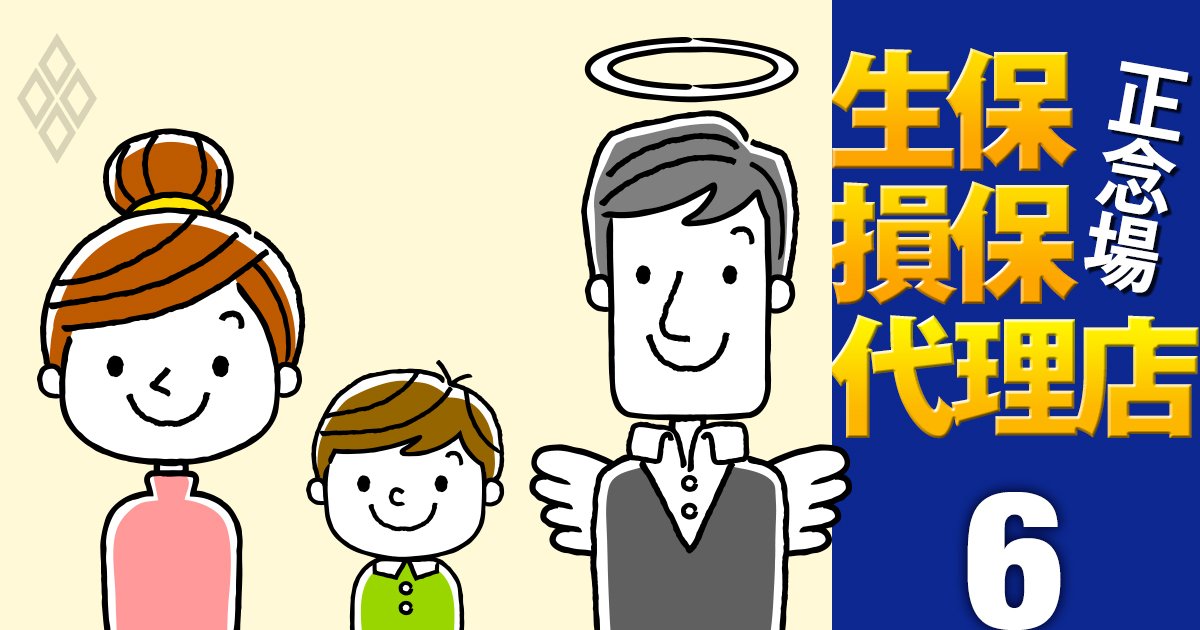「日本にはGAFAと渡り合える企業が生まれず、オードリー・タンが現れない、と悲観的な言葉で嘆くのは待ってほしい」──そう語るのは日本のさまざまな組織でDX(デジタルトランスフォーメーション)に向き合う人々を取材し、書籍『ルポ 日本のDX最前線』(集英社)としてまとめた著者・酒井真弓氏だ。
政府をはじめ、小売、飲食、金融、製造、エンタメなどの各業界でDXに取り組む組織や企業の試行錯誤を追ってきた酒井氏が、小売業界で注目した企業のひとつが福岡に本社を置くスーパーマーケットチェーンの「トライアル」だ。
トライアルグループの技術革新の中核を担うのは、Retail AI。売り場の欠品や顧客行動を可視化するAIカメラや、セルフレジ機能付きスマートショッピングカートを開発し、他社への販売も積極的に行っているIT企業だ。DXを実践するトライアルとRetail AIの取り組みについて、Retail AI代表取締役社長の永田洋幸氏の話からひもとく。
※本稿は、酒井真弓『ルポ 日本のDX最前線』(集英社)を一部抜粋・再編集したものです。
イノベーションは“ハイテク”ではなく“レトロフィット”から生まれる
永田には、DXを進める上で大切にしていることがある。それは、テクノロジー先行ではなく、現場のオペレーションに寄り添って変化すること。永田は、「レトロフィット(古いシステムに新しいテクノロジーや機能を追加して改良すること)」と表現する。