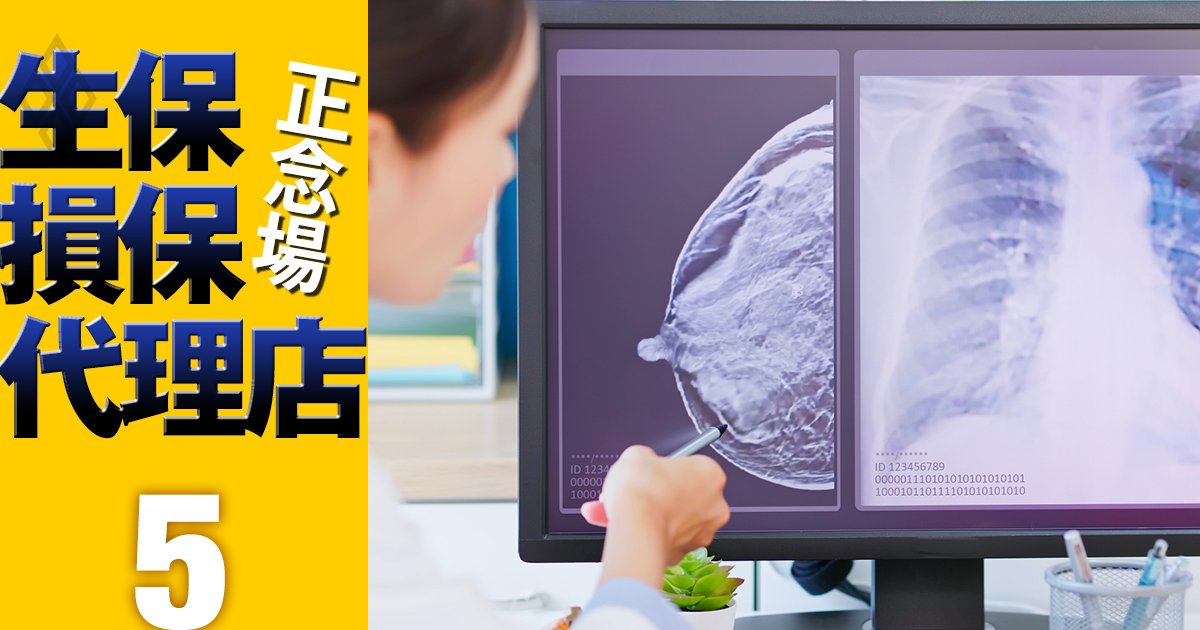食べ残しや売れ残り、賞味期限が近い──こうした理由から、本来食べられるのにもかかわらず食品が廃棄されてしまう“食品ロス”という問題。
農林水産省が今年の4月に発表した「平成30年度の食品ロス量推計値」によれば、日本の食品ロスの量は1年間で600万トンとなっている。この量は、国連世界食糧計画(WFP)が1年で世界中に行っている食品援助量の1.5倍だ。
全世界が解決すべき共通の課題としても知られている食品ロス。「SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)」の目標12「つくる責任とつかう責任」として取り上げられており、具体的な目標として2030年までに世界全体の1人当たりの食料の廃棄半減と、生産・サプライチェーンにおける食品の損失の減少が掲げられている。
そうした目標の実現に向け、“賞味期限が残っているのに廃棄されている商品”を扱うことで食品ロス問題の解決に取り組んでいるのが「トクポチ」だ。
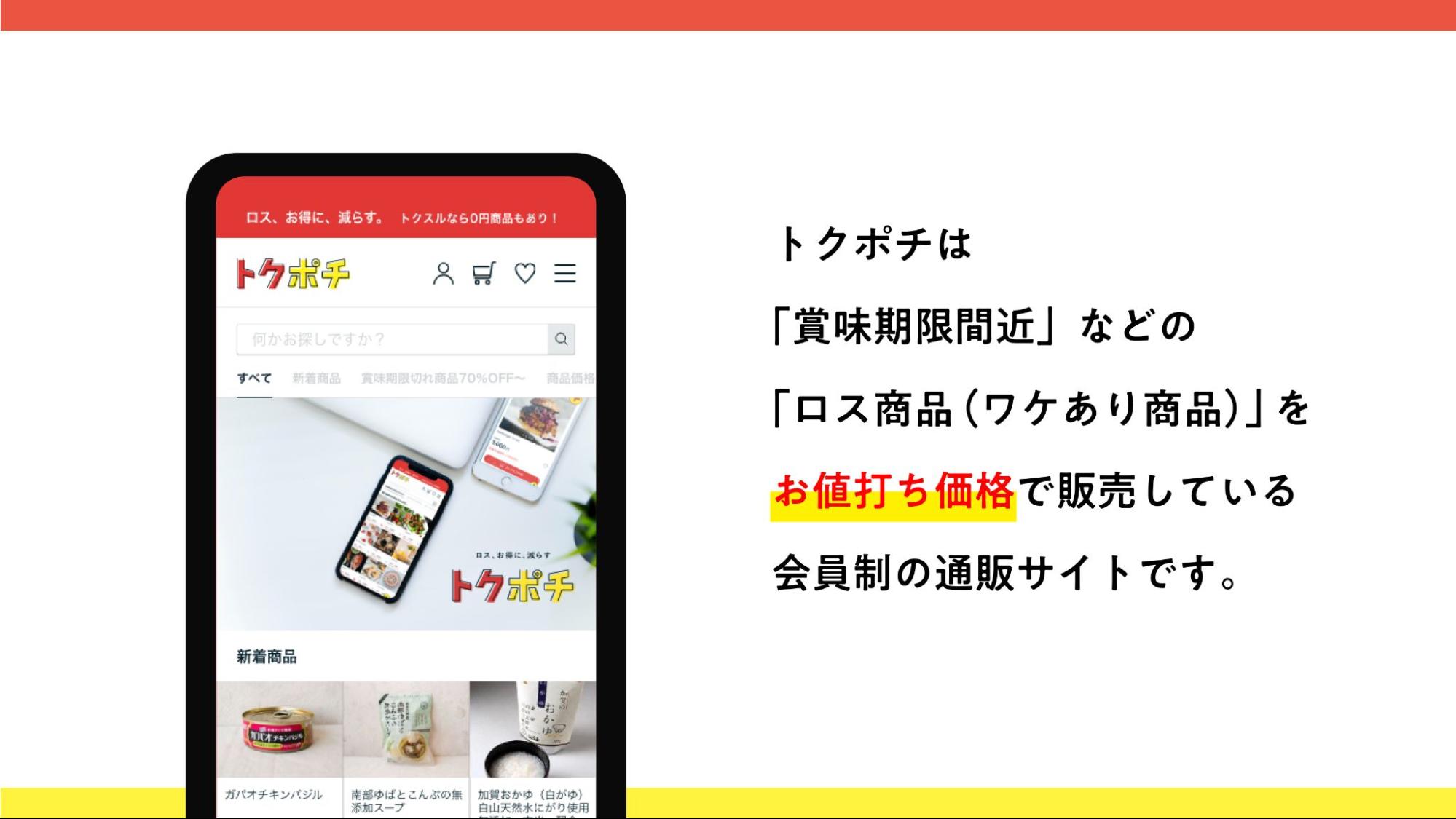
トクポチは「賞味期限間近」などのワケあり商品をお値打ち価格で販売している会員制の通販サイト(一般会員は月額130円、プレミアム会員は月額330円)。基本的に市価(市場で出回っている価格)の60%オフから商品を販売し、発売から1カ月経過した商品については「価格0円」で販売する仕組みになっている。このトクポチの仕組みはどのようにして実現したのか。以下は、運営元であるSTRK代表取締役の「我時朗」こと佐藤隆史朗氏のコラムだ。